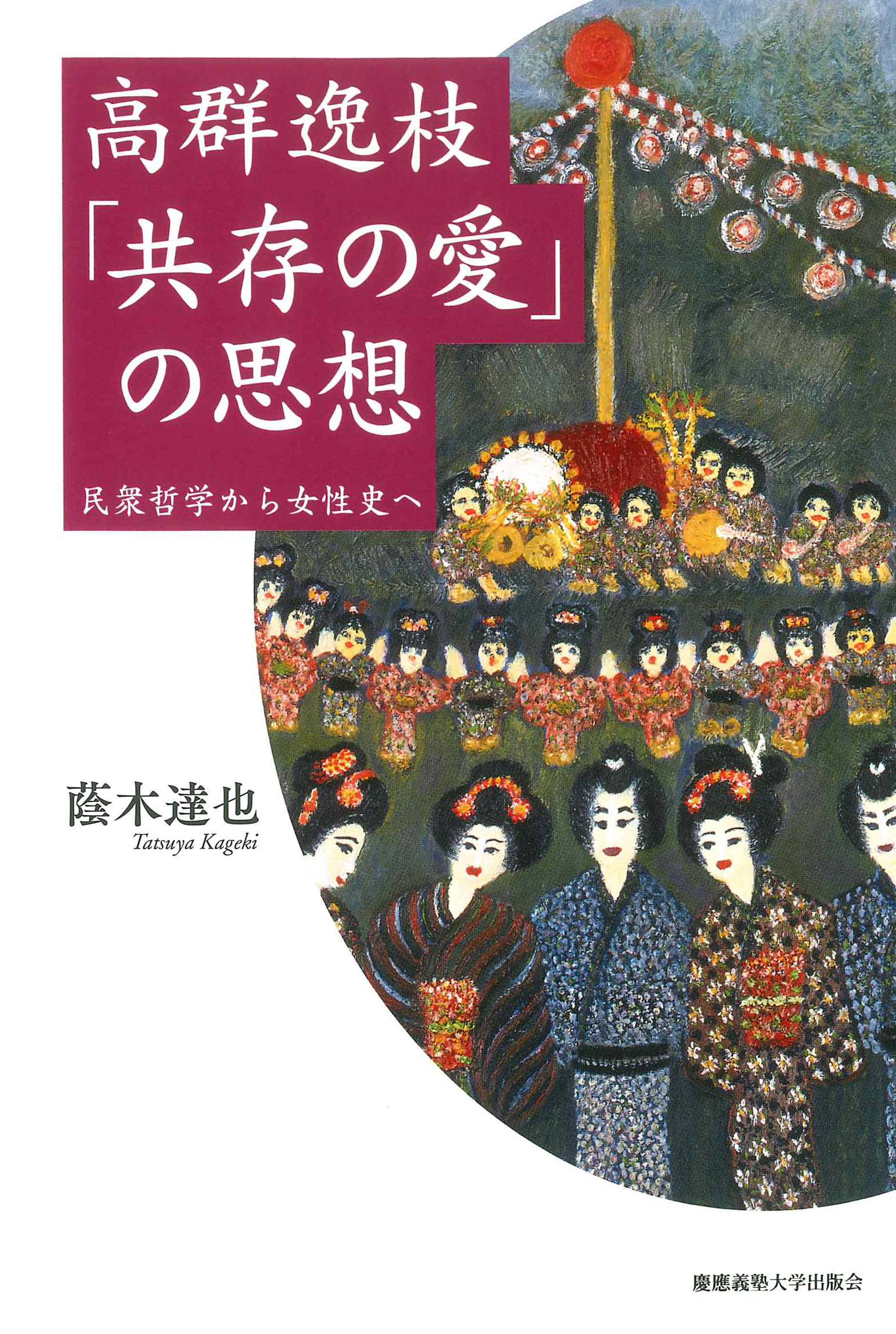
いま読むべき高群逸枝の思想 共存と排外が結びつく論理
高群逸枝(1894-1964)は、あらゆる差別の廃絶を願う女性解放論者で、戦前はアナーキズム陣営にいて、戦後は著名な女性史研究であった。高群はまた、「日本女性」を特別視する民族主義者で、戦時下には女性の戦争協力の旗振り役で、「母性」論の担い手であったとも評される。
そして、高群をめぐる全く相反するように思われるこの二つの評価はいずれも正当であり、高群の思想において、両者は矛盾するどころかむしろ一貫している。その論理を「共存の愛」という概念から辿るのが本書である。
これまでの高群研究者たちは、前者と後者の間に苦心して分割線を引いてきた。例えば歴史研究に向かったときに、あるいは戦争が始まったときに、高群に転向があった、そしてまた、戦争が終わったときに、再び転向があった、というように。そして、戦後の転向のあとに、戦争に対する反省の弁がなかったことを批判しもしてきた。
しかしそうした分割線を引くこと自体が、高群の思想を理解する上で混乱をもたらしてきた。ある時代の政治状況の把握においては有用である「左翼」「右翼」あるいは「体制」「反体制」といった分類が、高群の思想を理解する上で妨げとなっていたのである。
高群は、「愛」の力であらゆるものを「肯定」する社会を理想とし、「愛」の担い手、そして自由な社会に向かう人々として、「婦人」「母」「農民」「母神」、そしてそれらの人々に支えられる国(として高群が想定していた)「日本」を重視した。
差別がなく、誰もが共存する社会。誰もが「美」を「肯定」され、「愛される」社会。高群の理想はあまりに美しい。そして、高群は考える。その実現のためには、共存を脅かすような存在を排除しなければならない。母が我が子の出生を待ち受ける心に、性別や能力によって人を差別するような思想を吹き込んではいけない。女性の美しさに、お金を掛けた化粧や服飾の多寡で美醜を区別するような思想を吹き込んではいけない。自他それぞれのあり方を愛をもって尊重する日本の女性に、西洋列強の自己を優先し他をさげすむような思想を吹き込んではいけない。共存を脅かすような敵国には、戦意を鼓舞して男性兵士を送り込まねばならない——。
高群の論理は一貫しており、「共存」という思想の陥穽は明白だ。差別を拒否するために差別するものを排除することを認め、共存を守るために共存しないものを否定することを是とするなら、高群の思想の道行きを誤りだと断罪することはおろか、批判者自身が高群と同じ道を辿ることになろう。
高群は、存在の肯定、恋愛や美醜、生理や妊娠出産による差別への反感など、民衆や女性としての自身の経験や心情に根ざした新たな社会を探し求めた。そこに見出したものが、アナーキーな古代母系制の社会だった。その立場から、当時正しいとされた思想——昭和初期のマルクス主義や戦中期の皇国史観、古代日本史研究における父系制連続説など——に抗った。高群は日本古代史をモデルとし、戦中は天皇を通じて世界の秩序を担うものとなるもの、戦後は世界の平和を先導するものとなるものとして、日本女性を特権化した。
近年の研究が指摘している通り、高群逸枝の女性史研究は「意図的誤謬」のような改竄が加えられたものではないし、在野で研究していた高群にそこまでの器用さはない。むしろ、当時科学的で世界的普遍性があるとされた唯物史観に合致しない古代日本の家族や婚姻のあり方が、世界に卓越した「日本女性」という高群の解釈に裏付けを与えるかのように思われ、その立証としての女性史研究へと高群を駆りたてたのだった。
今日でも、「絆」や「共生」、「利他」や「ケア」といった概念は、人々がともに生きる支えとなる概念でありながら、他方で誰かを苦しめる軛、あるいは排除の論理となる危険性をも孕む。
「共存の愛」も魅力的で危険な概念であろうが、それを単に——「共存」や「愛」はわかりにくい、気持ち悪いといって——退けるのではなく、むしろ積極的に、批判的に吟味し続けることは、現代にもつながる有益な視座を与えてくれるはずだ。
高群の著作そのものはとっつきにくいが、本書はそれをある程度わかりやすく分析したつもりである。高群に関心がある人はもちろん、高群に抵抗がある人にこそ、一読をお願いしたい。
◆書誌データ
書名 :高群逸枝 「共存の愛」の思想 ——民衆哲学から女性史へ——
著者 :蔭木達也
頁数 :352頁
刊行日:2025/09/25
出版社:慶應義塾大学出版会
定価 :3960円(税込)







![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)











