
素敵な料理が登場する食のワークショップ
猪、長芋、ワサビなどから華麗な料理誕生
鳥取県倉吉市で2025年3月4、5日、食のワークショップを開催していただきました。地元ならではの食材「ねばりっこ(長芋)」、ジビエ(猪)、ワサビを中心に、特産の「ほし柿」、「大豆(「神のつぼみ」大豆水煮)」など組み合わせ料理を作るというもの。料理は20種類もでき、華やかで味わいも豊かで、参加メンバーでの食事会は至福のひとときとなり大好評でした。なにせ地味そうに見えた長芋、食べたことがない猪肉などが、見事な料理となりずらりと並んだからです。
猪は「猪肉のシェパーズパイ」、「猪肉の肉煮込みうどん」、「猪肉の肩ロース煮込み」、「猪肉の叉焼(チャーシュー)」、「猪肉の三枚肉のニンニクソース」、「猪肉の酒かす漬け」、「炒芦菜猪(猪肉とセロリの炒めもの)」に。ねばりっこは「干し柿きんとん」、「わさび醤油漬け」、「わさび丼」、「羊かん」、「八方とろろ」。わさびは「ささ身のわさびピカタ」、「わさびドレッシングサラダ」、「ニジマスのステーキ」、「ニジマスとワサビと白ネギのあえもの」。大豆は「大豆のディップ」などになりました。
なかでも驚嘆したのは、「猪肉の肩ロース煮込み」。肩ロース猪肉に切れ目を入れ、プラムを挟み、塩胡椒して糸で巻き、オリーブオイルで炒めたものに、玉ねぎ、人参、リンゴジュース、クローブ、ベイリーフ、タイムを加えて、猪肉が柔らかくなるまで煮た料理です。こんな極上の肉料理に猪がなるのというほどの絶品の美味さ。
「ねばりっこの羊かん」は、ねばりっこの皮をむいて薄切りにし、酢水に漬け洗い、軟らかく煮て、プロセッサーでつぶし、それを寒天(水に一晩入れふやかし火を入れたもの)に入れ、砂糖を少々加えたものを、菊を散らした流し箱に入れ、冷やし固めたもの。箱から取り出し、切って、青い皿に並べると、羊羹の中に、黄色い菊の花がうっすらと浮かびあがるように見えて愛くるしい。綺麗で可愛らしく上品で甘くぷりぷりとした食感が口内を幸せに包みます。
塩胡椒したニジマスを焼いて、バター、小麦粉を入れて火を入れブイヨンで伸ばし、すりおろしたわさびをたっぷり入れた「ニジマスのステーキ」。小さな食用花が上に飾られ、紫、薄紫、薄紅の花弁に黄色の雄しべと雌しべが彩り鮮やか。ニジマスの横には野菜サラダが添えられて華やかなこと。
料理に使われた食用の花や、ほかの食材は、近所のスーパーで手に入るものばかり。それだけに料理をされた方たちの感激もひとしおでした。



参加した方から「レストランを何軒もはしごしたみたい!」「美味しかったです。胃袋の容量が足りませんでした」「生産者のお話を聞け、とてもいい機会となりました」など、嬉しい感想が寄せられました。
会場は、倉吉市の地区公民館「上灘(うわなだ)コミュニティセンター」内の調理実習室。農業や食に携わる女性13名が参加し、料理を手掛けてくださった。しかもメンバーを代表して、ねばりっこの農家・堀本良子さん、猪肉の精肉を手掛ける工房「日本猪牧場」徳岡遙さんが、料理披露の前に、食材をパワーポイントで紹介するという趣向。食に対する思いも伝わり、料理をさらに輝かせて見せてくれたのでした。

「ねばりっこ」は、平成17 年に鳥取県園芸試験場育成の新品種として導入されたもの。粘りが強くアクが少なく果肉が白く緻密なのが特徴。「日本猪牧場」の徳岡遙さんは、嫁いできて、義父の猪精肉の販売と紹介の仕事を手掛けるようになったといいます。最初は「猪は臭くて嫌だ」と思っていたのだそう。ところが捕獲から敏速な解体処理までの過程を実際に見て、衛生管理された施設と正確な技術によって上質な精肉になることを知って、その魅力に目覚めます。実際には臭みもなく、ジビエの評価は高い。市・県・国もジビエを推奨している。しかし十分に知られていないこともあり、多くの人に広めたいとワークショップに参加したといいます。
わさびは、標高1,792mの大山(だいせん)から流れる清流の中で栽培されている。青々としたワサビの葉がひろがるわさび畑は、自然との風景の調和が素晴らしく圧倒されました。しかし地元では、あまり食べられていません。新たな食べ方を広げたいという要望もあったのでした。
料理指導に料理研究家の馬場香織さんを推薦。これまで何度もワークショップをご一緒させていただいていて、その活動が今回も繋がった。東京在住の馬場香織さんとの事前の打ち合わせは、ZOOMでのオンライン会議。メインの食材を馬場さんに送り、レシピを作ってもらい、ワークショップ当日に、馬場さんが東京から入り、現場に臨むという形がとられました。嬉しさもひとしおでした。
調理実習室には、調理台が4つあり、各台に3名から4名がつき、馬場さん作成のレシピが、各班に4つほどわたされて馬場さんの指導のもとに料理を作る。馬場さんは、調理台をくるくるめぐり丁寧にアドバイスをし、自らも料理を手掛けながら、ときに、みなさんに味見をしてもらい仕上げていきます。みんなが実際に料理を作るのです。1日目は仕込み、2日目は関係者を招いてのお披露目。

食のワークショップ参加の方々。前列中央が馬場香織さん
このワークショップ開催のきっかけは知り合いから紹介された小田急電鉄株式会社経由からでした。2023年1 月、倉吉市と小田急電鉄㈱が包括連携協定を締結。目的は地域価値創造型人材の創出を基軸に持続的なまちづくりへの推進。その中で農業振興のアドバイスを求められたのでした。早速、現地に赴き、主要産物の梨、スイカ、わさびなどの農家の現場、猪の精肉工房を視察させていただいた。いずれも農業の大きな力となっている。そこで食のワークショップを提案したところ地元のメンバーのプロジェクトで見事に形にしてくださったのです。
倉吉プロジェクト 倉吉の魅力発見事業・農産品に関する食のワークショップ実施報告書
長芋(ねばりっこ)、猪、わさび
https://www.kanamaru-jp.com/data/workshop/pdf/workshop20250327.pdf
スイカ、鹿肉、葉わさび、ニジマス
https://www.kanamaru-jp.com/data/workshop/pdf/workshop20250729.pdf
イタリアのスローフードからの衝撃
ここからは馬場香織さんとの出会い、それ以前にそもそも私がこうした活動に関心をもったきっかけについて、紹介させてください。もう20年以上も前のことです。これまでの私の活動を知った方が、「あなたがやっているのはスローフードの活動だね」と言われました。しかし、当時、さっぱり意味がわかりません。そこで2002年9月にイタリアへ取材に行きました。そこで仰天しました。スローフードが国内で4万名、全世界で10万名の会員を持つNPOであること。
もともとはジャーナリストであったカルロ・ペトリー二氏が立ち上げたもので、地域の今では有名となったワイン・バローロの葡萄の生産地ランゲ地方の地域調査や、小さな食の体験ツアーから始まったこと。そこから農家に所得と経済をもたらし若者の定住に繋ぐことができるよう、葡萄栽培から醸造、加工、販売までのサポートをしていくことが始まり、やがてプロモーションを手掛ける団体に。つまり生産だけはなく加工・販売で農家の所得を増やす仕組みです。
別会社で出版、コンサルタント、大学運営まで行い、州政府、町の食の事業の委託を受けて、食のプロモーション事業展開をしていることを知ります。NPOの会費だけでも3億円以上を集めています。
プロモーションは州政府から1億5000万円の委託費を受けていました。そして徹底した食の現場を大学とも連携して調査し、ガイドブックを作成して販売されています。とりわけ成功したと言われるのが「オステリア・デ・イタリア」という食のガイドブック。これは覆面調査で、町や村の個人経営の食のお店を紹介するもので、大衆版ミシュランと呼ばれたものです。この成功が大きくスローフードを引き上げたとも言われています。現地調査を徹底してテキストを作成し、「多様性のグローバルを目指す」がミッションになっていました。

スローフードの書籍。左からの2つは伝統的な食を調査したガイドブック。真ん中は、ソムリエが選定したワインガイドブック。右から2つ目が「オステリア・デ・イタリア」。右端は、有名なワインとなったバローロのランゲ地方の土壌、環境を調査したもの

食の祭典「テッラ・マードレ」で演説をするカルト・ペトリー氏
さらに食の祭典を州や町から委託を受けてプロモーションし、調査した食を大々的に売り出す。小さい農家に経済を回す。食のガイドで地方へお客を誘致する観光に繋ぐなど地域経済に繋ぎ、地域の人がノウハウを獲得し、自らのイノベーションを生み出す仕組みになっていて驚愕しました。スローフードのもっとも優れた取組は、地方の山村の農家の経済を創る仕組みに貢献したことでしょう。
カルロ・ペトリー二氏の「宣言するより実行せよ」という言葉にはもっとも影響を受けました。また出版に携わってきた私にとって、スローフードのような出版の形があるのかというのも、目からウロコの出来事でした。
ここから、自ら現場に行く、全体を観て記事を書く。また食をテキスト化する。地域の食材を調査して参加型のワークショップで料理を作る。ノウハウを地域で共有する。地域の人が自らの力で発信ができるようにするという試みを各地でするようになりました。そして書く、本にする、食のワークショップを開催する、ツアーに繋ぐ活動が始まります。本を書いたことで、大学や自治体などの講師などにも呼ばれるようになりました。
イタリア食文化を教える外国人向け料理専門学校ICEF
スローフードの祭典には、その後、再び行くこととなります。当時、雑誌「ソトコト」(木楽舎)では、スローフードの特集が組まれていました。そんななかで、木楽舎を創立した小黒一三さんが三國清三さんなどとともに、スローフードの祭典「サローネ・デル・グスト」に行かれることとなったのです。三國さんは、招聘を受けて、祭典で料理を披露されることとなっていたのです。
この祭典に同行させていただくこととしました。その代わり、ピエモンテ州ブラ市にあるスローフード・インターナショナルに行き、取材をさせていただき、その活動内容を訊くこととしました。コーディネーターは、当時、イタリア現地のスローフード協会にいらした石田雅芳さんです。石田さんは、その後、立命館大学・食マネジメント学部の教授になられて日伊の食文化の交流・研究をされるようになります。
スローフードについては、『スローフード・バイブル イタリア流・もっと「食」を愉しむ術』([著] カルロ・ペトリーニ [訳] 中村浩子/NHK出版)を何度も読み、付箋を貼り、素朴な疑問を書き出して学び、石田さんを介して、現地取材を行いました。現地ではカルロ・ペトリー二さんにもお会いできました。そして取材結果を、書籍『スローフード・マニフェスト』(石田雅芳との共著/木楽舎)としてまとめました。この本は、スローフード協会の正式な認定を受けた本となりました。その取材のなかで、地域経済とイノベーションに繋ぐ、実に細やかな地域の調査や、ノウハウの連携、地域産物のプロモーション、アドバイス事業、直販やバイヤーに繋ぐ仕組み、産官学金融連携での取り組みがされていること知りました。



城をリノベーションして生まれたICIF
このとき、三國さんと尋ねた外国人向け料理専門学校 ICIF(Italian Culinary Institute for Foreigners)には、とても驚きました。ピエモンテ州アスティ県コスティリオーテにあります。これがなんと1000年前のお城。それが学校になっているのです。ここから日本人が学び、5000名以上が卒業し、日本国内でもイタリアンレストランが増え、イタリアの食材が輸出される大きなきっかけをもたらしています。教育を通して食文化を発信する活動に目を見張ったのでした。実は、この専門学校には、のちに長男・金丸知弘に留学を勧め、学びに行くこととなります。彼が現地で体験したリポートを出してくれました。そこには、イタリアの食の現場を学ぶだけでなく実際のレストランでインターシップを行い、お客さんに料理を提供し、それで認められれば卒業となります。

この学校ができたきっかけが、実は、日本のイタリアブーム。1988年、イタリア・トリノ郊外ジェットホテルのシェフで経営者でもあるブルーノ・リブラン氏が東京・銀座に招かれたのですが、当時、日本には、イタリアのまともな食材がなく、イタリア料理を作るには程遠い状況でした。彼は、イタリアに戻ると、関係者に、日本がイタリアの食の知識が十分でないばかりか、食材もそろっていないことを話し、協力を呼びかけ、州政府、EUの協力も得て、城をリノベーションし、イタリア国外の人たちに、一からイタリアの食を学ぶ専門学校を創設したのです。この学校は短期コースもありますが、マスターコースというのがあり、一流のシェフたちが教えに来ます。
<ICIFの2つのマスターコース>
•マスターコースレベル Ⅰクラス(8ケ月)
前期:1ケ月 ICIFにて基礎講習と実習
後期:7ケ月 提携先レストランでインターンシップ
•マスターコースレベル Ⅱクラス(1年)
前期:2ケ月 ICIFにて基礎講習と実習
後期:10ケ月 提携先レストランでインターンシップ
他に、短期コースというのもあります。イタリア料理が好きで、簡単な調理ができる方(年齢、経験は不問)。8名以上のグループで、1日コースや2・3日コースも出来ます。食事・宿泊付き。
まず驚いたのが、古城が学校になっていること。しかも城のなかには、イタリア全土のワインがあり、これらは各地のワイナリーの協力でそろえられたもの。学校の授業では、ワインをティスティングして、料理とのマリアージュを学ぶようになっています。学校で基礎を学び、そのあと7か月から10か月、実際のレストランで実践を学ぶのです。この仕組みには驚嘆しました。
食の背景から学ぶ「味覚のワークショップ」
スローフードの祭典「サローネ・デル・グスト」の現地も訪れました。訪ねてみて初めて、そのイベントの規模に 驚きました。 トリノのリンゴットという大規模な会場をまるまる使い、一日ではとうてい観ることができないような、さまざまな食に関する展示や食のワークショップが繰り広げられています。
食にまつわる著名人やジャーナ リストの講演はもちろん、イタリア 全土からの、手づくりのチーズや生ハム、サラミを始め、オリーブオイル、パスタ、ワインなどのブースがずらりと並んでいます。それらはスローフード協会が地域を調査したそのうえで、地元の伝統的な手法、材料などで作られた厳選したものです。ブースのどこにも生産者や加工業者が立ち、試食コーナーとカラー刷りのパンフレットが置いてあります。つまり顔のみえる関係が築かれているのです。
そして会場は商取引の場にもきちんとなっています。バイヤーや料理人も呼ばれます。世界各地からスローフード協会が呼びかけたジャーナリストも多く参加しており、取材レポートをすぐに配信できるためのインターネットの設備のある特別プレスルームとプレスのための詳細な色刷りのパンフレット、会場マップなども用意してありました。
当時の国際理事で、日本にもたびたび訪れていたジャコモ・モヨーリさんが、会場のなかで、とくに熱を入れて紹介をしてくださったのが「味覚のワークショップ」です。いくつもの教室が並んでいて、「ここでは、食の背景や文化から学ぶ味覚のワー クショップを行うんだ」と自慢げに話してくださいました。 味覚のワークショップは、食の素材をいくつも並べて、味わい、香り、見た目、食感、音、栽培法、加工法など、その違いを、実際に食べながら比較し、言葉にしてメモをしていきます。ワイン、オリーブオイル、サラミ、ハム、菓子類など、さまざまな食材ごとにワークショップが開かれるのです。
例えば、チーズ一つにとっても、牛の品種、羊、ヤギなど家畜の種類、地域の加工法や熟成の違いで、すべて見た目も味も香りも異なる。その違いを、一皿に並べた6種類ほどのチーズを、一つ一つを専門家のレクチャーを受け、生産地のことや、家畜の飼育法や、ミルクの違い、熟成方法、環境などの話を聞きながら食べ比べるのです。さらにワインとの相性をみたりもします。ワインもソフトタイプからハード系まで何種類かが用意されます。
専門家のレクチャーは例えばこんな具合です。「皿の上のチーズに小さな旗が立っていますが、そこから右回りにティスティングをしていきます。最初のチーズは山間地のヤギのチーズです。放牧しているもので、樹木の葉を食べたりしています。生産量が尐なく、生産する人も高齢化をしていました。加工する人によって品質のばらつきがあったために、スローフード協会が調査を行い、安定的に製造できるようにアドバイスをしました。これらのチーズをプロモートして、継続してできるようにしました。美しい白色なのは熟成が浅いためで、香りは、草原の獣の優しさがあるでしょう。二番目のチーズは、外側が茶色いのは熟成が進んでいるためです。塩味と酸味があります。しかし、中を割って香りかぐと、まるで胡桃のようです」。
これほどチーズごとに個性が違うのかというのを初めて知ったのでした。その背景や環境が語られることによって、特徴が明確にわかる。まるで科学の時間のようです。実際、スローフードの味覚の講座は、生産、流通、環境、品種など総合的に学ぶ科学的という位置づけになっていました。このワークショップを知ったことで、単純に食べ比べるたけでも、同じ食品だと思っていたものが、素材はもちろん、地域性や加工によって多種多様な味わいがあることを理解できたのでした。しかも際立った個性があります。食べ物の材料や地域性や環境までを知り、本当においしい物を自分たちで選択できる力を身につけることとなります。ここから料理展開までを学び、豊かな味わいを知ることができるようになります。こうして多様な地域の文化的な食に、 経済性を加えて、地域に持続させていく仕組みを組み立ていくようになっています。
講師になるのは、ソムリエや、スローフード協会の食の地域調査に携わった専門家や、大学の食関連の教授、生産者など、様々なプロフェッショナルを交えて行われます。大量生産をしているところの関係者は講師には選ばれません。 味覚ワークショップは、一般の人の参加も多いが、バイヤーやレストラン関係者、食品会社、料理家なども受講します。これによって、より洗練されたおいしいものを手に入れることができるようになるわけです。料理を行ううえでも、どれとどれの組み合わせで、どんなものができるかを具体的に示すことができます。店舗においては、店の特徴を出せる品揃えをすることができるというわけです。この手法は、地域の小さな伝統的な食べ物を残し、経済的な基盤を築いて地方に残すためにあみだされた手法でもありました。ワインのティスティングの方法が発展したものです。
代々受け継がれていた地域性の高い食品、家畜や種の品種や、地元に受け継がれた技法などが、グローバリゼーションとファストフードを代表とする大量生産の食品がまん延するなかで、次々と失われて行く。これは日本でも同じです。 そのなかで、昔ながらの伝統的な食や、いいものを守りましょう、食べましょうといっても、なかなか広がりません。そこに経済性をともなう必要があります。なにより、消費者に理解させるための教育の場が必要です。なぜなら大手メーカーの手によって大量に作られる食品が、大手スーパーやチェーン店で一般化した現在、多くの消費者は、もはや、地域の手作りの食品など、ほとんど食べる機会がなくなり、どんなものかさえ理解されていないというのが、現実だからです。 そこから生まれたのがさまざまな食材を比較しティスティングして、個性と味を知る「味覚ワークショップ」でした。
そして、マーケティングの専門家も交えて、地域性のある食材の商取引とプロモーションの場として誕生したのが、最初の「サローネ・デル・グスト」のイベントです。素材を調査するための専門の委員会があり、地域から調査が行われます。なかでも絶滅の危機にあるものは、「プレシディオ(味の箱舟)」に選定されて、スポンサードをつけて、祭典でプロモーションがされます。 また調査したものは、本になり出版もされます。出版物は、商品を購入するための手引きとなり、観光地の食のガイドになります。教えるための教材のテキストにもなります。広告も入れられて販売もされます。本の売り上げは、スローフードの継続的な活動に使われるというわけです。
多様性のグローバリゼーション
食の地域調査からブランド形成と観光事業と地域雇用と作るスローフード協会の会長カルロ・ペトリーニ氏は「画一されたグローバルな食品がまん延するなかで、われわれは、多様性のグローバルゼーションを目指す」と宣言しました。また「味覚は文化である」とも。これは地域性の味こそ守るに値する文化と同格の価値あるものであるということです。こういった具体的な手法は、まさに安心安全な食のより視覚的、味覚的なアプローチです。 スローフードは、日本では、いまだ、伝統的な料理のことや、ゆっくり食べることなど、食べ物のことと誤解されています。だが、イタリアの本拠地では、環境と伝統的な食材や技法を残し、これらを地域経済に結び持続社会を創るための運動であり活動であり事業となっています。 スローフードは、食文化をテーマにした事業体です。120名を雇用するイタリア最大の食のNPOです。さらに彼らは、集まった情報をもとに別会社で食をテーマにした出版活動を行う出版社と、コンサルティングを行う会社の別会社、さらにスローフード食科学大学を運営しており、人材教育から食関連のイベント運営から食品会社のコンサルタントまで手がけている組織なのです。
2005年、イタリア・スローフード協会の創設者で、会長カルロ・ペトリー二さんが来日したのでした。滞在は2月23日から3月4日まで。この間イタリア大使館の記者会見、日仏会館での講演会、丸の内ミクニでの懇親会と都合3回会うことができたのでした。
実はペトリーニさんとは2002年のトリノのサローネ・デル・グストで、また2003年のブラのチーズのときに本部の中庭でお会いしています。
2005年の来日にあたっては記者会見のインフォメーションと農家との懇親会の呼びかけを手伝ったのでした。おかげで多くの生産家とも再会ができて楽しいものになったのでした。
記者会見と講演会でスローフードの食文化の明確な定義をじっくりと聞くことができたのでした。通訳は、石田雅芳さんです。
話は、スローフードの成り立ちがよく理解できるものでした。初期のスローフードの発足がワインと食文化の会であったのですが、ファストフードの出現によって味覚が均一化されるなかで、新しい世紀のガストロノミー(食文化)とはなにかと議論してきたことから打ち出した方向が味覚の多様性というコンセプトだったということ。そうしてNPOスローフード協会としての食文化を推進する事業が始まります。

とくに学校の味覚教育に力を入れ、それまでに1万5000名の教師がスローフードの教育プログラムに参加したといいいます。その大きなきっかけは子供たちが青いリンゴの香りをシャンプーの香りがすると言い、今では生産の現場から子供たち離れた環境にあり、本物が見分けがつかなくなっているということ。子供たちが正しい食べ物や飲み物を選択できるようになること、料理の知識や生産のことを知るというところから始まったということでした。
つまりスローフードのNPOが子供たちに正しい味と食を伝えることが根底にあったというわけです。学校での授業で使う教科書もあり、翻訳されて出版もされています。『味覚の学校』(プラート味覚教育センター、中野美季著/木楽舎)。
さらにもっとも危機感を抱いたのは食の大量生産による農業の衰退、画一された味、さまざまな種や畜産の淘汰であること。取材時にうかがったペトリーニさんの言葉をいくつか紹介します。
「ここ50年は食文化が根絶やしにされる時代だ。農村の知識や伝統的な文化を破壊してきた。1950年イタリアでは労働人口の48%が農業に従事していたが現在は約4%である。アメリカは38%から今や1%。日本は6%になったと聞いた(※注 総務省「労働力調査」では林業含め3%程度)。私たちはシステマチックなものから生物多様性を守る運動を始めた。生産を守るだけでなく知識を守ることを始めたのだ」
「今、一日の間に5種のフルーツや野菜が失われ、動物の種類も失われる。イタリアでは乳牛の種を4つ、8つの羊を失った。この状況は悪化している。それは大量生産をめざしたからだ。ソ連ではアゼロジューレという乳牛が存在した。一日当たりのミルクの量は15リットルだった。そのうち一日40リットルのホルスタインが出てきてアゼロジューレは飼わなくなった。種をなくしただけでなく、一つのチーズもなくしたのだ。何世紀にもわたってきた遺産であるにもかかわらず、生産性のために牛は犠牲になった。ガストロノミー(食文化)を考える人々は、今、本質を考えるときにきた」
「ガストロノミー(食文化)とは重要なものである。食文化は料理のことだと思っているかもしれないがそれは大間違いだ。複雑な科学の体系である。たくさんの学問からなっている。農業、畜産、食品の加工知識、その裏には経済活動がある。その多様な交流がないと食文化はない。そこには政治も経済も健康もあるだろう。もう一つの重要なことは肥満問題である。食品のクオリティとは賢い賢明なものである。他の科学文化と違うのは、複雑で多くの学科にまたがっているということだ」
そうしてスローフードの考える食文化の食品のクオリティについての話が度々登場しました。
「食品のクオリティには三つのファクターがある。一つは感覚的な、味がよいというクオリティ。味覚的においしいものでないといけない。それは文化的な価値という意味でもある。
二つ目は、環境を尊厳したもので、生態を壊すものであってはならないということ。除草剤を使った農業のように、生態系を壊すものであってはならない。
三つ目は、社会的に正統的なものであること。その生産活動に携わる人たち食品には正当な報酬(ほうしゅう)を受けていることが大切なのだ。これらの一つが欠けてもいけない」
さらに現在、イタリアも日本も食費にあてるお金がどんどん下がっていることから少し、まともな食べ物に支払いをするようにも呼びかけられました。さらに、東南アジアで行われている企業と商社による環境破壊のエビの養殖に対しての反対キャンペーンを行うこと、2004年にトリノで行った「テッラ・マードレ(母なる大地)」を次の年、今度は世界131各国5000名の生産者に加えて大学教授、シェフ100名を加え食文化と多様性を世界発信するということ、それに日本からももっと多くの人が参加するように呼びかけたのでした。この講演は、圧倒的な熱量でした。
国際会議「テ ッラ・マードレ(母なる大地)」
2006年からは、海外の農業者に呼び掛けて、持続社会を築くための循環型農業や伝統的な技術、種、品種などを受け継ぐ現場の生産者による国際会議「テ ッラ・マードレ(母なる大地)」も行われるようになりました。 つまり実践的な技術を生産者同志が話し合い、これを連携させよう、そこか ら食と農と環境を連携させた持続社会を築くという壮大な構想です。
スローフード協会は、もともとは、地域の地元ワインを愛好するグルメのジャーナリストを中心とする集まりでしたが、それでは地域の食を守ることはできない。そこで、地域経済につながる活動が始まったのです。ワインの品種、環境、土壌の調査、製造法、醸造の手法などを調査したり、ソムリエやバイヤーや専門家を呼んでの学習会、ツアーなどを開いたりするなかで、フランスからの樽詰や瓶詰など加工販売までの技術や手法が現地調査されてイタリアにもたらされます。地域のブドウ農家に具体的な技術や加工の手法、販売の手段を伝えたのです。それまでブドウ生産農家は生産だけに関わり、醸造と瓶詰と販売までは、別々でした。これらを一体化することで、農業者には、大きな価格の商品に変えることができるというわけです。これに販売する場を提供することによって、農業者は、これまで以上のお金を手にすることができるというわけです。
これはつまり、日本政府が農業政策として2010年に打ち出した「六次産業」と同じことです。六次産業とは、一次産業の農業、二次産業の工業、三次産業のサービスの、1.2.3を足すと6になることから名づけられた言葉。生産、加工、販売を 一体化することで、農業の付加価値を出すための政策です。スローフードは、6次産業を、もっと文化的な視点で、すでに、1980年 代から取り組んでいたというわけです。農家が生み出したワインが、スローフードの手によってもたらされた情報によって質の高いものとなり、ソムリエと出版社とが連携したガイドブックの作成、イベントでのプロモーション、バイヤーへの連携、さらに輸出までにつながり、地域農業に経済性と持続性を生みだしたのです。食をテーマに地域経済の基盤を築き、州政府と連携して世界的に人を呼び寄せるまでの祭典を運営するまでになりました。そこにイギリスのチャールズ皇太子(当時)を招くことができるスローフード協会の力に驚いたのでした。実はチャールズ皇太子も広大な牧場を運営していて、放牧によるアニマルウェルフェア(動物福祉)に基づいたところです。これもイギリス現地まで行き確認し、その取り組みに仰天させられました。
スローフードは大学も創設した
「スローフード食の大学」の構想を知ったのは2003年です。当時NPOスローフード協会の国際理事で日本担当であったジャコモ・モヨーリさんに、ブラ市と同協会のイベント「チーズ」の会場で、「今、スローフード協会で大学を建築中だが、見に行かないか?」と言われて一緒に出かけたのが最初。大学ができるというので、てっきり新しいビルでも建ったのかと思っていたのでした。ところが、その建造物を見て仰天しました。なんと、1830年代の貴族であるサボイ家カルロ・アルヴェルト2世が建てたネオゴシックの建築物。1993年から2000年にかけて放置されていたものです。それをリノベーションするというものだったのです。
イタリア共和国北西部のピエモンテ州ブラ市郊外、ポッレンツォ (Pollenzo) のスローフード食科学大学( The University of Gastronomic Sciences、略称: UNISG)です。
そこで、ジャコモさんから大学の構想を聞いたのですが、にわかには信じがたかったのでした。なにせ、地階には大きなワインセラーがあって、イタリア全土のビンテージワインが並び、そこから醸造学を学ぶとか、学生は各地の農業の現場から食材のなりたちを知るのだ、という話。それもNPOが城を大学にしてしまうというのですから、ほんとうだろうかと思ったのも無理もありません。だから、04年に開校した大学を訪れ、ふたたびジャコモさんに会いたいと願ったのでした。

スローフードの食科学大学


再訪、スローフード食の大学
再訪した大学は、ほんとうに古い建物がそのまま使われていました。当時と異なり、中庭は芝生で覆われ、人が行き交い、優雅で瀟洒な建物になっていました。地階にはイタリア全土のワインが並んでいます。しかも同じ構内にはレストランがあり、40室のホテルもあります。ホテルは天井が大きな梁のようなどっしりとした木材に覆われた重厚な造り。シンプルなデザインのインテリアもすばらしい。
建物は、もとはイタリア政府が管理していた文化財で、同協会の提案で、ピエモンテ州政府とエミリア・ロマーニャ州政府が賛同して大学として誕生。多くのワイナリーや篤志家による寄付もあったそうです。老朽化した建築物使えるようにするのにお金と時間がかかったというのですが、しかし、すばらしいプロジェクトです。
あとでブラ市の役場の人に話を聞いたら、大学ができたことで、世界から人が来るようになり、観 光客も増えて、市の認知度も格段に上がったそうです。ほかに、パルマ近郊のコロルノにも17世紀に建設された公爵宮殿を使った大学院があり、これら2つが補完しあう関係にあるのだということでした。
城の運営はポレンツォ・エージェント会社が行い、そこに、大学、ホテル、レストラン、ワインバンクが入っています。
地階に行くと、1,900㎡という広大なNPOワインバンクが管理するワインセラーがあります。これも同協会が新しい事業として投資して誕生したのだそうです。イタリア全土の有力なワイナリーのメンバーで構成されています。ここではワインを購入することもでき、また、プロモーションをする役割を担ってもいます。もちろん、大学の醸造学とも連携しているのです。
ジャコモさんは、「世界中から多くの人がやってきて食の国際会議も開く、だからクオリティーの高いものでないとね」と。それをみごと形なっているのでした。
続けて、「スローフードは、今日の農業問題に解答を与えるためにある文化的なプロジェクトなんだ。出版や農業や食などが複合的に関連している。農業に関する、今、生産者が直面している問題を解決し、持続可能性を導き出し、深めていく必要がある。それで大学をつくったんだ」。
彼は当時、大学の理事として2年生のスペシャルコースで地域デザインと新しいガストロノミー(食文化)の考え方について講義もされていました。
「大学をつくるという構想をたてた。テッラ・マードレ(母なる大地)で、農民がいたり、生産者がいたり、食べる人がいたりという、ばらばらの状態があるなかで、大学をつくることで、それらを一緒にして考えていこうと思ったんだ」とのことでした。
「学生は世界各国から、もちろん日本からも来ている。新しい食文化にふれて学ぶこともあるし、違う食文化を学んで違う文脈に置き換えて、自分の国に持ち帰ることもあるだろう。ここはイタリアの大学をめざしているのではなく、世界大学をめざしているんだ。先生も世界各国から来ている。
学生は、3か月にわたるヨーロッパ各地と世界の研修旅行を通じて、農業の現実を見ていくことが重要だ。ラボラトリー(実験室)のような大学なんだ。食と農に関するビジョンを創造するための実験的な大学ともいえるだろう」とジャコモさん。
大学の卒業生たちは、生産流通の現場の経営者やマネージャー、またジャーナリストなどとして活動をしています。多くの卒業生が誕生し、実際、食の現場で活動が始まっています。この壮大な活動を築きあげた、スローフードの理念には、ほんとうに驚かされました。
大学は、ブラ市、ロエロ地方、ランゲ地方の中間にあり、今では、国際的な文化交流の拠点となり、しかも大学を含む一帯がユネスコ世界遺産に登録されたのです。
建物は、3つの柱で構成されています。1つはツーリズムの役割を担うホテル、一つは地下にあるワインのプロモーションを行うワインバンク。一つは、学びとなった大学。
大学では、3年生の学部と、いくつかのマスターコース、修士のコースなどがあり、食文化を学びます。
これまでの卒業生は約4000名。世界各国から訪れています。毎年、すべてのコースを総合して約450名が受講。受講料は年間約200万円。そのなかに学食、年5回の実地研修が含まれます。研修は、実際の食の現場を訪ねて、生産や加工を学ぶというもので、海外も含まれています。国内研修は5日ほど。海外では10日から12日があてられています。
校内は、約4万冊の食の図書館があります。食堂では、地域の食材が使われ、世界中のシェフたちが料理を教えにきます。食堂の柱には、これまでに来た世界のシェフたちの写真が掲示されています。「まるで食の国連のようです。国の資金援助はないので、150社あまりの企業が資金援助をしています。出資額の大きい企業では、戦略パートナーで、かつ研修のパートナーでもあります。企業や銀行、財団で奨学金を出してくれるパートナーもあります」とは、案内をしてくださった大学担当のアレッサンドラ・アッボーナさん。大学ができたことで、経済効果も大きなものに繋がったといいます。大学ができたことで地域全体のプロモーションの一助となったのです。

大学の図書館で担当の方と岡崎啓子さん(右)
食文化発信の優れた女性・柴田香織さん
そしてスローフードから大きな出会いが生まれます。スローフード食科学大学大学院を卒業し、そのあとフードコーディネーターとなる柴田香織さん、それにスローフード食科学大学を卒業後、トリノに開業した「イータリー」でコーディネーターとなり、そのあと食文化の発信の活動をするようになった岡崎啓子さんのお二人です。


大学の食堂

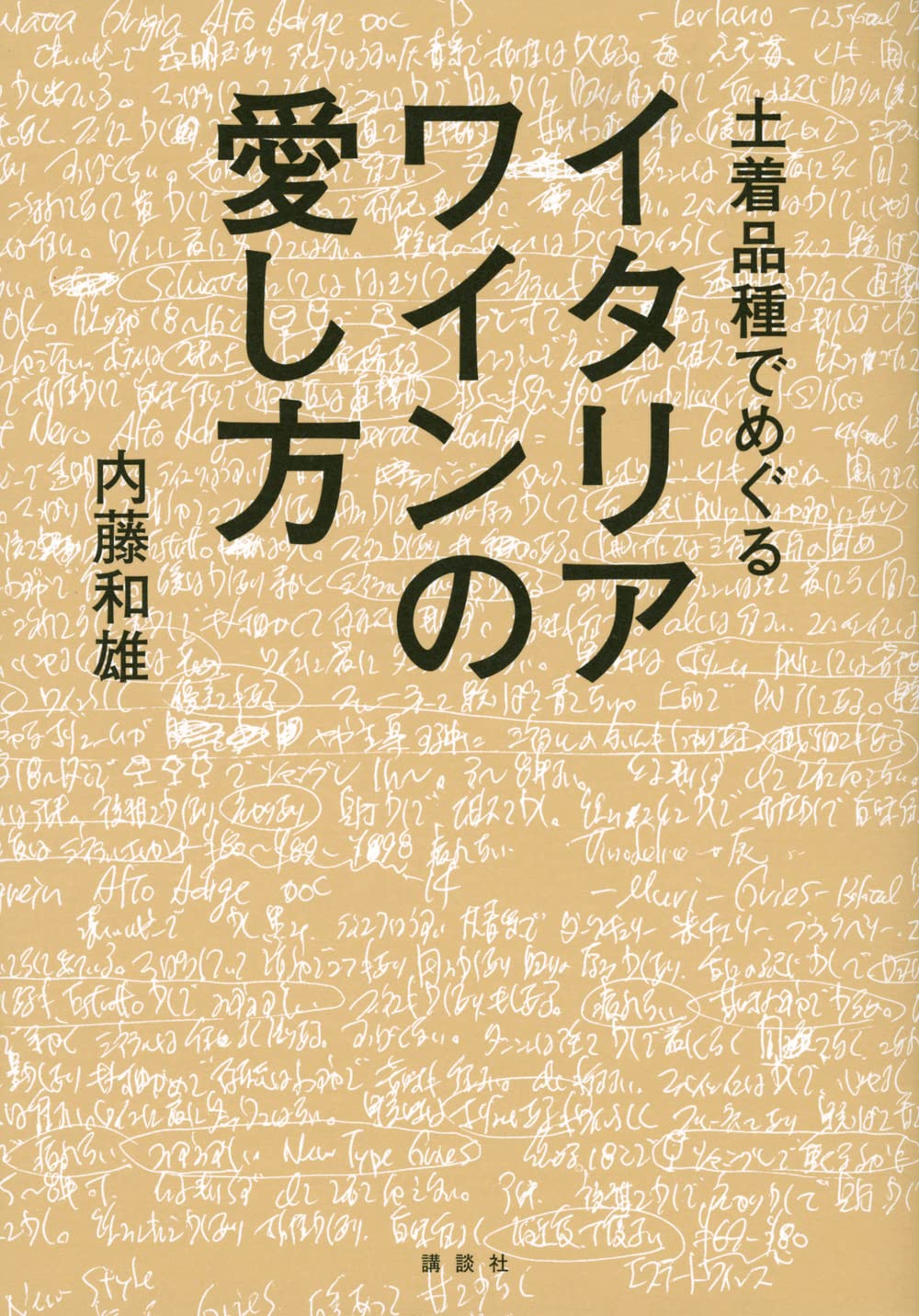
柴田香織さんの経歴は「大学卒業後、広告代理店に就職。2005年、イタリア・スローフード協会が設立した「食科学大学」に第一期生として入学し、大学院で1年間学ぶ。帰国後、フリーランスとして料理誌等での執筆、地方自治体の食の地域振興などに携わるほか、ワークショップの開催を通して“文化としての食”を伝える。2011年、(株)伊勢丹研究所に勤務。食品フロアのディレクションを担当。2014年4月〜フリーランスの活動を再開」とあります。各地でフードコーディネーターとしての活動はもちろん執筆活動もされています。
フリーランスになって間もないころ、イタリアのブラのスローフード・インターナショナル・オフィスを訪ね、そのときの記事が雑誌「料理王国」(2009年5月号)「スローフードの真実」として5ページにわたり掲載されています。
スローフードの活動がわかりやくす、写真も豊富に紹介されています。スローフードが食のプロモーションの事業体であり、彼らの多角的な運営事業内容と担当オフィスと各部署の担当者のコメントとが的確に案内されているものです。
柴田香織さんがプロデュースした優れた本があります。『土着品種でめぐるイタリアワインの愛し方』(内藤和雄著/講談社・2022年)です。
本を開くと見開きカラーで2ページに、イタリア各地の20州の78のその土地ならではのワインと地域の料理とが対になって紹介されています。本には、イタリアの全土のマップ、イタリアの葡萄畑や町々や山村の風景、料理の様子の写真なども挿入されています。
ワインと料理では、例えば、エミリア=ロマーナニャ州では、ランブルスコ・マエストリ(赤泡)とトリタフリットパルマ産生ハムとメロン。「エミリア地方は動物性油脂や乳製品を使うリッチな料理が多いので、軽やかに口を洗ってくれる赤の微発泡は、そもそも理に適っています」とあります。また著者が学生時代、アルバイト先の飲食店で勉強と称して重い赤ワインを飲まされ、それが馴染めずワイン嫌い寸前に出会ったワイン。その軽やかで心地よさに「ワイン人生に光が差した」ともあります。
アルバーナ(白)とはパッサテッリの料理が合う。残った固くなったパンをすりおろし、イタリアを代表するチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」と卵と一緒に練ってパスタを作り、肉や野菜のブロード(出汁)でゆでる。
ブーリア州では、プリミティーヴオ(赤)とチーメ・ディ・ラーバ(菜の花)のオレッキエッテ(耳の形をしたパスタ)の組み合わせ。プリミティーヴオは地元の人たちの食事のお供。常温で飲まれる。野菜料理や日本の食卓にもお勧め。などなど、どのページも垂涎の的なのです。
ワインと料理の相性が、ひとつひとつ語られます。なんとも贅沢。写真も見た目も美しい。どれも潤沢で美味しそう。そこからワインの香りや料理の味わいが漂ってくるようです。どれもが五感を多いに刺激され、現地を訪ね、触れ試したくなりするのです。
「イタリアにはイタリア料理はない」とは、よく言われる話。それは、土地土地の自治体(コムーネ)によって独自の郷土料理があり、それが大事にされているからです。この本では豊かな地域の食とワインが語られます。食の本でありながら、旅の本でもあり、著者のエッセイでもあり、イタリアの人々の食に対する愛と歴史と叡智の賜物でもありと、多彩な輝きを放っています。
嬉しいのは最初のページがピエモンテ州のドルチェット(赤)とカルネ・クルーダ(生肉のタルタル)から始まっていることでした。というのは、ピエモンテ州は、初めてイタリアに行った場所。スローフード・インターナショナルが主催する食の祭典「サローネ・デ・グスト」に出かけて「味覚のワークショップ」という素材の背景を知り、五感を駆使して、見た目、香り、味わい、触感など、実際に食べてみて、それを語彙豊かに表現し感性を呼び覚ますワークショップに目覚めたところ。まさに「美味礼賛」を教わったところです。それが本を見開いた途端、当時の情景や食のことがまざまざと蘇ってきたのでした。
本の著者となっている内藤和雄さんは故人。2019年9月22日に白血病で亡くなっています。柴田さんの前書きによるとイタリアをこよなく愛したレストラン「ヴィーノ・デッラ・パーチェ」のソムリエ。毎年2回イタリアにでかけていました。彼の蘊蓄を柴田さんが食の雑誌『料理通信』で聞き書きで連載していたのです。当初はイタリア20州の代表的なワインと食を巡る旅だったのが、さらに続き、78回で著者の逝去で連載は終わることとなります。内田さんは少なくとも400回は欲しいと語っていたのだそうです。内田さんの思いを伝えようと彼を慕った方々でプロジェクトが生まれ、クラウドファンディングで資金調達を行い出版社を探してとの経過があって生まれた書籍。それらの思いが存分に生きています。
本を開けた途端、すっかり魅せられてしまいました。日本酒、あるいは日本のワインと国内全土の郷土料理の本ができたら、どんなに素敵だろうとまで妄想してしまったのでした。
「味覚のワークショップ」の実践を学ぶ
本をまとめた柴田香織さんとはイタリアで知り合い、東京都八王子の牧場でのワークショップで、イタリアの「味覚の講座」を実地で教えていただいたりしました。「味覚のワークショップ」では、目、鼻、唇、手の絵があって、その横に空欄があり、テーマの食材、例えば、チーズがあるとすると、実際に見た目、香り、味わい、食感や手触りなど、音などを、書き込みます。そのシートをイタリアのものを参考に作ってくださいました。すると観察力が養われるとともに、表現も豊かになり、食材の特徴を学ぶことにもなります。
その当時、私が講義をしていたフェリス女学院大学「地域と食文化」、明治大学農学部「食文化と農業ビジネス」の授業では、八王子にある牧場「磯沼ミルクファーム」を年に一度開放してもらい、希望する学生が参加し、ピザやデザートまで創る、フルコースの牧場の料理会を開いていていました。というのは、大学での講義だけでなく、実際の現場で体験してもらいたいと考えたからです。
牧場では、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジー、エアシャー、ホルスタインなどが飼われています。これだけの種類の牛を飼っているところは、ほとんどないでしょう。フランスでは40種類以上の牛がいて、それと飼育される環境の違いなどもあり、チーズの種類が牛の品種によるミルクの違い、見た目、味わい、香り、食感などについて学習する「味覚ワークショップ」を開いています。また牛の飼育の環境やエサがどこからくるのかなども学びます。「味覚ワークショップ」をカリキュラム化し実施しているフランスの味覚の授業、イタリアのスローフードのワークショップも学びに行きました。

牧場の料理会・東京八王子「磯沼ミルクファーム」


味覚の授業は、五感を使い、食べ物を表現することで、個性を育み、語彙を豊かにしていくものです。また、料理会をするにあたっては、食材の成り立ちや文化的な背景がわからないと、きちんと学生にも、参加者にも伝えることができません。そこで食材のテキストを作成し、料理まで展開をするという食のワークショップを各地で開くようになったというわけです。
料理家・馬場香織さんと出会う
柴田香織さんがプロデユースをした恵比寿の「バンタンデザイン研究所」で行われた「フードマエストロ」講座の講師に呼んでいただき、そこで柴田さんが引き合わせてくださったのが料理家・馬場香織さん。
柴田香織さんにさそわれて行ったのが馬場香織さんの料理の本『何度でも作りたくなる ほめられレシピ(レタスクラブMOOK)』(KADOKAWA)の出版記念ホームパーティー。そのお祝いをしようとなったのです。そして馬場香織さんが、手料理でもてなすという趣向。これが見事な料理。しかも主婦の視点で作成されていて見栄えがする。どれもおいしい。
彼女の本に登場するメニューでのおもてなし。「ブロッコリーと海老炒め」「蒸しなす香味だれ」「鶏肉のシュプレーム」「スモークサーモン寿司」「翡翠チンゲンサイ」「鶏肉の紅茶煮」「豆サラダ」などなどがテーブルいっぱいに並んだのです。
「ドライカレー」と「海老と貝柱のホイル焼き」は、実演付での料理のプロセスを披露するという、彼女が自宅でクッキングスクールをしていることから生まれたアイディア。これがなんとも簡単そうで、できあがりを食べてみても美味しい。
披露されたドライカレーは、ひき肉を、バターとニンニクでいためる。それに塩とカレー粉を入れるだけ。あとは、バターライスを添える。ポテトチップス、ゆで卵、ラッキョウ、福神漬け、ピクルスなどを、トッピング用に用意するというもの。
料理はどれも美しく調和も素敵です。本は、発売をして一週間で3刷となったといいます。売れたのは、手ごろな価格に加えて、料理がわかりやすく、だれでもができるという主婦の知恵が生きている。それも、今までの料理とは違ったオリジナルで、新鮮さがあるのでした。
馬場さんは、夫の仕事でシカゴ、ニューヨークで10年の海外生活の経験者。海外での生活で関係者を招き親睦を深めるためにホームパーティーを開いていたのだといます。それがすべて手料理のおもてなし。それが「彼女は料理の天才だ」と噂になり、料理学校の講師にと誘いがかかります。弁護士に相談したところ、労働ビザがないのでお金はいただけない。しかし無料で教えるかわりに、ほかの講座を受けさせてもらうという条件で講師を受けたのだといいます。こうしてアメリカで、さまざまな料理の資格を取得。それを生かした料理教室を開き、出版社の目にとまり本を出すことに。その最初の機会に呼ばれたわけです。
馬場香織さんと、地方で食のワークショップをやりたいと、思ったのでした。馬場さんも「地方に行ってみたい」とおっしゃり、そこから、各地で食のワークショップを実現するということとなります。
なぜ、馬場さんをお願いしたかというと、農家のお母さんたちと料理を一緒にしてもらいたい思ったからだでした。というのは地方で食のブランドをするという事業で、よく有名なフレンチ、イタリアンを始め、料理店の料理家、パティシエなどを呼んで実施される場面に出会いました。しかし、役場の担当も素人。集まるのは地元の農家の人たちというケースが多く。料理家を呼んでも、料理店を経営するのではないわけで、ほとんどがイベントで終わるというケースが多々あったからです。これが、小都市のホテルの料理家のセミナーなどであれば、いいのですが、そういうケースはほとんどありません。しかも、地域の食材は地方によって異なります。まず地域の食の調査があって、それに合った料理で、参加した人たちが応用できるものないとなりません。それを馬場香織さんなら、やっていただけると確信したからでした。こうして、まず、私が現地へ行き、地域の食材の調査をしていただき、そこから参加メンバーと調理場を確保してもらい、馬場香織さんの、地域の情報と食材を伝え、それでレシピを考えてもらい、現場には、早めに入ってもらい、農家や漁師さん、学校給食関係者、地元の小売店、農産物直売所の方々や、地域の方たちに料理指導をしながら、1日目は仕込み、2日目は料理作りと披露という形の参加型ワークショップを各地で開くようになりました。
東京都八王子の牧場の料理会でも、馬場香織さんには、学生たちに、料理を手取り足取り教えていただき、これが大好評だったのでした。なにせ、包丁をもったことがない、野菜の切り方がわからない、という学生もいて、馬場さんは、それも丁寧に指導してくださったのでした。さらに味付けの仕方、料理の塩梅、盛り付けの仕方まで、指導してくださったのですから、喜ばれたのでした。馬場さんは、嫌な顔ひとつとせず「若い子たちと一緒の料理ができて楽しい」と笑顔で応えてくださったのでした。
馬場香織さんに引き合わせていただいた柴田香織さんには、スローフードの食のプロモーション展開と味覚の授業を実地でも教えていただきました。まさに人生を変えた恩人ともいえる方です。
アサヒビールとキリンビールのトップの教え
そして後で知ることとなるのですが、馬場香織さんのお父さんは、中條高德(なかじょう たかのり/1927年 - 2014)さん。アサヒビール株式会社の副社長を経て名誉顧問だった方。アサヒスーパードライの躍進に貢献され、著作も多くあります。馬場香織さんは、お父さんのマネジメントも一時されたことがあるそう。有名な方なので、全国から、「うちからもビールを出してほしい」という要望がたくさんきたそうです。そのとき、「やめなさい。99%失敗する。まずは、足元から、ひとつずつ手掛けなさい」と言われたのだそう。よく、大手のヒット作品にあやかろうというものが多くあります。
アサヒビールのヒットも一朝一夕でできたものではありません。試行錯誤あり、営業、販売網、宣伝などの体制ができ、初めてヒットとなったものです。まずは、モノづくりを足元からというのが納得でした。馬場香織さんからは、お父さんの本『おじいちゃん日本のことを教えて ――孫娘からの質問状』(中條高徳著/致知出版社) もいただきました。
そんなこともあり、馬場香織さんの、食材を吟味して、料理を作ってみるというワークショップは、理にかなっていると思ったのでした。
そして、その後、さらに驚くことに出会います。キリンビールの社長、そのあと会長となられた荒蒔康一郎(あらまき こういちろう)さん(1939年~ )との出会いです。後述しますが、食のワークショップを各地で手掛け、その実績ができてメデァイでも発信していたことから総務省に呼ばれて、茨城県常陸太田市の食のブランド事業に携わり、その成果が認められて、当時の市長の在籍中に常陸太田市大使を拝命します。実は、荒蒔さんは常陸太田市出身。荒蒔さんも常陸太田市大使でした。
荒蒔さんとは、実は、銀座の食のシンポジウムでお会いしておりました。その懇親会が行われ、司会の方が、「それでは、乾杯をします。みなさんビールでいいですか」と言われました。それで、私は「わたしは焼酎がいいです」と言ったら、ものすごい顔でにらまれました。そのあと司会の方が「それではキリンビールでいいですか」と言われたのです。会場の皆さんはビール片手に「はーい!」と大きな声。そして「キリンビール会長の荒蒔康一郎さんに、乾杯の挨拶をいただきます」と、そのとき、立たれたのが、なんと私の隣の席の方。お隣が荒蒔さんだったのです。
「ビールで乾杯」といわれて異議を唱えた私が睨まれたのも無理ありません。冷や汗ものでした。
そして、後日、常陸太田市の大使を招いての懇親会が現地であり、そのときに伺いました。そうすると荒蒔さんがいらしたのです。
「以前、銀座でお会いしています。覚えていらっしゃいますか」と言うと「もちろん。あなたの息子さん、和歌山県田辺市に移住したでしょう。一度、うかがわないと思っています」と。
「えっ、なんでご存じなんですか」と驚くと、「あんたの息子さんの嫁さん、りさんは、うちの娘の友達なんだよ」と言われてびっくりしたのです。どんなご縁があるかわかりません。
そのあと、常陸太田市にできた道の駅に招かれてお披露目会がありました。
そのとき、荒蒔さんが、「市長が、前々から知り合いで、キリンビールの企業誘致をしてほしいと、何度も言われた。だけどやめなさいと。大手企業は、経営がよくないと、すぐ撤退してしまう。それよりも、まずは、足元からコツコツと一からやりなさいと、何度も話した。やっと最近わかってくれたみたいだ」と話されたのです。
なんと、アサヒビールとキリンビールのトップの方が、まったく同じことを諭されているというのに、モノづくりの大切さを示唆されたのでした。
道の駅お披露目では、市長の挨拶のあと、責任者という女性の方が挨拶。
「オープンしましたが、問題は山積みです」と言われたのです。
すぐに私は手を挙げて「道の駅に「炭小屋」を造ってください。「山炭=山積」が売れます」と大きい声で言ったら、みなさんドン引き。
そのとき、荒蒔さんが、すかさず手を挙げて「金丸さんに座布団1枚あげてください」とおっしゃったのです。ユーモアもある方です。
そのあと、お手紙を出すと、いつも丁寧に手書きのハガキが届くのでした。成功の陰には、細やかな気遣いがあると知ったのでした。
食のプロモーションを岡崎啓子さんに学ぶ
スローフードの祭典でお会いした方で、その後、たくさんのサポートを受けた方がいます。岡崎啓子さんです。岡崎さんは夫がワイン醸造家。イタリア北東部エミリア= ロマーナニャ州にワイン醸造家の夫とお子さん2人と暮らしています。
岡崎啓子さんは埼玉県鴻巣市の兼業農家生まれ。2000年東京女子大学現代文科学部(現・現代教養学部)コミュニケーション学科卒業。イベント制作会社に就職。スローフード協会が「食」の新しい学びを提供する大学を新設することを知り2004年渡伊。2008年イタリア食科学大学学部第一期生として卒業。2008〜2014年高品質なイタリアの食品の販売・レストラン・教育事業を行うイータリー社・トリノ市で、日本を主とする海外展開事業に関わります。生産者とのリレーション、仕入れ、輸出入を日伊両サイドからサポートしたほか、メディア対応やイベント企画など幅広く経験されています。

「イータリー」トリノの店

「イータリー」が、最初に海外に出店したのが代官山(2008年~2014年)でした。そのときイータリーに岡崎さんも日本にお見えでした。この頃、長男・金丸知弘が、通信高校に通いながら今後のことを模索しているときでした。アルバイトをしていて、うどんのチェーン店でした。それで「働いているところの食材の袋を持ってきてみて」と頼んで、彼が並べた食材の袋は、すべて中国産。「ほかのアルバイトしている人はどうなの」と訊いたら「やる気ない」との話。「どうせ働くなら、本物の食材を扱うところに行ったら」と、それで「イータリーに行ってみたら」と誘ったのです。
最初は、当時、世田谷に住んでいたので「遠い」と敬遠していたのですが、「とりあえず一度訪ねたら」と話し、岡崎さんからは「日本人で働いている人もいるから会ってみたらどうですか」ということで、そこから知弘は「イータリー」で働くこととなったのです。そしてしばらくして「どんどん人が辞める」と言います。これは間違ったかと不安に思ったのでした。よくよく尋ねると、実は、最初は皿洗い。熱心にしていたら、今度は、お客さんの接客と注文を受ける。イタリア人も多く来るから、対応が面倒と思うと、そこで、アルバイトもやめる人がいる。ところが、そこでも熱心にしていたら、今度は、「サラダを作ってみなよ」と言われる。一所懸命にすると「パスタを作ってみなよ」と言われる。さらに「今度、チーズを教えてあげる」と、次々に仕事を学ばさせてくれる。そして「三越本店においでよ」と誘われて、イタリアの食の基本を学ばせてくれたのです。
「それって面白いじゃない」と言ったら「そうなんだよ。面白いんだよ」。
それで、「どうせならイタリアまで行ったら」ということで、イタリアの専門学校ICEFへと留学することとなりました。そしてイタリアへ行く前に、「日本を一周してから行きたい」と言います。理由を尋ねたら「イータリーに来るイタリア人から、日本の北海道の素晴らしさを知っているか、富士山の優雅さを見たかとか、言われる。イタリアに行ったとき、日本のことを話せないのは嫌だから。それとお父さんが行ったところも見てみたい」ということでした。それで彼は、自転車で日本を一周してイタリアへと向かいます。
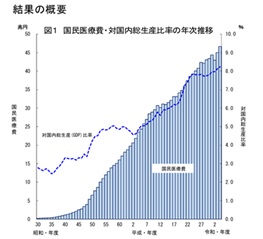
令和4(2022)年度 国民医療費の概況(厚生労働省)
総務省地域力創造アドバイザー事業
岡崎さんとは、新たな連携をしていただきました。実は、スローフードで学んだ食の背景の調査、味覚のワークショップを実践に移し、幼稚園、小学校、大学など、農家など、さまざまな現場での活動を始めていました。それらを文章に書きいくつかの本も出しました。
2005年(平成17年)食育基本法が制定されます。背景は、生活習慣病が広がり、医療費が戦後最大になったこと。健康被害が子供たちにも広がっていること。食料自給率が低いこと。日本の地域の食文化が失われかけていることなどが要因にあります。食べることが法制化されることとなりました。どの自治体も食育基本計画に沿って食育を推進することとなったのです。

それまで給食の各地の取り組みを取材したり、ワークショップをしていたりしたこともあり、大分県から食育のアドバイザーに来てほしいと声がかかります。また佐賀県からは、唐津市が市町村合併したことから、食をテーマに、地域振興の依頼もありました。
そんなときに、岩波書店の編集者の賀来みすずさんから「食育の本を書きませんか」と勧められます。各地の実施活動をまとめることができ『創造的な食育ワークショップ』(2007年)という本になります。
その本を、当時、総務省にいらした末宗徹郎さん(のちに一般財団法人地域総合整備財団=ふるさと財団理事長)が読んで、声をかけていただき、引き合わせていただいたのが都市計画家・西郷真理子さん。明治大学農学部教授の小田切徳美さん。西郷さんからは香川県高松市の商店街の食のプロジェクトをご一緒させていただくこととなり、小田切先生には、明治大学農学部の非常勤講師、そのあと兼任講師をさせていただくこととなります。また、総務省では、当時の総務大臣・増田寛也氏に引き合わせていただきました。そのときの担当が、参事官の椎川忍さん(のちに一般財団法人地域活性化センター理事長)でした。
総務省地域力創造アドバイザー事業は、11名が呼ばれました。これは、その後2014年に始まる「地方創生法」の、外部人材の派遣事業「総務省地域力創造アドバイザー」の前段にあたるものでした。そのとき筆者にオファーがあり、コーディネーターとして携わることとなるのが茨城県常陸太田市の食の地域づくり「常陸秋そば」でした。
総務省では、地域づくりをするために、先進市町村で活躍している職員や民間専門家を招聘し活用することができる制度を運営することとなります。これは、地方で人口が激減するなかで、新たな活力を生み出すためには、外部人材との連携が必要ということから生まれたものです。同省のホームページには「地域人材ネット(地域力創造アドバイザー)」という項目があり、「市町村が、地域力創造のための外部専門家(地域人材ネット)」登録者、通称「地域力創造アドバイザー」)を招聘して、地域独自の魅力や価値を向上させる取り組みに要する費用を特別交付税措置の算定対象としています」とあります。
経歴の説明とあわせて登録されているのは、職員・専門家約600名です。
自治体が欲しいと思う専門家がいれば、申請すれば来てもらえる仕組みです。年度内に延べ10日以上または5回以上。最長3年間にわたり制度が使えます。予算は地方交付税で補填されます。

宿儺かぼちゃのブランド事業
同時期に農林水産省・岐阜県高山市「宿儺(すくな)かぼちゃ」のブランド事業を手掛けることとなります。
この「常陸秋そば」と、「宿儺かぼちゃ」のプロモーション事業を、サポートしてくださったのが「イータリー」に当時いらした岡崎啓子さんだったのです。
蕎麦もカボチャもイタリアでも古くから栽培されていて、同じ伝統的な作物もまったくことなる食べ方あることを教えていただきました。
「このかぼちゃはイタリアのものと同じ。一度、イタリアの市場に行ってみてください」と岡崎さんに言われて現地を訪ねました。すると本当に、長く大きなかぼちゃが売られています。また、蕎麦は、ロンバルデァイ州で1600年代から栽培されていることも知りました。
プロモーションでは、レストランを貸し切りにして、「イータリー」のトップシェフに参加していただき、蕎麦はロンバルディア州山間部ヴァルテッリーナ地区の伝統パスタ「ピッツォッケリ」に。そして常陸太田市の伝統的な蕎麦料理で大根、ニンジン、こんにゃく、ねぎ、ニンジンなどを入れた温かい汁に入れた「つけけんちん」。料理は常陸太田市の農家の海老名ひや子さん(当時80歳)。伝統のコラボレーションです。
発信力のある方々に呼び掛け「麺が結ぶ二つの文化」というタイトルで案内しました。
「宿儺かぼちゃ」ではリゾットやスープなどフルコースで参加者に提供していただくこともおこなっていただきました。

常陸秋そばのテキストの一部。全体で16ページがある。ソバ ( 蕎 麦 ) の 話 https://www.kanamaru-jp.com/data/workshop/pdf/workshop2009040401.pdf
このとき、食材の文化背景から歴史、品種の特徴など詳細なテキストを、役場の方にアドバイスし作成していただきました。これはスローフードで行われていることを、応用したものです。このテキストを、当時の「イータリー」の代表のイタリア人の方に、お渡ししたら「君たちは、素晴らしい文化をもっている。ぜひ一緒にやろう」と、言ってくださったのでした。
さらに常陸太田市、高山市では、農家や料理家など出迎え、伝統的建造物を使った場にツアーを組み込むことも行いました。つまり、今、よくいわれるガストロノミー(食文化を通じての交流)を形にしていたわけです。これらの活動は、さまざまなメディアに登場することとなります。テキストを作成していたので、メディアには正確な記事が掲載されました。

高山市から届く「花もち」
「宿儺かぼちゃ」では、柴田香織さんに紹介いただいた料理家の馬場香織さんに料理を手がけていただき、小田急線・経堂駅近くにあった生協のキッチンスタジオで、料理が披露されました。パイ、サラダ、キッシュ、和え物など10品目以上が登場。
馬場さんが調理デモンストレーションで披露したのは、「パンプキンミートロース」。ローフにベーコンを張り付け、そこに、牛肉、玉ねぎ、ニンニク、卵、かぼちゃを詰め込んで焼く。それにマッシュドパンプキンを塗り、さらに焼く。そこにスライスしたかぼちゃを並べるというもの。かぼちゃの色合いが美しい。それに美味しい。
これを観た高山市の「宿儺かぼちゃ研究会」の代表で農家の若林定夫さんが「この料理を地元のかあちゃんたちと一緒に作りたい」と言われました。「けど予算がない」とも。
「入場料をとればいいじゃないですか」と私。
「なるほど」と若林さん。
高山市とJAとの協力で、キッチンを借り切り、入場料を集め、馬場香織さんを呼び、地元のお母さんたちが参加し料理を披露する公開ワークショップを形にしてくださったのでした。せいろ蒸し、そぼろ餡あん、グラタン、シフォンケーキ、コロッケなど、カボチャ料理が30品目以上登場しました。試食会には、地元の新聞や雑誌、議員さん、飲食店、関係者など100名近くを集めてくださり大盛況。
翌日、若林さんが高山市の町を案内してくださいました。するとあちこちから若林さんに声がかかります。
「新聞でみたよ」。料理会の噂は一気に市内に広がったのでした。

それから、今も、岐阜県高山市丹生川(にゅうかわ)の山間地から、毎年、届くのがお正月に飾る「飛騨の花もち」。農家が山に入り枝ぶりのいい切り株を探しだし、枝に搗きたての餅で花のように飾り付けた「花餅」。紅白の餅が春の桃のようで可愛らしい。飛騨地方の冬は雪が多く正月に飾る花もないことから、部屋を明るく飾り、子供たちを喜ばせ、豊穣を祈って、座敷天井下の横柱に取り付けるのだそう。
贈ってくださるのは農家の若林定夫さん。必ずお手紙がついています。それには「全国津々浦々花もちが飾られた日本を夢見て40年」とある。若林さんが32歳のときから始まったといいます。「飛騨のはなもち組合」を作り仲間の中野さんの二人で作り続けてきました。11月末になると餅をついてくれる人に声を掛け近所の多くの女性たちが集まり「花もち」づくりが行われます。
若林さんは「花もち」用にもち米も栽培しています。
地元で2000個近くの数の「花もち」が売られ、県外にも名古屋、大阪、東京など花市場を経由し300個くらいはでているといいます。
古民家でもてなしのツアーを行う
若林さんと知り合ったのは2008年。大きなヘチマのような形をした「宿儺(すくな)かぼちゃ」を東京に売り出したいと高山市市役所の方と二人でお見えになった。そこから3年間、ご一緒させていただいたのですが、若林さんの地域の方々の信頼の厚さ、行動力の素晴らしさ、実現力の力に目を見張ったのでした。
「宿儺かぼちゃ」のワークショップを行った翌年。今度は、高山市内のホテルや料理店でのカボチャ料理の集いと披露が行われたのでした。
ホテルでは農家と関係者の集まりでした。参加者に銘々膳が置かれています。景品も並んでいます。若林さんがおもむろに広間の中央で、背広の上着を脱いで、それを畳の上で引っ張り始めました。
「これ、なんに見える」と若林さん。
「地引網」と、私。
すると若林さん「服を引いとるやろ。これから福引や」。
次に干し柿が配られ「なかを開けてみて」。
干し柿を割ってみると、種がないもの、1つだけ、2つあるものなど、いろいろある。なにもないのは「はずれ」。入っているものに、それぞれ景品があります。
さらに翌年。「高山市は景観が素晴らしい。東京に売り出すよりツアーを組んで外の人に高山の暮らしと文化を紹介したほうが訴求力が高い」と提案したら、農家のみなさんに声をかけて実現してくださったのです。古民家を改修した宿を貸し切り、銘々膳でカボチャ料理を出す。神社の祭りや、出荷場まで巡るツアー。その翌年は築150年の古民家で農家さん総出でのもてなし料理。それぞれ全国から20名近くが参加しました。その古民家での入口でのもてなしが、また最上のものでした。農家の代表の方が、裃で大きな一升枡と半升枡を並べて「益々、繁昌!(升升、半升)」との口上での出迎えなのです。
そのとき参加の皆さんに阿弥陀籤。当たりには生産者の名前がある。引いた人は、宅急便の伝票が渡され、それぞれの籤の当たりの農家から季節の米や野菜などが届くという趣向。
その素敵な演出に感心し「若林さん、若い頃、そうとう遊びましたね」と言うと「そんなことない。真面目にやっとったわ」。が、こんな洒落っ気のある若林さんは、いい遊びをした人に違いありません。
「花もち」が送られてくる度に、高山市の素敵な情景と「宿儺かぼちゃ」一つで、さまざまな高山のあるものと人の良さを結びつけくださったがことが細やかにくっきりと浮かびあがるのです。そして若林さんが声をかけた「宿儺かぼちゃの会」は、20周年を迎え、そのときに招待され、「宿儺かぼちゃ」の知名度を上げたということで、なんと感謝状をいただきました。
国際メンバーとの食文化交流へ
さて、岡崎啓子さんは、「イータリー」勤務のあと結婚。その後出産。「イータリー」を退職されたあと食と文化と持続社会を作るプロジェクト・ JINOWA consortium メンバーになります。この会社は、岡崎さんと同じくスローフード食科学大学の卒業生・齋藤由佳子さん(ピエモンテ州アルバ在住)が起業したもので、多くの方たちが参加する体験の場のコーディネートや国際交流を行っています。交流を通してノウハウの連携を行い持続社会に繋がる形で地域に還元していく活動です。
これまで、2015年ミラノ国際万博と三重県の食文化発信、山形県鶴岡市ユネスコ食文化創造都市国際交流などをはじめ、数多くの食文化の交流事業を手掛けられています。
「イタリアから世界へ。持続社会を食・土・伝統文化を繋ぐプロジェクトGEN主催・齋藤由佳子さん」
https://wan.or.jp/article/show/10599#gsc.tab=0(パート1)
https://wan.or.jp/article/show/10603#gsc.tab=0(パート2)
会社は斎藤さんと岡崎さんほか3名を中心に毎回、シェフ、醸造家、学識者、建築家など、プロフェッショナルとのプロジェクトを組んでいます。
今まで30カ国の人々とコラボレーションしています。それだけに現場の食や環境や各地の取り組みの様子をよくご存知。
2023年2月、イタリア、フィンランドの国際メンバーと、鹿児島、埼玉、群馬、東京、静岡など酢、焼酎、納豆、味噌、酒造、鰹節など、発酵文化をメインとしたサスティナブルな取り組みの交流を実現させました。この日本ツアーが契機で、岡崎さんと再会することとなったのです。
再会のきっかけは1通のメールからでした。ツアーメンバーを埼玉県秩父市・秩父蒸溜所(イチローズモルト)に繋いでもらえないかという内容でした。
イチローズモルトのアンバサダー吉川由美さんのことを書いた私のWEB連載を岡崎さんが読んでくださっていたのでした。記事は上野千鶴子さん(社会学者・東大名誉教授)が理事長である「WAN ウイメンズアクションネットワーク」での連載「金丸弘美のニッポンはおいしい!」からのもの。この連載は、上野さんの強い勧めで「農村女性の起業家のことを連載しませんか」ということから始まったものです。
イチローズモルトは株式会社ベンチャーウイスキー肥土伊知郎(あくと・いちろう)さんが埼玉県秩父市に秩父蒸留所を構え製造しているウイスキー。数々の賞を受賞しており世界的にも知られているところです。このウイスキーのことを知ったのは、一般財団法人地域活性化センターの現地ゼミからでした。醸造所の現場で、案内をしていたのが吉川由美さん。実に細やかな解説で、すっかり魅せられたのでした。実は吉川さん、帝国ホテルの元バーテンダー。そのあと、ニューヨークを経て、イギリス・スコットランドへ行き、現地のバー、ワイン醸造所で学び、自らイチローズモルトに売り込みアンバサダーとして世界へ日本のウイスキーを紹介する方だったのです。

国産ウイスキーの素晴らしさを一人でも多くの人に知ってほしい」(ブランドアンバサダー・吉川由美さん)https://wan.or.jp/article/show/8147

イチローズモルトの現場は、一般の方は入れません。ところが吉川由美さんに連絡をしたら、海外からのツアーを快諾してくださったのでした。こうして海外の方たちのメンバーとの日本での交流に繋がることとなったのです。
ツアーでメイン会場のひとつとなったのが、埼玉県入間郡三芳町上富にある産業廃棄物処理会社でリサイクルを手掛ける「石坂産業」(石坂典子代表取締役)。実は「石坂産業」には、社内勉強会の講師で呼ばれたところで、その環境を配慮した活動は大きな注目となっているところです。里山を保全させて農業や食の体験と食と循環型環境の学びができる場にと再生させた東京ドーム4個分の「三富今昔村(さんとみこんじゃくむら)」があり、そこで地元の食材を使った料理の提供や環境学習に使われています。
そのあと、岡崎啓子さんが一時帰国。話をしたのは、農村での宿泊アグリツーリズムのことでした。
アグリツーリズムと農村観光振興へ
イタリアのスローフードの祭典「サローネ・デル・グスト」に行ったとき泊まったのが、農家での宿泊アグリツーリズムでした。農家の家屋の一部が宿泊施設になっています。これが実に快適です。個室になっていて、ベッド・シャワー・机・小さいリビングまであります。知り合いに、「へたなホテルより、農家に泊まったほうが快適」と言われて、それを試したら本当でした。それでとても興味を持ちました。
というのは、日本でも、農村の活性化で農家民泊が推進されていたからです。これまで観光地ではなかったところであった農村に、自然や農村の風景に溶け込み、その土地ならではの食をいただき、農業体験による学びと交流、そして農家に泊まり、触れあい、文化を楽しむという取組です。
これは、「グリーンツーリズム」という名称で1992年度(平成4年度)から進められてきました。名称の由来はEU諸国では、普遍化している農村観光からとられています。2005年(平成17年)「農山漁村余暇法」(農村休暇法)が制定されて、法整備も整い、農家の宿泊や料理の提供や体験などの取り組みが、農家のみならず、漁村や離島などにも大きく広がることとなります。背景は農家の人口や若者の激減、遊休地の増加、空き家増などがあります。これらを、観光・体験・宿泊などを連携させて、新たな農村観光として経済に繋ぐという政策です。
最初は、農村に修学旅行の誘致から始まったところが少なくありません。
まだグリーンツーリズムという名前が、出たばかりの頃、農林水産省の外郭団体、(財)都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう)に伺い、グリーンツーリズムの勉強会へも行きました。当時は、あまり情報もなく、よく意味がわかりません。実際に国内のモデル地区と言われる長野県飯田市、大分県安心院、山形県飯豊町などを始め、各地にも出かけ泊まりました。どこもが農家の民家に泊まるものでした。多くが、普通の家の一部屋に泊まる。風呂もトイレも家族と同じというところばかりでした。正直、泊まるのには、気軽とは行きにくいというところがほとんどでした。
EUがモデルだというので、イギリス、ドイツ、フランス、ギリシャなどにも行きました。そしてイタリア。ドイツ、フランス、イタリアは、自ら知り合いにお願いしてオリジナルのツアーを組んだのです。そこで初めて、行ったところは、農家民泊といっても、すべて個室になっており、地元の食が提供され、快適な居住空間が用意されており、周辺の景観や風景、体験なども楽しめるようになっていることでした。
日本の農家に泊まる民泊とは、まったく異なるものでした。すっかり魅せられて、何度もイタリアへ行きました。そこでEUでは、フランスには地方の民泊、Chambre d'hote(シャンブル・ドート)や、1棟貸しのGITES(ジット)などがあり、それらのノウハウがEUで、共有化されていることを知ります。しかも詳細なサイトがあり、どこも、その地方らしい建物、部屋、料理、風景、ホスピタリティ(体験)が一目でわかるようになっており、気軽に利用できるようになっているのです。フランスが、インバウンドで、世界トップというのは、実はパリに行っているのではなく農村に行っていると知ります。なぜなら、パリから1時間も行けば、優雅な農村風景と、個室タイプの農村の快適な宿泊があり、そこならではのワイン、チーズ、料理が味わえるという趣向だからです。
イタリアのアグリツーリズムも、快適なところばかり。その運営のために学ぶ授業があったり、手厚い支援制度があったりすることを知りました。
それで、イタリアに住む岡崎啓子さんに尋ねたら、「私の家の周辺で、車で20分から30分のところにアグリツーリズムは20軒くらいあります。サイトで簡単に見られます。子供のいるお母さんたちと、『今度の週末、どこへ行くと相談して、よく使います』とのこと、日常化しているとのことでびっくり。それもそのはずです。
なんと、イタリア全土で2万5000軒以上もあり、それがサイトで、外観、部屋、料理、周辺の環境、乗馬、ツーリング、ワイナリーなど、どんな体験ができるかまで、写真で観ることができ、そこから行ってみたいところにアクセスできるのです。
しかも多言語対応。農家で宿泊施設は12部屋まで持つことができます。レストランを持っているところもあります。プールやBBQがあったり、子供たちのための遊具や小さい公園を持っているところもあります。料理も、そこならではのものが提供されます。イタリアは公共の列車に、自転車ごと乗れます。それでツーリングしながらアグリツーリズムを利用することができるようにもなっているのです。
詳しく知りたいと岡崎さんに言うと「もちろん」と快諾してくださいました。現地からの詳細なレポートを送っていただいただけでなく、一時帰国されたときに、私の提案で、農林水産省の外郭団体(一財)都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう)や総務省と全自治体の地方創生を手掛ける(一財)地域活性化センターでのセミナー講師などもしていただきました。なにせ、現地にいらして、普段に家族でアグリツーリズムを利用し、子育てもされているので、その視点が、私たちの旅行者とは、まったく異なります。写真も豊富に用意されていて、学びの多いものでした。

列車内に手軽に自転車ごと乗り込める(トリノにて)

観光と都市との交流に大きく繋がるアグリツーリズム、イタリアへ農村観光と食の連携を学ぶ
岡崎さんが紹介されたアグリツーリズムの現地を訪ねようと2024年10月6日から16日までイタリアへでかけることとしました。岡崎さん家族が住んでいる北東部のエミリア=ロマーニャ州と、そのお隣で、岡崎さんが卒業したスローフード食科学大学がある北西部ピエモンテ州を訪ねることとなります。
目的は明確にあって、アグリツーリズム(農村観光)と、地域の特産品であるバルサミコ酢、ワイン、生ハム、チーズなどの工房の探訪、それにGI(Geographical Indication=地理的表示)や農業、オステリア(osteria=料理店)などの連携を視察するというものです。

生ハム工房

パルメジャーノレッジャーノ工房
旅行手配は1日ごとに詳細な日程を決める
旅を組んだのは、静岡県浜松市の国産素材でソースを製造販売するトリイソース鳥居大資さんと、群馬県下仁田で国産大豆で納豆を製造販売している下仁田納豆の南都隆道さんのリクエストもあったことからでした。鳥居さんを取材したときに、岡崎さんから学んだイタリアのアグリツーリズムのことをどうやら話したらしいのですが、すっかり忘れていました。それを聞きつけた南都さんから「ぜひイタリアへ案内してほしい」という連絡があり、お二人の希望も入れながら旅の日程を調整していただいたのでした。
旅行の手配は、岡田奈穂子さん(株式会社Table a Cloth代表取締役CEO )にお願いしました。岡田さんは、世界40か国160都市に行かれていて、個人旅行のコーディネートをされている方です。フランスやイタリアのアグリツーリズムの現地の宿泊施設もよくご存知。
事前に岡崎啓子さんと岡田奈穂子さんと、鳥居さん、南都さんとZOOMで打ち合わせを行い、そこから日程が組まれました。旅行前に岡田さんから送られてきた「旅行スケジュール」が素晴らしい。1日ごとの訪ねる場所が一覧になっていて、どんなところで、どんな学びの場なのか、1冊のファィルが作成されて、現地の様子と地図とが写真入りで入っているというもの。つまり、現地に行く前に予習ができる内容になっているのでした。
素材の背景から解説されティスティングもある視察行程
旅は成田空港からエティハド航空でアブダビ空港経由でミラノへ向かいました。
メンバーは、鳥居大資さんと、鳥居さんと共同事業を予定しているという料理家で農業も手掛ける今津亮さん、それに下仁田納豆の南都隆道さんと妻の由美さんです。
空港では、岡崎啓子さんが手配してくださったワゴン車の運転手さんが待っていてくださり、そこから、現地へと赴くこととなります。まず1日目は、自然農法で野菜類を栽培する若手農家の圃場見学から始まり、アグリツーリズムのレストランでの食事、ワイナリー見学、アグリツーリズムの宿泊。2日目は、畜産から循環型の資源の取組、クラフトビール施設と続き、3日目は加工野菜工房、バルサミコ酢、4日目は、パルメジャーノレッジャーノ、パルマハム、5日目は、トリノの食品店イータリーで、販売されている食材の背景から紹介する店内案内があり、ランチをいただくというものでした。

農場訪問ll Filo di Salice。福岡正信さんの自然農法を取り入れた活動


有機ワイナリーCantine Lurettaの訪問


「イータリー」の店内と料理

工程は十分な時間がとってあり、現地では、現場の担当の方や代表の方々が案内についてくださり、製造の行程を丁寧に紹介されます。ティスティングもあり、どこもが綺麗な冊子が用意されていました。
素材の背景のストーリーがしっかり把握されていて、ここしかない食が明確に語られます。それらが、地域にあるオステリア(食事ができる現地のお店)やアグリツーリズムの食事にも連動しているのです。美味しさが、背景から素材から作り手までが、わかるというこまやかな手配で、すべてが学びの深いものとなりました。イタリアの食が、観光に繋がり、多くの人を惹きつけているというのがよくわかります。ひとつひとつ、どれをとってもクオリティの高いものでした。

1日目の昼食アグリツーリズムのレストランBosco Gerolo


試食で提供されたカットしたパルミジャーノレッジャーノ
パルミジャーノレッジャーノの素敵な時間
オーガニックの畑の見学から次に訪ねたのは田園に囲まれたルレッタ・ワイナリー。オーガニックでワインが造られ、貯蔵するエノテーカは、まるで古城のような建築物のなかにあり、その優雅な佇まいに圧倒されたのでした。
パルマの生ハム工房では、生肉カッティングのパフォーマンスがあり、熟成させる工房では、天井からぎっちりと吊り下げられた生ハム、その行程や室内の温度管理までが案内され、試食もあるという丁寧さ。どれもこれもが、感性を揺さぶる体験。語りつくせないほど豊潤な毎日。
訪ねたなかで印象に残った一つに「パルミジャーノレッジャーノ」の熟成を手掛ける工房があります。というのも、よくパスタやサラダにも使うからです。しかもこの工房は、一度できあがったチーズを購入し、さらに熟成させて、よりうま味を引き出すというところ。販売する専門のお店も持っています。
工房に入ると天井まで丸型のパルミジャーノレッジャーノがずらりと並んで壮観。
1個は40㎏もあるとのこと。工房を運営する方からのチーズのルーツの歴史解説から始まりました。
「ベネディクト派(カトリック教会の修道会)の人たちは、特にイタリアの農業をすごく進展させた。農業と労働は祈りと同じ大切な修行のようなもので自給自足をしていた。彼らが牛もたくさん飼っていてミルクがとれ、それをどうしようかというところから生まれたチーズです」

そこから現在の工程が紹介されます。朝搾乳した5 0 0 ℓの牛乳と前の晩に搾乳した5 0 0 ℓの牛乳を、1 0 0 0 ℓ入る加熱できる大きな器に入れ、そこから二つのパルミジャーノレッジャーノの玉が作られます。
牛乳を26度くらいまで温め子牛の4番目の胃から採れるレンネット(凝乳酵素)で固めます。
その次に凝固したものを崩し56度くらいまで温度が達したら火を消し固形分と液体分を分離させます。
生乳を取り除き、底のほうに残ったものを麻の袋に入れ吊り上げ液体を落とし夕方まで吊るしておきます。それから木枠に入れます。さらに袋の目の細かいものに入れ替え、パルミジャーノレッジャーノの文字と模様が入っている型に入れます。製造年月日も印されます。2日間ほど置いて、今度は塩水のプールのようなところに入れた日から20日くらい置いておきます。
そこから出して熟成に入ります。熟成期間は最低でも12か月。そして製品規格を満たすこととなります。
パルミジャーノレッジャーノのコンソーシアム(共同事業体)の方を呼び、ハンマーのようなもので叩き、音の調子で品質検査し、均一な音がでれば合格で刻印がされます。
1年間にパルミジャーノレッジャーノは地域全体で4 0 0万個生産され、そのひとつひとつチェックされるのです。
不合格の例は音が違い、中が割れているか穴が開いている。これは味が劣るわけではありません。イタリア産チーズとして一般的な名前で販売されます。
案内された工房は、12か月を経て規格を通ったパルミジャーノレッジャーノを仕入れて、さらに12か月追熟させます。
彼に言わせると「もともと食べ物というよりも、味をつける調味料的な役割で生まれたチーズですから、やはりしっかり熟成させないといけないと思っています」とのこと。さらに36か月熟成もあるそうでパスタの料理に合わせるためだといいます。
工房は木を主体に造られ窓の開閉で温度調整がされ自然環境のなかで熟成されます。
ちなみにチーズを造る牛は、伝統的な茶色いブルーナアルピーナという種類で、餌も協会が規定したものを与える決まりになっています。
その蘊蓄と丁寧な行程に感心するとともに、さりげなく料理に使っていたパルミジャーノレッジャーノの味わいの深さと奥行きを噛みしめた素敵な時間となりました。
優雅な環境が備わっているアグリツーリズム
宿泊は、アグリツーリズムを手配していただきました。泊まったのは2か所。それと1か所は、代表の方に、これまでの取組の経緯を紹介していただいたのです。
アグリツーリズムの宿泊の施設がどれも素晴らしい。クオリティが高い。3か所ともレストラン、プール、BBQ、ホールまでもがあり、庭園も広く、優雅に過ごせる施設となっています。宿泊の部屋は、ダブルベッド、シャワー、トイレも、それぞれがあり、快適な空間が整備されていました。
イタリアの岡崎啓子さんが、ママ仲間と、「今度、子ども連れてどこに行く?」と、アグリツーリズムをよく利用するという理由がよくわかります。
泊まった1軒目は、郊外の「Agriturismo La Coranina(ラ・コラリーナ)」。古い建物を活かし入口から入ると右手に大きなダイニング。正面はエレベーターもあり2階3階が宿泊施設。部屋は11室。入口の左手奥が広い調理室となっています。庭にはBBQができる場所やプールもあります。別棟の建物は、天井も高く椅子が並び、会合や結婚式もできる仕様。屋根裏部屋に続く螺旋階段があり、息子さんたちがDIYで改装されているとのことでした。
敷地は、葡萄畑が8haに、バラ園・人口の池と公園のような緑地が4ha。果樹園が2haもあります。
ここの建物と土地は、ルチーア夫妻が、息子さんに将来住む家を探していて、気に入り、2019年に購入したとのこと。もともとアグリツーリズムで倒産し10年近く空き家だったそうです。町から現在の地に移り住み暮らすようになったのだそう。

部屋の外観と入口。庭にはプールもあるという豪華さ。


宿泊施設の入り口

アグリツーリズムに続く道
アグリツーリズムの資格取得には授業と試験がある
ルチアーノさんは元郵便局勤務。夫のブルーノさんご自身は事故があり、体が不自由になってしまって、身体障害がある方たちの、サポートをする組織のボランティアをやっていたそうです。
購入額は60万ユーロ。資金は自分たちの貯金。郵便局の退職金。相続したものと家族親戚にヘルプしてもらったもの。あと借り入れをしたそうです。
今回のアグリツーリズムの旅でわかったのは、アグリツーリズムを開業するには、資金も多く必要ですが、そのための補助もあること。そして、資格を取得すための授業を受けなければならないということ。起業のための学びの場があると知りました。
まず、アグリツーリズムを運営するには農業法人が条件。運営のための講座も受けねばなりません。
ルチアーノさんによると、農業法人とアグリツーリズムのコースは、どちらも農業連盟のような組織があり、そこが開催するレッスンを1週間に2回、約6カ月受けたそうです。
農業法人の方は、受講料700ユーロ。土地権利、栽培品目、法的な部分、化学薬品など、どうやって使うかとか。実践的なものでトラクターの運転とか含まれています。
アグリツーリズムは、受講料1000ユーロ。国の定義や法律があり州ごとに規則がきめられています。それに関する勉強、衛生管理法、シェフを呼んでの栄養学とかのコース。弁護士さんの法律と使える補助金関係やお金の面での授業もあったとのこと。

ルチアーノさんのアグリツーリズムの別棟には、ホールやラウンジまでがあった。

農業に新たな事業を付加をすることから始まった
そして2軒目に泊まったのが、エミリア=ロマニャ州フィオレンツオーラにある「バッティブーエ(Agriturismo Battibue)」。
丘陵地にあるのですが、周辺はよく手入れされた樹木があり田園地帯となっていて、まるで公園のようです。サイトを観ると、部屋の様子や調度品などが紹介されています。 ベビーベッド付き部屋もあり、幼児連れでも泊まれます。シャワー、トイレが、それぞれにあります。
広い庭、部屋、レストラン、テラスがあり、パーティ、ブライダル、会社の会議も使えます。キャンピングカー向けのスペース、電動自転車レンタルもあります。
経営者のジャンピエトロ・ピザ―二さんは、親の農業を継いでアグリツーリズムを始めました。1998年にレストランから始めました。2006年6部屋を開業。2012 年、追加で5部屋を開けました。
6歳上のお姉さんがいて、姉と農業法人を二つに分けました。理由は、州の決まりで、アグリツーリズムは部屋数12室までとなっているためで、部屋数を増やすために2つの法人にわけたとのこと。
現在、お姉さんが12室。ジャンピエトロさんは9室。ジャンピエトロさんも姉さんも、一時は、外で働いていたそうです。レストランを開けるとここに戻ってきて働くようになり、親の農業を継ぎました。
農場としては大規模でした。農業でトマト栽培を2015年まで150haやっていました。現在、畑は25ha、貸しているのが45ha。全部で70haがあります。今は野菜や果物と穀類を育てています。
ジャンピエトロさんに言わせると「イタリアの基準でいうと、僕たちのタイプというのは、中くらいも達していないのではないか」とのこと。
アグリツーリズムを始めた理由は2つ。古い建物の再利用。納屋、豚小屋、干し草の貯蔵庫など、今では使わないものがあります。もうひとつは、親の代に栽培していたトマトの価格が下落したこと。新たな事業を手掛ける必要があったからです。

リノベーションして生まれ変わったアグリツーリズム


アグリツーリズムの教科書
学ぶ場としてのインターンシップ制度もある
アグリツーリズムを開業する際には、国の支援事業の利用ができると、ジャンピエトロさん。
EUには、7年ごとのサイクルで農村開発プログラム(Rural Development Programme=RDP)が実施されています。この期間中、1つの法人は最大2件まで補助申請が可能とされており、1件あたりの申請額の上限は50万ユーロです。平野部での補助率(助成率)は申請額の40%ですが、丘陵地・山間地域では50%、さらに若い世代の農業従事者であれば55%となります。
しかもアグリツーリズムでは、レストランで出す食事の原材料の35%は自社のもの、80%が地域のものか州で生産されたものという決まりになっていて、3年に1回、州政府から適正な運営がされているか検査が入るというではありませんか。
ジャンピエトロさんからも、アグリツーリズムは、資格試験があると説明を受けました。受講料は1000ユーロ。授業は150時間。教科書もあります。80%以上の出席で試験に合格しないといけません。授業ではアグリツーリズムの現地でのインターンシップもあります。ジャンピエトロさんも講師として、現地でインターンの受け入れを行っています。
さらにアグリツーリストという労働組合組織があり、会員になると会計や労働に関する運営のサポートを受けることができます。
ボローニャには、アグツーリストの事務本部があり、ウエッブサイトの運営がされていて、そこから全国や海外に紹介がされ、誘客に繋がっているのです。
これまで、何度かイタリアへ行き、アグリツーリズムの宿泊施設に泊まりましたが、どこも快適で環境がよく、食事も地域ならではの美味しいものが出てきて、かつ、その食の背景まで、語りがあると感心をしていたのですが、実は、しっかりと学ぶ場があり、その支援体制もとられているということを改めて知ることとなったのでした。
現在、エミリア=ロマニャ州では、アグリツーリズムの宿泊施設は1251軒にもなったといいます。そのことで、都市や海外からの観光客も増え、また施設も充実していることから、会社の商談会、会合、イベント、パーティ、結婚式などにも使われるようになっているというから驚きです。

レストランの外観と内部。ここはかつてチーズ工房として使われていた。

食と文化と景観の融合の取り組みを学ぶ
イタリア共和国北西部ピエモンテ州クオーネ県では、アルド・サルトーレ氏にお会いすることとなります。今回の旅のコーディネートをしてくださった岡崎啓子さんの強い薦めからでした。
南都隆道夫妻、鳥居大資さん、今津亮さんたちは、仕事の都合で早めに帰国。岡崎さんから、少し日程を伸ばし、ぜひあったほうがいいと言われたのがアルド氏への訪問でした。
岡崎さんによれば「ご自身もワイン生産をしながらアグリツーリズムを経営、アルバ観光協会とも懇意にされており、長年にわたり地域の食と観光の振興に関わっている地元の名士」。
続けて「サンタ ヴィットリア ダルバ城のふもとにあり、ブドウ畑と森の自然の円形劇場に守られた歴史ある邸宅。テラコッタの床、火のついた暖炉のパチパチ音、温かみのある木製の天井から取られた年代物の家具。ヴァルディスピンソのリビング ルームは、この土地の魅力的な歴史を思い出させます」とありました。
ホームページによれば、宿泊施設と部屋は地域のワインの名前がついていて、それぞれの部屋が、どれも個性的。インテリアは古い農家のものが使われており、エレガントな 19 世紀の家具が置かれています。
ゲストは広い共用キッチンと暖炉のあるラウンジを利用できます。共用屋外スペースでは、季節限定のスイミングプール、バローロ樽で造られたサウナ、バーベキューや薪オーブンを備えた屋外クッキングコーナーも楽しめます。部屋には以下のような種類があります。
・ダブルベッドルーム: アルネイスとバルベラ。カップルに最適な 2 つの独立した部屋には、ダブルベッドと専用バスルームが備わっています。
・ミニアパートメント:ロエロ。宿泊施設は最大4名様まで宿泊可能。格天井のある大きなダブルベッドルーム、ダブルソファベッドと小さな簡易キッチンのあるリビングルーム、バスルームで構成。
・ネッビオーロ: アパートメント。4~5人用の快適なアパートメント: ソファベッド付きのリビングルーム、キッチン、シングルベッド2台のある中2階、ダブルベッドルーム1室。
・ファヴォリータ :アパートメント。スイミングプールに面した5名用の宿泊施設で、キッチン、ソファベッド付きのリビングルーム、グラウンドフロアのトイレが備わっている。上階にはダブルベッドルームとシングルベッド 3 台を備えたベッドルーム。テーブルとバーベキュー付きの外部ポーチ。
・モスカート:アパートメント。プールサイドの宿泊施設。屋外で食事ができるテーブルを備えた外部ポーチが付き。グラウンドフロアにはダブルソファベッド付きのキッチンとバスルーム。上階には専用バスルーム付きのダブルベッドルームがあります。
「かつてサヴォイ家の邸宅だった高貴な農家は、現在、過去と現在が可能な限り最良の方法で共存する場所でゲストを迎えています」とあります。なんとも優雅なアグリツーリズムなのでしょう。
https://valdispinso.it/




アグリツーリズムの建物と部屋の様子。

アルド・サルトーレ氏とコーディネーターの岡崎啓子
自然と地域の食文化が海外の人を惹きつける
アルド・サルトーレ氏にお会いすると、とても気さくな方で、こちらの質問になんでも答えてくださる。アグリツーリズムの流れ、現在にいたるまでを詳細に話してくださった。
「このランゲとロオレ地方は、1984年、1985年くらいから、この辺のエリアの名前について少しプロモーションを始めて、最初に注目したのはフランス人が多かった。
当時のこの辺りの、宿泊施設の規模を話すと、84の自治体があるなかで、ベッド数は2500くらいだった。それもブラの郊外に、4,5軒のホテルがあるくらい。
90年代の終わり頃にアグリツーリズムの施設もできるようになってきた。85年にこの地域の観光組合ができて、州としても観光のプロモーションをするための組織ができた。で、各県の重要な都市には支部ができました。
90年代になると、だんだんこの地域のことが知られるようになってきて、今、自然とか、環境とか、人との繋がりとか、食というような嗜好にむいていくようなって、それが2000年代になって一気に爆発的にシステム化されて広がった。
最初、人が少なかった頃は、例えば、どこかの大きな工場で、労働力が必要であるとか、工事があるとかで、仕事があって、寝るだけみたいな、そのための宿泊施設が多かった。それがだんだん観光になった。
観光の傾向も、かつては「芸術の町」や「文化の町」といったキャッチフレーズが主流でしたが、次第に自然や地域の食文化が前面に出るようになりました。イタリアの魅力を海外に伝えるため、観光系の雑誌やメディア関係者を対象に招待ツアーが企画され、その結果、フランス人だけでなくスイスやドイツからの観光客も増加しました。1990年代後半には宿泊施設のベッド数はおよそ1万でしたが、現在では正確な統計はないものの、体感としては6万から8万にまで増えていると考えられます。
2000年代に入って、地域外の資本も入って、かなり高級なリゾートを創たりとかいう動きにも発展しました」
アグリツーリズムの流れを伺うと、ここ20年くらいで、大きな広がりになったということがわかります。その頃、アルドさんも観光協会の会長も務めていたといいます。
地域の食のストーリーを明確化しプロモーション
「なにか、この地域を、特徴づけるポイントをあきらかにしましょうと、いうことであげたのが、まずは白トリフェですね。食べ物だけでなく、自然環境とか、ストーリーを、どうやってそれを探しにいくのか、犬がいたので、訓練して、ストーリーをわかるようにした」
アルバは、ピエモンテ州の州都トリノより電車で約1時間半。アルバ市内にあるトリュフ祭りに、インタビューの後でかけたのだが、会場のある町は、たくさんの出店が出ていて、道は人であふれていたのでした。
「もうひとつが、ワイン産業のシステムが非常に成長して、例えば、バローロという、イタリアでも重要なワインがありますけど、これもトリフェと同じような、この地域の重要な、イメージする、反映するような、ものになった。
そして3つ目に、これらのトリフェとワインを連携させる景観を、これをいかに美しくみせるかという努力をして、この観点を盛り込んだパンフレットを作った。これらの観点を十分に盛り込んだ。当時は、まだ紙媒体でしたから、パンフレットを創って、優秀な写真家とか、デザイナーを入れて、そういうパブのツールを作った。
で、もうひとつは、その当時、州などの観光協会から国内外の観光、ツーリズム系の展示会に、人が派遣されるようになって、この地域のプロモーションを行うようになった。
そして今から33年前に、料理人と地域の料理の方で観光コンソーシアムを作った。それは 半パブリックで、半プライベートなもの。というのが自分たちで投資もしたし同じだけ州にもお金を出してほしいとお願いをした。
それをやったことで、例えば、いろんなイベントだとか運営できるようになった。面白かったのは、ニューヨークのセントラルパークに、トリフェハンティングの犬を2匹連れていって、公園の中にトリフェを隠して、でマスコミを呼んで、みんなでトリフェ探しをやってた。どれだけニューヨークの町は盛り上がったか。だけどリスが食べた(笑)。そんなトラブルもありましたけど。そんなこともありました」
プロモーションのための地域資源調査がされていて、それをストーリーに組み込み、メデァアに発信していくという、こまやかな活動があったことがわかります。

トリフェ祭りで賑わう町

海外の人たちにワイン、食、トレッキングなどプログラムを提供
「2008年には、2万8000ユーロの資金で気球を買って、そこにアンジェ・ロエロと書いて、1年間、ジャーナリストや、いろんな媒体の人にコンタクトして、気球に乗って、空から、高いところから葡萄畑とか城だとか、この地域の景観を楽しみにきませんかということを1年間ずっとやった。これを気球じゃなくて、直接、媒体のスペースを買うようなことをやっていたら、たぶん2億ユーロくらいかかっていたと思うので非常に小さな投資。小さいといっても安いもではないですけど、コンパクトな投資で巨大なリターンを得ることができたというのが気球のトライアルでした」
食と景観を繋ぎ、新たな観光プロモーションに繋ぐ、見事な、取り組みと言えるでしょう。
「まず、2003年の2004年のところで、国際的な、エノガストロノミー(ワインと料理の調和を楽しむこと、またはそれを目的とした観光のこと)のツーリズムの奨学金ですけれども、名前としては学ぶための体験してもらうための国際レベルでのツアーオペレーターに対するオファーできる仕組みを作った。こちら側が提供して体験してもらうという、さらに、この地域のプロモーションのために官民半々のコンソーシアムとピエモンテ州と、観光協会で、お金を出し合った。これは国際コンソーシアムとして、いろんな国のオペレーターの人たちに、例えば、ワインのテイスティング・コースであったり、ワイナリーやお城の訪問ツアーだとか、とにかくワインに関連する体験を、オファーするということを、仕組みとして作った。それを2年ごとに、どんどんプログラムを増やしていって、乗馬のお散歩とか、あるいは葡萄畑の間のトレッキングだとか、あるいはレスパ(原付の)でツーリングをするとか、そういうことをどんどん増やしていって、今は、それが標準化されたので、やっていないんですが、当時、重要な取り組みだったと思う。そういうことを見せて、いろんな過ごし方を見せて、滞在日数を増やすという取り組みを、行いました」
ワインのティスティング、散歩、トレッキングなど、これまでになかった体験プログラムが作られて、それがアグリツーリズムと連携できるようになっている。手渡されたパンフレットは、いくつもの体験プログラムが、美しい写真とともに作成されていて、それぞれにQRコードが付いています。つまりアグリツーリズムが、ただ農村で泊まるだけでなく、地域の食、ワインを楽しむのはもちろん、広域で楽しめるプログラムがしっかり作られていたというわけです。

体験プログラムのガイド Authentic Experiences LANGEHE MONFRRATO ROERO https://www.langhe-experience.it/en/11-authentic-experiences-langhe-monferrato-roero

これまで、何度かイタリアへ行き、アグリツーリズムに泊まったのですが、その度に、さまざまな体験、チーズ、ワイナリー、パスタづくり、などなど、楽しんだのですが、その度に、現地の方々が、丁寧に解説をして、その食の素材や背景を語り、ティスティングがある。思わず購入してしまう。なるほど、しっかりおもてなしの下地が作られていたと改めて知ることとなったのでした。
「今は、この地域にエノガストロノミーを目的にやってくるひとたちは、滞在日数は平均2・5日くらい。そうやって発展してくるなかで、いろんな宿泊施設で、ただ美味しいものをだすだけじゃだめだと、快適な部屋だけじゃだめだねと、施設のなかにプールを造る人が増えた。
それは、今日の観光協会のモットーにもなっているんですけれど、快適に気持ちよく過ごせるということが非常に大事で、食べるだけじゃなくて、滞在期間をいかに豊かに充実して自然環境のなかで、過ごしてもらえるかを大切にしている」
アグリツーリズムの開業にあたっては、150時間の授業、ワークショップの参加が必要で、合格しないと認可されないとは、今回の取材で知ったことですが、どのアグリツーリズムもレベルが高く、快適な宿泊観光ができるという背景には、組織化され、地域と人が連携し、ノウハウが共有化されて、接客からもてなしまで、全体のレベルが挙がっているのだと理解できたのでした。
以前、2019年にエミリア=ロマーナ州のアグリツーリズムで、レクチャーを受けたことがあるのですが、そのときは、広域で、車で1時間圏内の、さまざまな体験できるところのマップが示されて、山間地から海までが連携するようになっていて、1年中、さまざまな楽しみができるように集客・誘客の仕組みを学ぶようになっていました。今回のインタビューで、しっかりと農村観光の広域連携が、プログラムされてきたことを改めて知ることとなったのです。
スローフードとの連携で食文化が大きく広がる
「こういった成長のなかでは、スローフードの力もすごく大きかったですし、ポレンツォに大学ができたというのも、大きかった」とアルドさん。
「アルドさんも大学設立には投資していますし、運営委員会の理事を5年間勤めていた」とコーディネーターの岡崎啓子さん。
NPOスローフード・インターナショナルの始まりは「バローロ愛好協会」と、「ゴーラ」ワイン・グルメ雑誌のメンバーが結びついたのが始まり。1986年のこと。イタリア余暇食文化協会「アルチゴーラ」でスタートをする。ローマにマグドナルドが進出し、地方の地域文化と多様性を守り、ファストフードの画一化に対抗することから「スローフード」という名称が生まれる。
事務局はブラの街中にある。そこには、食事ができる「アオステリア・ボッコディウ”ィーノ」が開店。初期の頃は、ここに子どもたちを迎えての食の体験プログラムが行われた。
さらに地元のワインの試飲会、郷土料理の会食会、ワインや地域特産物の通信販売から始まる。地元の農家のワインやグルメ、観光のプロモーション活動が始まる。メンバーが左翼系のグルメ評論誌「ガンベロ・ロッソ」に参加。1987年「イタリアのワイン」発行。この本はイタリア、フランスのワイナリー見学、農業共済会(ワイン農家の勉強会)、ワイン関係者やジャーナリストの議論、生産者と消費者の教育から、地域の高品質のワインの売り出しが始まる。
1989年に「アルチゴーラ・スローフード協会」となる。スローフードの考えを「スローフード宣言」として採択。食の職人や会食のできる歴史的建造物のリスト「グルメ歴」をつくる。「ランゲ地方とロエロ地方のグルメ観光地図」「ランゲ地方の名ワイン地図、バローロ」などを出版。
1990年に「スローフード出版」を設立。郷土料理のガイド「イタリアのオステリアガイド」創刊。これは、農家や酒屋、レストランなど郷土に根差した料理を出す店が紹介される。
出所:『スローフード・マニフェスト』(石田雅芳・金丸弘美共著/木楽舎)
「そのことがこの辺りのガストロノミーツーリズムが発展するなかで、全体がひとつの建物だとしたら、大事な基礎部分になったピースだと思っています」とアルドさん。
続けて「今では標準化された取り組みですが、アルドさんは、その核にかかわっていた人なんですよね」と岡崎啓子さん。
「もうひとつ大事な基礎部分が、ここはユネスコの食文化創造都市のタイトルをとっているんですね、それのタイトルをとるにあたって、景観ということも改めて見直しましたし、食もオファーする食べ物と料理というのも、レベルがあがった。で、もしかしたらイタリア国内で、ミシュランスターレストランが集中している地域かもしれない。というのが40キロ圏内にミシュランスターレストランが22軒ある。
かつては、トラティア―は、お母さんの素朴な料理で、価格面でも、だれでも満足できるような料理を出していればよかったのだけれど、ツーリズムが洗練化されてきて、満足させなければならないニーズもレベルがあがってきている」とアルドさん。
その周到な食文化の発信に唸らされたのでした。
さて、アルドさんのアグリツーリズムの建物も庭も周辺の景色も、実に優雅に見える。インタビューはレンガで囲まれた壁のある大きなテーブルのある部屋で行われたのでした。
「実は、この下にチンザノ一族が巨大な地下壕を掘って、そこでワインを保存していました。醸造用の機械もここに置いてあり、膨大な量のワインとともに、戦時中もずっと保管されていました。この辺りはドイツからの侵攻にも遭って、ドイツ兵もこの地下壕を使っていたのですが、ワインのことはずっと秘密にされたままでした。戦争が終るとそれらを売り、そこから得た資本が、この地域で再出発するための重要な財源となったのでした。という本当の話を誰も話しませんでした。それが『サンタ・ビットリアの秘密 The Secret of Santa Vittoria 』(1968年製作/アメリカ)というタイトルの映画になりました。

ここにある家具は、300年くらい経っているかもしれません。あちらの部屋に牛がいて、動物たちの体温で、人間のいるこちらの部屋を暖めていた。そういう暮らしだったんですよ。まだ60~70年前の話です。昔は、貴族の裕福な人たちと貧しい農民らの間に、大変な格差がありました。それが今は、皆一様にムチ打たれている(税金を取られている)。こんな手の込んだ彫刻が施された家具でも、全く今日の嗜好と合わないから価値がない。でも私は芸術作品と思って大切にしています」
学びの多い充実の時間となった。
ブラでのチーズ職人ジョリートさんとの再会
イタリア・アグリツーリズムの旅で最後に旅行予定表になかった楽しく素敵な人と場所に引き合わせていただくこととなりました。
北西部ピエモンテ州ブラ市のフィレンツオ・ジョリートさんと彼の運営するチーズショップ『giulito F・ ORMAGGIジ ョリート・フェルマッジ』です。
ジョリートさんとも親しい岡崎啓子さんのおかげのご縁でした。
実はジョリートさんのお店に伺うのは2度目。その前は、妻・早苗と旅をした2008年のこと。お店には厳選されたチーズがずらりと並んでいます。地下にチーズ工房があり棚に大きな丸い塊のチーズが並んでいます。この地域ならではのチーズ「ブラ・ドゥーロ」。伝統的な食品であることを保証するDOP(原産地名称保護制度)ののマークがついています。熟成させたチーズを仕入れてさらに熟成をするということがあると初めて知ったのでした。
昔のチーズ造りの機材も置いてあり、子どもたちの食の体験講座も行っているとのこと。お店にはワインもずらりと並び、チーズとワインとの相性を学ぶティスティングも教えていただきました。
ジョリートさんの店で初めて味わい、すっかり魅せられしまったのが「Braciukブラチュック」。ブラ・ドゥーロを赤ワインの葡萄・バルベーラの搾りかすで漬けこんだものです。名前を翻訳すると〝ブラの酔っ払い〞。チーズの周りが葡萄を絞った果実が綺麗な葡 萄色で覆われています。
柚子色のようなチーズとコントラストがとても綺麗。
「ワインが大好きでチーズを合わせたらどうなるかと試して生まれた」とジョリートさん。
妻は〝ブラの酔っ払い〞の魅力に惹かれチーズ好きになったと言います。というのも彼女はチーズの独特の香りが苦手。ところがブラチェックは見た目がまるでチョコレートチップのよう。チーズの香りがしなくてすっと美味しく食べられたのだといいます。

「ブラ・ドゥーロ」のチーズを手に紹介するジョリートさん

ジョリートさんは、チーズのお店の3代目。
1920〜30年代にジョリートさんのおばあちゃんが、ブラの熟成したチーズをジェノバに運んでいたのだといいます。ジェノバはリグリア海に面した港湾都市で大きな貿易港。そこからチーズは船で運ばれアメリカへ輸出されていました。長旅も保存が効くチーズだったからだったからです。
1950年代。ジョリートさんの両親は、今とは別の場所のメルカート(マーケット)に店を出していました。ピエモンテ州はスイス、フランスにも近く山もあり交易点でもあったことから栄えていました。ジョリートさんは両親の店で働くこととなります。当時はチーズのほかにサラミも販売していました。
しかし20 年ほど経つとスーパーマーケットの時代が訪れ、そちらにお客さんが移っていったことから一度、閉店をしました。もうやれることはやったという思いもあったといいます。
ですが数年後に現在の場所へ店を開けました。その頃ブラでは1980年代にスローフード運動が生まれます。ジョリートさんも参加していたと伺いました。2000年、ブラ市が拠点となったスローフード協会と連携しチーズの祭典が始まります。アルバ、ブラ、ランゲ・ロエロ観光協会、イタリア・チーズ協会の協賛も受けた大掛かりなもの。イタリア各地、海外も含めさまざまなチーズが登場します。しかもブラ市の街並みの景観を生かし、町が歩けるようになっており、そこにテントが張られて、選ばれたチーズ生産者が、チーズを対面で販売します。古い建造物なかでは、チーズの「味覚のワークショップ」が行われるというもの。丁寧なカリキュラムが作成されています。教室が設けられ、壇上には生産者とチーズの専門家が並びます。机には皿に何種類かのチーズ、ワインがあり、素材と背景から紹介され、見た目、香り、味わい、食感をティスティングして書き出し、ワインとの相性を試します。チーズの生産地、国、牛やヤギなどの動物の違いなど、さまざまなコースがあり、その多彩で多様なありかたに圧倒されたのでした。
2007年にトリノにイタリアのよりすぐりの食材を集めて販売し食事もできる『イータリー』が誕生します。チーズコーナーはイタリア全土のチーズがズラリと並び圧巻。ジョリートさんは、イータリーのチーズの責任者としてオープンにも関わったのだそうです。

「イータリー」のチーズ売り場

イータリーが2008年に東京・代官山(当時)にオープン。輸出担当が当時勤務していた岡崎啓子さん。チーズ担当が片岡恵子さん(当時、寺山恵子さん)。片岡恵子さんは、フランスに住んでいたがチーズに嵌はまりチーズ工房を訪ね独学。フランスから車でブラのジョリートさんの店も訪ね知り合い、推薦を受け代官山のチーズ担当となったのです。そのときに働くこととなった長男・金丸知弘へ、チーズを教えてくださったのが、片岡恵子さんだったのです。
片岡恵子さんはイータリーを退職した後、一旦、故郷の北海道に戻り、その後、群馬県川場村の道の駅を夫と訪ねたとき、フレッシュ・チーズの魅力を語り『KAWABA CHEEZ』の立ち上げに参加することになります。そこで再びイタリアのジョリートさんを訪ね、また川場村にも来てもらいアドバイスも受け地元の畜産家と連携した瑞々しいフレッシュ・チーズを世に送り出し大きな注目となり。その川場村も、岡崎さんに教えられて訪ね片岡恵子さんと再会することとなりました。
群馬県の山間地にある川場村は、人口3,314人。 ここに1998年に開業したのが道の駅の「田園プラザ川場」です。大きさは東京ドーム1・5個分。農産物を販売するファーマーズマーケットから、蕎麦店、地ビール工房、甘味処を始め、子供の遊び場まであり、来場者は年間240万人。景色もよく美味しい食とくつろぎの場があることで、平日も満員の人気となっています。
「新鮮なミルクから生まれるフレッシュ・チーズを届けたい」群馬県川場村「田園プラザ川場」KAWABA CHEESE 片岡恵子さん
銀座の『GINZA SIX』6階に『イータリー』があることを知り妻と訪ね、川場村の「ブッラータ・フレッシュ・チーズ」(モッツァレラの生地の中に生クリームと裂いたモッツァレラの生地「ストラッチャテーラ」が詰まっている)がどんとのったピザをいただいたのでした。
ジョリートさんとのブラでの再会は、多くの出来事が巡り巡った至福の時間となったのでした。

ブッラータ・フレッシュ・チーズの乗ったピザ
●WANサイト連載「金丸弘美のニッポンはおいしい!」バックナンバー
https://www.kanamaru-jp.com/yotei/yoteidetail.php?&no=768&a=2017
●金丸弘美ホームページ
https://x.gd/6Vz5m






![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)












