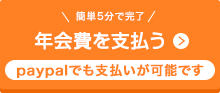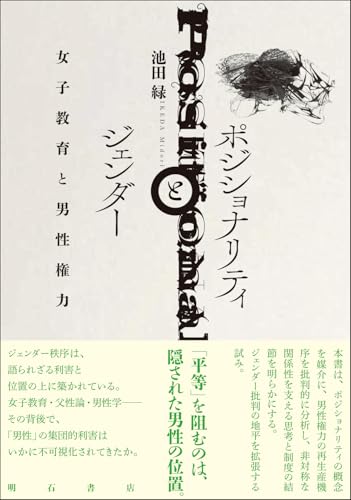『ドマーニ!愛のことづて』
監督・脚本: パオラ・コルテッレージ
公式サイト:https://www.sumomo-inc.com/domani
舞台は1946年5月のローマ。最初のシーンは朝を迎えた中年夫婦の寝室。目覚めた夫は、何も言わずいきなり妻の頬を張る。ほぼ無反応でそれを受けとめる妻は、着替えて朝食の支度にとりかかる。中学に上がる学費を出してもらえなかった娘はアイロンかけの仕事に、弟2人は学校に出かけていく。夫も不機嫌なまま家を後にする。
夫から無能だの何の役にも立たないだのとさんざん罵られていた妻デリアの1日は、労働の連続である。寝たきりの舅に朝食を運び、家を片付けたあと、裕福な家庭の老人に注射を打ちにいったり(腕がいいらしい)、下着の繕い物を届けたり、傘の修理仕事をしたり(ベテランなのに、働き始めたばかりの男の子より賃金が安いのは「女だから」)、よその家の洗濯物を干したりと、いくつもの日雇い仕事を掛け持ちしている。買い物をして家に帰ると、早速舅に呼びつけられ、また家族のための食事作りが始まる。
帰宅した夫は、娘と妻からその日の稼ぎをそっくり出すよう要求する。そして自分はめかしこんで、男たちが集まるカードゲームの場に、あるいは浮気相手のところに出かけていく。
モノクロで描かれるデリアとその家族の日常は、けっして暗いトーンに満ちているわけではないが、夫の暴力が何をきっかけに始まるかわからないという不穏さがつねに一定の緊張を観客にも強いる。そして、暴力のスイッチがはいったと感じた子供たちは全員、静かに部屋を出ていき、デリアだけがそこに残されるのである。彼らが暮らす集合住宅の前には中庭があり、そこに集う近所の女性たちにも、家の中で起きていることは伝わっている。彼女たちも緊張しながら、だが黙ってそこにいることしかできない。
この映画でDV夫として描かれるのは、デリアの夫イヴァーノだけだ。彼がいつもイライラして妻に理不尽な暴力を向ける理由の一つは、「2度も戦争に行った」こととされている。だがデリアとは境遇が異なる女性たち、たとえばみるからに裕福な家庭の妻、景気のいいバール経営者の妻、一人で店を切り盛りする未婚(または未亡人)女性も、直接の暴力は受けないまでも、夫たちや男性たちから「女は黙っていろ」「女には決められない」「女だてらに」という言葉を投げつけられる。夫の言いなりになるだけの母に失望し、別の生き方をしたいと願うデリアの娘、マルチェッラでさえ、恋人の甘いささやきに不穏な気配が混じる瞬間を経験する。
映画後半の展開の鍵となる、デリア宛に届いた封書は、このあからさまな家父長制と男性支配から逃れる希望の種を運んできた…のだろうか?
邦題の「ドマーニ」は「明日」を意味する。原題は「まだ明日がある」。
たしかに、映画の最後は新しい始まりを見せてくれる力強いシーンで終わる。だが、観客のわたしたちは知っている。1946年のイタリアで、あるいはその同じ年の日本で、明日の希望につながる大きな変化が起きたとしても、それだけでは家父長制は打破できなかったということを。この映画が600万人の観客を動員したイタリアで、今なおフェミサイド、つまり女性を標的にする殺人が相次ぎ、社会問題化していることを。
つまり、「まだ明日がある」というこの映画のタイトルは、1946年当時の女性たちにとってだけでなく、現代を生きる私たちにとっても、よりよい明日を願い続け、ささやかな行動を重ねることの重要性を訴えかけているのではないだろうか。
*追加上映のおしらせ
好評につき、以下の追加上映が決まったそうです。
・新宿ケイズシネマにて4/12~25の二週間限定
https://www.ks-cinema.com/schedule/
4/12~18 12:00
4/19~25 上映時間未定
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)