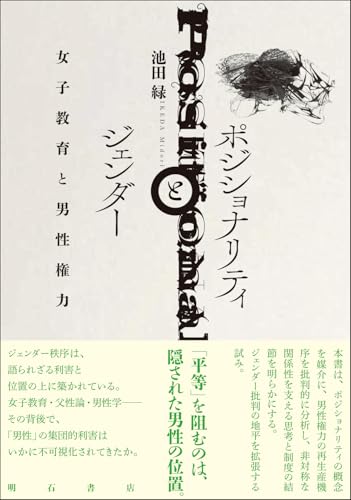views
2517
感傷にからめとられないために 田丸理砂
2011.07.08 Fri
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
たしかに荒木さんが前回のエッセイで指摘されているように、より「批判しやすい」他者に敵意を抱き、問題の本質を見失い、被害者同士がいがみ合うという構図は何としても避けなければならない。けれど柳澤桂子氏が『いのちと放射能』のなかで、放射能が人体の及ぼす危険をよく知りながらも、原子力発電の恐ろしさに無知であった科学者としての自らの責任を問うているように、今回の原発事故に関しては、原発には何となく反対というだけで、これまで再三再四繰り返されてきた警告にちゃんと耳を傾けず、あまり真剣に考えてこなかったわたし自身、忸怩たる思いがある。
というわけでこの間、原発関係の本を読み、「反原発」のデモにも参加したが、そこで感じたのは「反原発」「脱原発」という点では意見が一致しても、それ以上何か主張しようとすると、むしろそれぞれの差異のほうが鮮明になってしまうということだ(といってデモの参加をやめるつもりはないのだが)。今回の事故に対する東京電力や政府の対応、そしてこれまでの原子力政策を批判する一方で、再生可能エネルギーの利用だけでなく、わたしたちのライフスタイルの見直しを呼び掛けることも大切だと思う。次世代である子どもたちを守るということでは賛同できても、家族への回帰や、ましてや「がんばろう!日本」みたいなキャッチコピーには同意できない。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
3月11日の震災は、多くの人にとって今後の生き方や人間関係を考え直すきっかけとなっただろう。地震後、首都圏では鉄道路線のほとんどがストップし、数多くの帰宅困難者が出た。幸いにもわたしは夜遅くに家に辿り着くことができたが、その後しばらくは余震や計画停電のことも心配で、おちおち電車に乗ってもいられず、帰宅が遅くなるのも極力避けていた。6年前、仕事のために現在の住所に引っ越してきたわたしには、徒歩圏内に仲の良い友人もほとんどいない(ちょっとはいる)。3月11日以降、マンションのお隣さんや、行きつけの美容室の美容師さんと携帯電話の番号やメールアドレスなどのプライヴェートの連絡先を交換した。隣に住む女性が地震の日に心配して何度もわたしの部屋の電気が点いているかを確認していたと聞いてうれしかった。それからは会う人ごとに3月11日は何をしていたかを互いに語り合っていたように思う。こうしたこともささやかな「災害ユートピア」的経験なのかもしれない(レベッカ・ソルニット『災害ユートピア』)。
けれど震災をきっかけに、これまでの生き方を見直した結果、結婚を望む人が増えていると聞くと、想像はできたけれど、やはりがっかりしてしまう。自分の生まれ育った家族以外にかけがえのない存在が欲しいのだという。なるほど現在ある枠組みの中で一番親密な関係と思われているものから生き方を選ぶとすると、「結婚」ということになるのだろう。でも…フェミニズムは従来の意味での「結婚」や「家族」に回収されない親密な人間関係をずっと考え、発言してきたはずだ。それなのに、結局そこに落ち着いちゃうの、フェミニズムの言葉は届いていなかったのかと落胆してしまうのである。
いまだ収束の見えない原発事故の行方に不安を抱き緊張した毎日を送っているものの、首都圏で生活し、住む場所も仕事もあるわたしが、こんなことを言うのは思いあがりなのだろうか。危機的な状況下で地域社会でのつながりや家族が重要な役割を果たすことは、じゅうぶんに理解できる。それでもマスメディア等で「絆」や「家族愛」がことさらに感動的に語られるのには抵抗がある。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
酒井直樹氏は、今回の福島第一原発の災害の報道について、大手の報道機関が「醸し出された不安感を被害者に関する感傷的な逸話で緩和」することで感傷的な被害者への共感を生み出し、それにより「共感の共同体」の現出に手を貸したことを批判する。これにより「今回の人災の引き起こした企業、官僚、政治家、地方公共団体、技術者などから公衆の関心を逸ら」し、今回の原発災害によって露呈された「無責任の体系」に貢献してきたのだというのである(酒井直樹「〈無責任の体系〉三たび」『現代思想5月号 特集:東日本大震災』)。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
2011年初めに上梓された『女が国家を裏切るとき』において菅聡子氏は、文学的「感傷」性がたやすくわたしたちを「われわれ」として結びつけることに潜む暴力を指摘し、文学的感傷力に抗う読みの実践を試みている。今回の震災を文学作品として物語るには、まだしばらく時間を要するだろう。とはいえ文学以外の領域で感動的な物語を求める誘惑は、語り手の側にも聞き手の側にも、きわめて大きい。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
菅聡子さんは5月14日に48歳で逝去された。わたしは個人的には面識はないが、かつて菅さんが編集された『〈少女小説〉ワンダーランド』での菅さんご自身による氷室冴子論が忘れられない。菅さんは氷室冴子以降の少女小説を「つねに欲望の視線にさらされ、品定めされる自分に意識的にならざる」をえない少女が、「女の子が女の子でいることそれ自体が祝福される場所」として捉える。そこからは「女の子」「少女小説」、そして氷室冴子さんの作品への熱い思いが溢れている。氷室風に言うと、愛をもって「少女」小説が語られているのだ。そんな菅さんの言葉だからこそ、以下の『女が国家を裏切るとき』の第Ⅲ部「女の友情、そのゆくえ――吉屋信子と大東亜戦争」の結びの言葉は心に響く。
「〈花物語〉的なるものの行方が、その感傷性ゆえに国家の欲望との共謀を呼び寄せてしまったことは確かだ。しかし吉屋が思いを馳せた女性同士の絆がその真の意義を発揮するときが、必ず存在するはずだ。その行方を追跡することが、女性表現の〈いま〉をひらく契機となることを願う。」
菅さんの今後のお仕事を楽しみにしていただけに、その早すぎる死が残念でならない。心より哀悼の意を表します。
次回「倒れた樹を忘れるな」へバトンタッチ・・・・つぎの記事はこちらから
カテゴリー:リレー・エッセイ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)