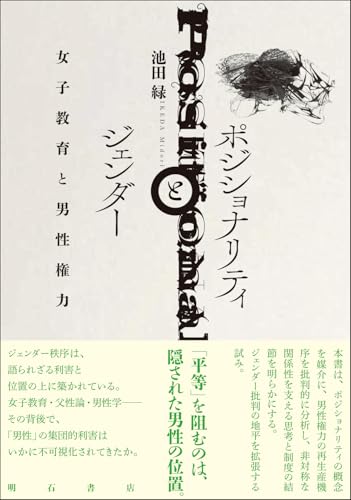views
1951
4.6 語り続けること 矢内琴江
2012.04.27 Fri
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
岡野さんが結んだように、私たちは「広島・長崎から何も学んでいない」、久しぶりに大田洋子の文章を読んでいて、奥歯をかみしめて、そう思った。東日本大震災から1年が経ち、今なおヒサイもヒバクも、現在進行形の問題があるにも関わらず、風化の傾向と、「魑魅魍魎」の何やら不穏な動きがある。その中で、原爆の経験を書き続け、忘れ去られていた作家・大田洋子の「だから私は原爆のことを書き続けてきたのだ」というつぶやきが聞こえてくる気がする。
大田洋子という作家に出会ってから、もう何年か経つ。でもまさか、出会った当時、彼女の言葉が、今、こんなにも生々しく響くことになるとは、思ってもいなかった。原爆投下後の、破壊の内の静けさ、人びとが助け合う様子、いかなる支援も来ない期間。3月11日以降、何度も聞いてきたエピソードと重なる。そして、被爆による死への恐怖と不安。新型爆弾で次々に死んでいく人たちの中で、「被害者たちは、客観と主観の間をさすらい、絶えず死に引きずられていることを感じないではいられなかった。(…)原子爆弾の被害の特質は、今後何年か経たなくては真実がつかめそうにない、その過剰な不安をもたらされたことのうちにあった。」また、原子爆弾の本当の恐怖は、その被害の目に見えないことにある、とも言った洋子の言葉は、今まさに、福島第一原発爆発後、何度となく聞いたそれだ。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
1903年に広島で生まれ、20代で、東京で作家として活動していた。戦中は、若い男女の青春を描いた戦争協力の作品で売れっ子になる。しかし、1945年8月6日、疎開中だった広島市で被爆。『コレクション 戦争と文学 ヒロシマ・ナガサキ』に収められた『屍の街』は、その経験をいち早く書いた作品だ。大田洋子自身、助かった人びとでさえ次々と死んでいくのを目の当たりにし、次は自分かという、恐怖と不安の中、死に急かされ、紙を集めて書き記した。そこで彼女が書こうとしたのは、単に破壊しつくされた悲惨な風景だけではない。「無欲顔貌」。原爆後の広島の人々の、心を失ったような表情だ。「白痴の顔で、精神状態までも痴呆状の無慾機構になっていること」。原爆、否、戦争という暴力の生の否定は、命を奪うだけではなく、あらゆる感情、思考、感覚の、一切を剥ぎ取った。その中には、原爆や戦争に怒ること、そして、平和を願うことも含まれる。「私どもは原子爆弾を怨むことさえ忘れていた」。さらに、戦後の復興モード、経済成長は、被爆が現在進行形の問題であったヒロシマやナガサキの人びとの声をかき消した。もちろん、平和運動があった。でも、被爆者は「こうあるべき」、原爆は「こう語られるべき」が乱立していた。その中で、復興から弾かれ、かき消されていく人々の表情、声、感情、つまり生を、紙面に刻もうとした大田洋子は、文壇でも、社会の中でも、孤立した。
ところで、洋子自身、原爆のことを書くのに、「ありきたりの文学の形にしがみついていることができない」と言った。言葉がもはやない、と。だから、文学的ジャンルも不明瞭となり、また、文壇からは構成力に欠けると評された。洋子が生活のために書いていた青春小説、彼女の「感情的な」性格、男性との関係も災いした。彼女は、「正しい」「原爆」作家ではなく、結局「原爆しか書けない」という意味で「原爆」作家と呼ばれた。いずれにしても、「こうあるべき」を押し付けるレッテルだ。それは、彼女の心身をも苦しめた。彼女は、原爆の「後遺症」だとするが、私は無理やりあてがわれた名前に対する、全身をもっての抵抗でもあったのでは、と考えている。レッテルへの抵抗と言えば、リブ。洋子自身は、フェミニズムからは程遠い人ではあるが、田中美津たちの運動も、「私」という全身が抱える矛盾でさえ引き受け、パワーに変えた、社会の、運動の中の、「こうあるべき」に抗う運動だった。「化粧か素顔か」の二者択一ではなく、「やりたければ化粧も素顔も自由自在」。過去も未来も全部含んでいる「今ここに生きている私」を丸ごと引き受ける。しかし、戦後も全国で「無欲顔貌」を生み出し続け、原発を許した社会は、このパワーを抑圧し、またリブの物語も歪めて、型に押し込めた。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
東日本大震災から一年が経ち、すでに様々な記録が出版され、写真や映像で公開されている。けれども、風化が懸念される中で、私たちがしなければならないのは、単に数や、メディアの問題でもない。なぜなら、結局それらが「こうあるべき」、「こう語られるべき」物語を語り繰り返せば、私たちは、再び「無欲顔貌」を作りだすだけだろう。物語の真実は、トリン・T・ミンハも言うように、「論理で筋づけられたり」、「尺度」で測れるものではない。物語は、むしろ、矛盾、曖昧さ、不明瞭さ、飛躍、を孕んでいる。否、「矛盾」と見なすのは他者で、それは語る「私」にとっては、生の体験、そのものだ。だから、「私」が「そう語られるべきだと思うやり方で」、それぞれが今生きている3.11を、語り続けられること、そのことの方が、むしろ重要なのではないだろうか。3.11を風化させないために、そして同じ過ちを繰り返さないために。
次回「<オンナのカラダ>を語る言葉」へバトンタッチ・・・・つぎの記事はこちらから
カテゴリー:リレー・エッセイ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)