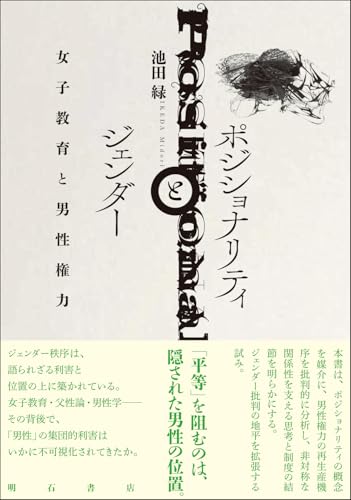views
2505
語りかける証言 千田有紀
2011.09.16 Fri
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください. 内藤さんのノルウェーの事件からみるヨーロッパとイスラムの考察、とても興味深かったです。イギリスでの暴動なども重ねて考え合わせるにつけ、外から敵が来ることばかりを想定するのではなく、内にいる「他者」を「敵」にしないことを考えなければならないのではないかと思いました。なんだかこのエッセイ、続けて読むと旅シリーズになってきているような気がしないでもないですが、御多聞に漏れず、わたしもこの夏アメリカに調査旅行に行ってきました。
アメリカでは国内線に乗るにも、セキュリティの厳しいことには驚かされます。見ていると、子どものサンダルが脱がされ、また別の子どものリュックのジュースが取り上げられて機械にかけられ(とんだ小さなテロリスト)、日焼け止めやリップグロスまで厳しく制限(どんな爆弾つくるというのか)、という仰々しさでした。とくに靴を脱がされるのはアメリカ人には屈辱らしく、唯々諾々と従いながらも不快さは抑えきれないよう。9・11前にはIDなくても乗れたし、国内線のセキュリティなんてあったかな、という気がするのに、本当に世界は変わってしまったと思います。
世界が変わってしまったといえば、やっぱりこの話題から離れられない。3・11以降に、わたしたちの住む世界は完全に変わってしまいました。移動の機内で読んだのは『チェルノブイリの祈り -未来への物語』。チェルノブイリに関係したひとびとのお話を、著者のスベトラーナ・アレクシエービッチが集めた証言集です。いろいろなひとたちの。そこにある物語は多様でありながら、それでもなぜか既視感が存在します。真実は逆で、チェルノブイリで起こったことをわたしがじゅうぶん耳を傾けて来なかったので、いまさら未来からすでに起こってしまった過去に既視感を感じるという転倒をしているにすぎないんですが。でもいろいろな意味で考えさせられる一冊でした。
まずはチェルノブイリで失ったものについて: 「ぼくらが失ったのは町じゃない、全人生なんだ」というひとがいれば、「爆発したのは原子炉じゃない、以前の価値体系すべてなんだ」という意見にさらに踏み込んで、ロシア人の信じるものが「原子力」から「市場経済」に変わったと嘆くひとがいる。かと思えば、「世界が終わろうとするときにも、悪のメカニズムは機能するのです。……この世の最後を前にしても、人はいまとなんら変わることはないんです。いつでも」というチェルノブイリを撮影した映画カメラマン。何もかもが変わってしまったけれども、でも非常時で繰り広げられる人間の(崇高さと)醜さは変わることがない。日本でも3・11以降にいろいろな亀裂が走っているけれど、みんなが震災や事故を契機に変わってしまったせいではないと思う。むしろ今まで巧妙に隠していたそのひとのひととなりや意見の違いが、否応なしに前景化し、つきつけられているだけなのではないかと。
「いつも通りの生活」: チェルノブイリでもいろいろと平時とは違う日常が現われているけれど、ひとびとはできるだけ日常を続けようとしている。例えば事故の翌日、「朝八時にはもう防毒マスクをつけた軍人が通りを歩いていた」と証言するプリピャチに住んでいた女性は、「通りに兵士や装甲車を見たとき、私たちは驚いたりしませんでした」といい、事の重大さに気づくどころか、「軍隊が救援にかけつけたんだもの、もうだいじょうぶよ」とむしろ安心したといっている。
また「チェルノブイリの子どもたち」代表のロストワは当時、「チェルノブイリは連中(当局)の問題よ」と考え、自分からは「遠くのこと」と思っていたという。「ところが、牛乳びんに<子ども用><おとな用>のラベルが貼られたとき、これは一大事とびっくりしたのです。そう、私は党員ではありませんが、やっぱりソビエト人なんです」。しかしラディッシュの葉が巨大化し「不安にかられても、その夜テレビをつけると『煽動に踊らされないでください』といっている。それですっかり疑いが消えてしまうのです」。 システムに対する不信(体制は変わりっこない)と信頼(軍隊は守ってくれる。報道は正しい)が交錯するなかで、ひとびとは以前とは変わらない生活に固執する。それは理解可能な心理的メカニズムではある。がしかし、そのためにはそれに従わないひとを排除し、同一化をもとめ、結果として自分たちの身を危険に晒してしまう。
また同じ工場のドイツ人が「医者と線量計と食べ物の検査を要求した」ことにロストワは、「まあ、ドイツ人っていうのはこんな人間なのね、…ヒステリーなんだわ。臆病者よ。ボルシチやメンチカツの放射線を測っている。こっけいだこと」と馬鹿にしている。そのいっぽうで、「そこへいくとわが国の男たちはほんものの男よ。さすがロシア男児だわ。死にものぐるいで原子炉と闘っている」とソ連の男たちを褒めたたえていた。そこでは他国の男性を「ヒステリー」と女性化し、自国の男性の男らしさの賞賛がおこなわれていたのだ。
しかしすべてがすんだあとでロストワは当時を振り返ってこう考えるようになる。「でも、これもやはり一種の無知なんです。自分の身に危険を感じないということは。私たちはいつも<われわれ>といい<私>とはいわなかった。<われわれはソビエト的ヒロイズムを示そう>、<われわれはソビエト人の性格を示そう>。全世界に!…チェルノブイリのあと、私たちは<私>を語ることを学びはじめたのです」。もちろん、原子炉と闘っているひとたちは劣悪な環境で重要な任務を担い、皆の犠牲になった。誰にでもできることではない。しかしその犠牲を賞賛によって推進し、まるで<われわれ>の業績であるかのように誇っているとしたら、それは罪深いことではないだろうか。
ある兵士は語る。「ぼくは行った。…志願したんです」。「男が熱中できることなんです。ほんものの男たちがほんものの仕事をしに行くんです。ほかのやつら? 女のスカートのしたにもぐってな」。彼はすべて――勲章、特典、アパート、車、別荘――をもっていたため、志願してチェルノブイリに行ったのは、純粋に「男のほんものの仕事」のためだった。そうでない男は「女のスカートのしたにもぐってな」というような弱虫だと。ここでも鍵になるのは、「男らしさ」である。 ただこの話の幕引きは、かなり切ない。「家に帰った。あそこで着ていたものはすっかり脱いで、ダストシュートに投げ込んだ。パイロット帽だけは幼い息子にやったんです。とてもほしがったから。息子はいつもかぶっていた。二年後、息子に診断がくだされた。脳浮腫…ぼくはこれ以上話したくない」。
チェルノブイリでは強制と自発性が混在している。みなが限られた情報、限られた選択肢のなかで、必ずしも強制ばかりではなく、ときには自発的にものごとを選択して暮らしている。「私たちには想像もつかないことが起きたのよ」といい子どものために「避難しよう」と提案する母親にむかって別の母親が罵る。「みんながあなたみたいなことをしていたら、私たちはどうなるかしら?
戦争にだって勝てっこなかったでしょうよ?」。戦争のようにみんなが一丸となって団結すべし。この証言をした女性は傍で見ていて、避難しようと提案する女性を「集まりをだいなしにしてしまった」と「憎んだ」という。 「私たちは子どもに晴れ着を着せて、メーデーの行進につれていきました。行っても、行かなくてもよかったのです、自分で選択できました。強制されたり要求されたりはしませんでした。しかし、私たちは義務だと考えていました」。「そのようなとき、そのような日には、みんな一緒にいるべきなのです」。「通りへ走りました。群衆のなかへ」。のちにこの女性は後悔を込めてこう語る。「あの、メーデーの行進を私は忘れないでしょう」。 騒ぎのさなかで、何が正しく何が間違っているのか判断することはとても難しい。ひょっとしたらのちに振り返ってさえも難しい。わたしたちは過去から何を学ぶことができるのか、混沌とした日々が続くなかで、考えさせられた。
次回「わたしたちの〈日常〉の行方」へバトンタッチ・・・・つぎの記事はこちらから
カテゴリー:リレー・エッセイ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)