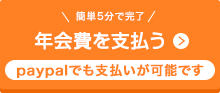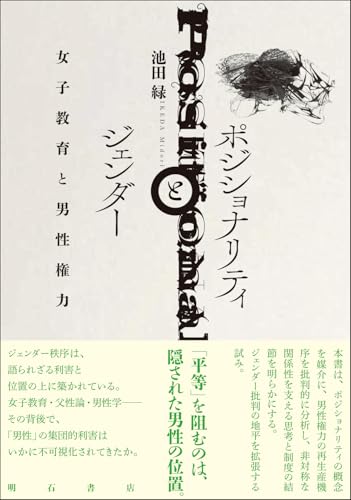イラスト:田中サトミ
東京藝大で大吉原展が5月19日まで開催された。開催前から物議を醸していたが、自分の目で見ないことにはモノをいうのもよくないと思い、控えていた。先日ようやく会場へ足を運んだ。肩透かしを食らった。
冒頭に「本展は女性の人権侵害を認めません」と宣言があるが、「本展」が認めないだけでなく、誰の人権であれ、人権侵害は認めてはならない。その女性の人権侵害を商売にした巨大な性産業が吉原という遊郭だ。展示には歌麿、北斎、英泉などの浮世絵版画ばかりか、それをプロデュースした版元の蔦屋重三郎の紹介まであるのに、それらの浮世絵と地続きの春画が1点も出てこない。このきらびやかな光景の背後に、セックスという労働があるというのに。(もちろん春画の性表現がリアルを反映しているわけではないことには、注意が必要だ)
揚屋の緻密な模型やお金をかけたCGが吉原を再現するが、そこにあるのは遊客の視線ばかり。この狭い空間に3千人の遊女が閉じこめられていたが、その数倍の数でたむろしたであろう遊客の姿は風景としか描かれない。この男たちが、セックスしたさに舟や籠ではるばるやってきたと思えばキモチ悪い。編み笠や頬被りで顔を隠しているのは、後ろめたさがあったからだろうか。
出てくるのは遊女の姿ばかり、というのは視線の主が男だからだ。表の顔の裏にある、遊女の暮らしの実態は描かれない。客の前で飲食を禁じられた遊女が粗食に甘んじたことや、楼主による折檻や打擲、苛酷なつとめや性病などは描かれない。正月の初衣装や流行の源になった華麗な装束も、すべて遊女の掛かりとなって借金をふくらませ、苦界から抜けだせなくなる仕組みの説明もない。わずかに放火事件で抱え主に抗議した遊女たちが厳しい制裁を受けたことが述べられるだけだ。ロマンスの成就として美化される「身請け」も、実質は奴隷の売買と同じ、逃げることも逆らうことも許されない。最高位の太夫の供養は出てきても、死んだ女郎を弔いもせずに投げ込んだ投げ込み寺こと浄閑寺は出てこない。吉原の光の部分ばかりが登場して、闇はないことにされる。これではまるで隠蔽と粉飾の展示だ。
これに比べれば国立歴史民俗博物館で開催された『性差(ジェンダー)の日本史』が扱った江戸時代の遊郭展示は、はるかに目配りが行き届いていた。遊女の「奉公」についての契約書の展示があり、契約者は親、奉公先で何があっても文句は言いませんとある。契約の形はとっているが、実質は人身売買である。また遊客の支払いや、大店が奉公人を身分に応じて吉原に送り出すなど、まるで従業員の性の管理のような実態を示す文書もあった。
東京の名所巡り観光バス、はとバスの巡行路にはかつて吉原が含まれていた。日本が誇る伝統文化と言いつのる関係者もいたが、抗議を受けてなくなった。吉原は日本の伝統の恥部でもある。光を示すなら、闇も同時に示すべきだろう。
美術の展示に政治を持ちこむな、という人たちがいる。だが政治に無縁な美術はない。今回の大吉原展は、みごとに「脱ジェンダー化の政治」を実践したものだ。
「朝日新聞」5月21日付け北陸版「北陸六味」を許可を得て転載(一部改訂)。
朝日新聞社に無断で転載することを禁じる(承諾番号18-5999)
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)