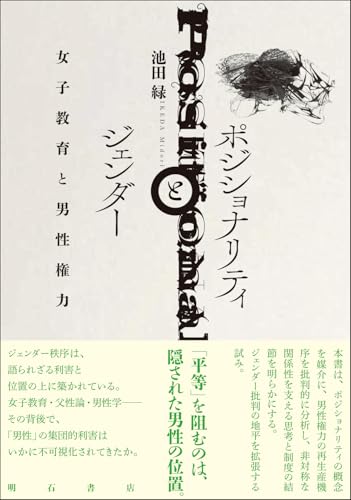2011.08.03 Wed
 そんなことにこだわっている場合じゃない。とにかく今は非常事態なのだから。
そんなことにこだわっている場合じゃない。とにかく今は非常事態なのだから。
そんな声が聞こえてくる。でも、そうやって小さな違和感にフタをして、あとで落ち着いてから話せばいいという「後回し」を、いろんな所で、何回もやってきた気がする。
3・11以降、脱原発デモやエネルギーシフトパレード、国会議員会館での院内集会や交渉に行って、あるいはツイッターやネットの情報を読んでいて、そしてマスコミ報道、政府や関係機関の対応をみていて、感じてしまう違和感。それは「母」の使われ方だ。
まずは、私が原子力発電に反対しなければと思った一九八〇年前後、心に響いた文章を紹介したい。
「女とは、男とは、ときめつけることを私は好まない。女とて、男とて、よりよく生きたいと希っているだろう。しかし、弱いもの、小さいものの生命を守るゆえの女の遅い歩みを、差別の対象にしてきた男たちへの不信がある。(略)
原子力発電が動いている以上、そこから放出される放射能による被害は、いつ、どこに及ぶかわからない。私たちすべてが被害者たりうるが、原発関連施設で働いている人々や、建設現地の人々は、より深刻に被害を受けるだろう。現にそこで働いている人々の放射能被曝は、年々増えている。女たちを差別してきた男たちは、その人々のいたみを及ばぬながらもわかち合おうとしないで、自分たちとは別の人々だとしてしまうのではなかろうか。原子力発電は新しい差別構造を生みだすし、すでに差別の事実の上に成り立っている。(略)
男たちは、子育てというもっとも手のかかることを女たちに任せてきた。また後始末のような、やり映えのしないことをも女たちの仕事とした。やさしさを欠いた仕業を積み重ねながら、男たちは前へ前へと進めばよかったのである。原子力発電に伴う危険な廃棄物の完全な処理方法はないのに、男たちはそのことに対して切迫感がないのではなかろうか。後始末のことを真剣に考える性向を彼らは失ってしまっている。」
これは、中野耕さん「失った朝の光——原発社会のもたらす暮らしを問いなおす」という文章で、一九七九年四月十五日発行の『反原発事典(2)[反]原子力文明篇』(現代書館)に収められている。一部しか引用できなくて残念だが、都市で電気を使う生活者の立場から、原発のさまざまな問題点を明らかにしている。ここでの「女」「男」は象徴的な意味でもある(性別二元論という批判もありうるが)。でも、実際の性別とも重なっている。東京の反原発運動で私はすてきで面白い女たちに出会った。それまでの男性中心、上意下達スタイルとは違う雰囲気が感じられた。
大阪では、一九七八年に「なにがなんでも原発に反対する女たちのグループ」ができ、論理的説明だけでなく感覚的な思いつきや感情を大切にする井戸端ふう会議やゲリラシアターなどの行動をしていた。この会のパンフレットには、「運動の場から切りすてられてきた女だからこそ、そして男社会の中では男志向をもち、自らの・女・を否定してきた女だからこそ、・女と反原発・なのです」と書かれている。(同会編パンフレット『女と反原発』一九七九年)
私は「女」の立場からのこうした主張に、とても共感した。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.その後、一九八六年チェルノブイリ原発事故があり、甘藷珠恵子さんの『まだ、まにあうのなら——私の書いた一番長い手紙』(地湧社、一九八七年)が広く読まれた。
ここでは、「母」が鍵になっている。
「私たち母親は、子どもの健やかな成長を何より、何より願います。その生命を脅かすものを赦すことができません。……子どもたちの生命を守るために私はハッキリと『原発はいらない!』と声に出して言い、そのための行動をしたいと思います。それが原発のある世に子どもを産んだ母親の、子どもに対する責任だと思っています」
一九八八年二月、伊方原発での出力調整実験の日には、甘藷さんの冊子の広がりに呼応するように、多くの人々が集まったという(当時、子どもだった俳優いしだ壱成さんがこの行動に参加した経験を3・11直前にブログに書き、話題になった)。
当時の「盛り上がり」に対して、「母として反対する」というトーンになじめない、「母であろうがなかろうが、女であれ男であれ、一人の人間として原発に反対したい」という意見もあった。同時に、放射能の影響で「奇形が生まれる」という表現に危機感を持つ障害者もいた。堤愛子さんはこう書いている。
「『お化け』であれ『巨大』であれ、タンポポの『奇形』を強調することによって放射能汚染の恐怖をあおり立てることに、私は言いようのない苛立ちとたまらなさを感じる。(略)『障害者』に対する恐怖感や差別感、『自分はあんなふうにはなりたくない』という意識が人々の心にしみついていたからこそ(また母性が強調されている時代だからこそ)、本書[引用者注:『まだ、まにあうのなら』]はこれほど多くの人々の共感を得、広がっていったと思うのは、うがった見方だろうか。(略)かけがえのない生命をおびやかすものに対しては、私も断固反対する。公害然り、原発然り。そして『障害者はかわいそう』『障害児なんて産みたくない』とする考え方や、『障害』を恐怖の象徴に仕立てようとする人々の意識も、『障害』をもつ人々のかけがえのない生命と人生をおびやかすものとして、やはり『反対!!』といいつづけていくつもりだ」(堤愛子「ミュータントからの手紙」『クリティーク』12号、一九八八年、青弓社より)
反原発運動をしていた人のなかにも、こういう意見がある。伊藤書佳さんは、
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.「ワタシは、障害のある子が生まれるから、かわいそうだから原発を止めなくちゃ、というふうにははっきりいって思えない。障害を持っている人のことを不幸だとは思わないし、障害のない人なんていないんじゃないかとも思う。(略)だけど、人のつくった放射能によって、遺伝子が傷つけられたりして、障害をもった子が多くなったり少なくなるのは、話がべつ。そういうことで自然のバランスがくずれるっていうのは大問題だ。」
と『超ウルトラ原発子ども』(ジャパンマシニスト社、一九八九年発行)で書いている。当時、「ワタシが学校で感じた苦しさと原発が同じなんじゃないか」と考えるようになり、小学生から十代までの原発を止めたいと思う子どもたちに話を聞いてまとめた本だ。こうも書いている。
「確かに、頭が二つある牛や巨大なタンポポには悲惨な事実のショックがある。ビックリしてコワくなる。でも、ショックな事っていうのはそれだけでは持続する力がないのかもしれない。だって、ショックな事は忘れたい、忘れようって心がはたらくし、自分とは関係なくあって欲しいって気持ちが強くなると思うんだ。/よく小学生とかのとき、夏になると戦争についての話や広島や長崎の原爆が落ちたあとの子どもや町のつらい写真とか見せられて、目をおおったりゾーッとした。戦争はコワイ、イヤダと思うけど、なんだか自分の毎日とは結びつかなくてむしろ●私は平和なときに生まれてよかった●なんて満足というか安心したりしていつの間にか忘れた。まるで、コワイ映画を見てしまったときのように。」(同上)
それから二〇年、事故が現実のものとなってしまった。
文部科学省に抗議にきた人たちをさして、マスコミは「福島のお母さんたち」と報道する。それは事実だ。でも、お父さんもいるのに、とすぐツッコミを入れたくなる。
何よりひっかかるのは、3・11以降とくに、母といえば、子どもを第一に考え、自分を犠牲にすることも厭わず必死に努力、健気にがんばるというイメージが流布したこと。現実にはいろんな母親がいるし、そもそも母という属性とは別に、さまざまな仕事をしていたり家事専業だったり、家族や子どもとの関わりも雑多であるにもかかわらず、何か一つの鋳型に入れた感じになる。そして母性愛とセットのようにして出てくるのが「難しいことはわからない、無知な母親」というイメージなのだ。
たとえば、「妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの放射能へのご心配にお答します」という厚生労働省の冊子(二〇一一年四月一日時点の情報や考え方をもとに作成)を見ると、その無内容さに驚く。母親には(国民にも、だけど)数値など詳しく説明してもわからないだろうから、安心ですと言ってあげればパニックにならなくていい、母親が不安になると子どもの精神にも悪影響をあたえる、おかあさんは笑顔で子どもに接していればいい、という内容。データや根拠はまったく示すことなく、「安全です。心配しすぎる必要はありません」をただただ繰り返している。
一方で、原発に疑問をもち、放射能の影響について危険性を知らせようとする人が、「世のお母さんにもわかるように、出来るだけ平易に書いたつもり」と自分の文章を紹介していたりして、アレレ? と思う。
ママはニコニコしているのが一番大事。ママが不安になったり怒ったり、デモをする過激派になったりしたら、子どもがかわいそう、という意見が、原発に賛成の立場からも反対の立場からも聞こえてくる。
母親である人自身の「難しいことはわかりません。ただ子どもを守りたいだけなんです」という発言もよく聞く。ある種、枕詞のようになっているようだし、「ただの普通の母親なんです」と言い訳しないと、危険な「活動家」と思われて、マスコミも近所の人も耳を貸してくれないから言わざるをえない。昔からよく聞く、PTAの用事なら外出しても「主人」や義父母が嫌な顔をしないというのと似ているかも。
あるいは母親蔑視に対する皮肉として、「どうせ私は」と愚かで何も知らない母を演じている人もいるだろう。母の仮面をかぶりながら、中から母を解体していく戦術もアリだ。
一方、母と子という形でアピールするほうがマスコミや一般の人々に受けいれられる、ビジュアル的にも母と子は「絵になる」という感覚で積極的に活用する立場もある。
みんなが、いろんな表現をすればいいと思う。
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.とはいえ、「子どものため」「母として」なんて、どっちの立場にも転がりうる。かつて「朝まで生テレビ」に出た原発賛成派のおばさんは「わたしたちは、東京に住んでいる娘や息子や孫が使う電気のためなら、ここに原子力発電所が建ってもいい、それがみんなの役に立つなら、そういう気持ちなんです」(『超ウルトラ原発子ども』より)といったそうだ。
そして「母」はすごい、偉大だと持ち上げておきながら、「感情的」「論理的ではない」と切り捨てたりもする。それは「女」に対しても同じだ。「お母さんたちには、この程度でいいでしょう」という政府や関係機関の馬鹿にした態度には、しっかり抗議したい。
冒頭で紹介した中野耕さんの文章にある、子育てや後始末を担ってきた「女」としてと、「母」とでは、どこが違うのかも考えたい。
さて、先の厚生労働省のパンフは、妊娠中の女性に対して「避難指示や屋内退避指示が出ているエリア外で放射線がおなかの中の赤ちゃんに影響をおよぼすことは、まず、考えられません。また、国や自治体から指示がない限りは、妊娠中だからという理由で特別な対処が必要、ということはありません」と説明している。
チェルノブイリのあと、人工妊娠中絶が増えた地域や国があったとの報告があるが、日本ではどうなっていくのか。
郡山市の一歳児のいる女性は「もう赤ちゃんは産めないと思う。こわくて産めない。そういう人はまわりにもたくさんいる。過剰反応っていわれるけど」と話していた。(ちなみに彼女は、5・23抗議行動を夫がネットで知り新幹線でかけつけた。ちょうど文部科学省に入っていった山下俊一らしき人物に向かって「人殺し!」と涙ながらに叫び「あの男、安全について話してない、安心と言っただけって開き直ってんだよ」と怒っていた。山下氏は福島県の放射線健康リスク管理アドバイザー。長崎での被爆二世で、親たちは汚染された水を飲んで復興してくれた、とも語る)
少子化対策に躍起になっていたが、この国は●子どもを安心して産み育てられる社会●ではなくなってしまった。私たちに何ができるのか。たとえば次のような呼びかけを読んで、私の頭は混乱する。
「妊婦が被曝すると妊娠初期で死産、中期で奇形児出産の可能性、後期で発達障害の可能性が高まるというデータがあります。被災地の助産師によると、放射性物質の食物への影響を心配する妊婦も増えているとのことです。特に、葉物野菜の欠乏が、妊婦と胎児の栄養状態に影響を与えつつあります。」(被災地の妊婦さんに野菜を届けるプロジェクト、ホームページより)
この取り組みに文句をつけたいのでは全くない。それぞれができることをしながら、でも何に違和感をもったのか、その背後には何があるのか、シコシコと続いてきた反原発運動での過去の議論も再生しながら、話しあえる雰囲気や場をつくっていけたらと思うのだ。ココロは反原発と思うばかりで、いつのまにか呑みこまれていた悔しさをこめて。
[大橋由香子(おおはし・ゆかこ)フリーライター・編集者。「SOSHIREN 女(わたし)のからだから」メンバー。インパクション誌編集委員]
初出:インパクション一八〇号 特集「震災を克服し原発に抗う」2011年6月25日刊、1500円+税
カテゴリー:脱原発に向けた動き
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)