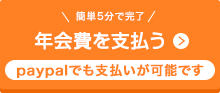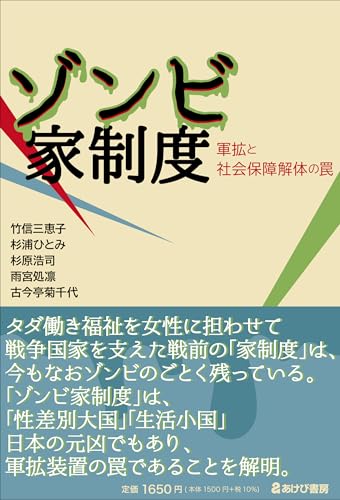「何でママはPTAに入らないの?」では、任意加入のPTAに非加入の親子に対する村八分が起きても、救済の手立てがないことを書いています。
そのなかで、一つの解決策としてPTAをNPOにするということを提案しました。
組織体を変えると、行政が立ち入れる組織になります。
行政に動いてもらおうと思っても動いてもらえない、という課題に対しては対処されます。
しかし、本質的にこれだけでは済まされないことも多いのです。
本書では踏み込んでいないのですが、PTAがなくてもまわれる教育制度に革新する、のも一つの方法です。
しかし、現状は高齢者社会であり、教員の拡充がどこまでできるかは疑問があります。
そこで外国人をいれる、ということもあるのですがその議論の前になされるべく課題があるのです。
それは、地域の相互自助の仕組みをどう機能させるか、です。高齢化等で形骸化してしまっている町内会も増えています。それ自体は悪いことではありませんが、大規模災害が起きたとき相互自助が機能していれば多くの命を救い、様々な社会問題の解決にも寄与することは紛れもない事実です。
会社など労使関係においては、斡旋等すでに話し合いによる解決方法が導入されつつあります。とはいえ、圧倒的なパワーの差がある分、なかなかパワハラはなくなりません。
これと同じことが、地域の長が会長を務めるPTAや町内会にもあてはまるのではないでしょうか。
それとは別に、地方分権を進めればよい、という意見もあります。これも少し考える余地があります。
なぜなら、これらの課題は地域の課題をすべて行政に移譲してしまったがために起こってしまっていることでもあるからです。
ではどうすればよいか。
行き着くところはやはり、機能する地域の相互自助をどう導くかです。
よく言われる、公共圏と私圏ではなく、その狭間の共圏存在がこうした調整機能を持てばよいのです。
防災地域作りなどを含めそのあり方が議論され、いろんな地域でPTA活動内容を選択できる状況をつくる必要があります。
共圏というお互いフラットな関係で相互の話し合いで決められる場があり、相互自助が実現できるのであれば、それがPTAや町内会の役割を果たすことができます。
PTAに限れば、任意加入団体という現在の法的枠組みが危ういために村八分等が起り、親子を追い詰め、「こどもが教育を受ける権利」が脅かされていることが問題です。
これを改善するために、何ができるのかについてまだまだ成熟された議論がなされていません。
悲しいかな、「地域差」があるのです。このあり方についてその地域にあった選択ができるように、まずは選択肢の提供から始め、その上で、適切な運用ができるよう十分議論される必要があります。
(共著者 恵史あい)
本記事に関連する記事はこちらから
2016.10.28 Fri
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)