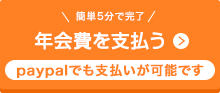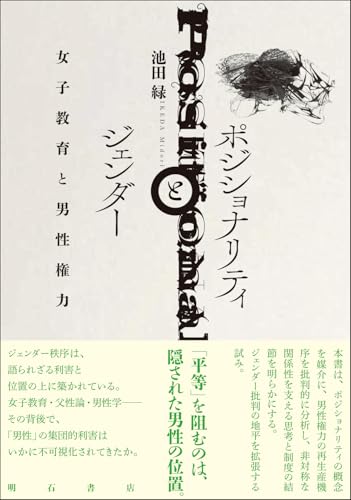韓国女性学会40周年記念大会スピーチ
「韓国女性学会40周年を振り返って」
女性学会創立40周年を心ゆくまで祝ってみようと思います。揺り動かされている女性家族部の地位を考えると、力強く歩みを進めている女性学会は本当に頼もしいです。
約40年前、冴えないネクタイ部隊(ホワイトカラー男性)と過ごすのがつらい時は、勤めていた大学の隣りにある女子大学のキャンパスに駆け込みました。 社会学科のチョウ・ヒョン教授室を出入りしながら「もう一つの文化」(女性運動団体)を作り、そこでは女性学関連のニュースを誰よりも早く聞けました。 政治的には非常に暗い時代でしたが、国家経済は大きく成長し、「息子・娘を差別せず、二人だけ産んでよく育てよう」という人口政策によって、娘たちが大量に大学に入学してくる時でした。彼女らが社会に出て、女性の声を上げ始めた時期でした。
1985年創立第1回学術発表会のテーマは「韓国女性学の普遍性と特殊性-宗教に現れた女性観」でした。宗教の家父長性に対する議論を始め、男女平等に対する新しい認識の場が開かれました。明晰で賢く、威風堂々とした素敵な女性の先輩学者たちに会し、心強かった記憶があります。
開会のあいさつで、尹厚淨(ユン・フジョン)会長は、女性の問題とは、誰でも人間らしく生きることのできる「人間化」を目指すことだと述べました。「人は誰でも人間らしく生きるため、恵みと権利を与えられており、この社会のどの階層の誰しもが、不当に扱われたり、人間らしく生きられない場合があったら、それは改善していかなければなりません。 そういう意味では、平等な機会の下、お互いに依存し、協力し合う社会にならなければならないのではないでしょうか。女性問題を考えるとき、最近の女性の70~80%は、家庭内で過ごすことに満足していません。しかし、私たちの社会構造や家族制度は、女性が仕事をすることを許しません。人間らしく生きるという私たちの価値観や行動が正しいとするならば、それを阻害する要因となる社会構造や制度を解決し、打開していかなければなりません」と当時としては、体制に亀裂を入れようとする壮大な宣言でした。
40年経った今、尹厚淨会長の平等な機会への願いは一定の成果があげたようです。女子大生の社会進出は年々進み、「アルファガール」というニックネームが生まれ、臆病になった男性が反撃してくるほどです。しかし、お互いに依存し、協力する社会はできていないようです。 たぶん、その「人間化」という言葉が問題なのでしょう。 延世大学で学生を教えていた頃、私と同僚たちが開設した科目名は「男女平等と人間化」でした。素敵な科目名だと考えていましたが、今では違和感があります。確かに、これまで女性は社会構成員としての権利をかなり獲得できましたが、競争と敵対に基づく社会体制を変えるには力不足だったのです。この場で、告白しますが、私は韓国女性学会の創立から約10年後の1996年に「女性学会が面白くないからもう来ない」と言って騒ぎを起こしたのですが、それは女性学が既存の体制に亀裂を入れないで「割り込み」だけに集中しているという考えからでした。高等教育を受けた女性たちは、当時、押し寄せてきた新自由主義の突風に、適応するのに精一杯だったようです。
尹厚淨会長は、3千年余りの間、女性問題があったが、数百年前だけでも女性たちが、今日のように目覚めていたらよかったと残念がるような話もされています。「家父長制3千年」がずっと頭の中にあったようです。宗教学者カレン・アームストロング(Karen Armstrong)が自著『大変革(The Great Transformation)』でいう「軸の時代」を参考にすると、巨大宗教が出現した紀元前800~300年頃に唯一神を信じる奴隷制社会が定着します。万物に宿る魂(アニミズム)を追い出し、人間が絶叫すればいつも現れていた神(シャーマニズム)も消えます。唯一神の名の下に、中世の絶対王権を庇護し、家父長制が強化された時期です。 その後、人間は厄介な神を殺し、その座に男性的な技術と資本を座らせます。かつて誰もが命を懸けて守ろうとしていた民主主義は、高度な監視技術と資本の力によって崩壊し、国家は暴力組織に転落します。自分たちが生きている生物学的な基盤を息をのむような速度で破壊した種は「人類」であり、彼らが台無しにした時代を私たちは「人新世(anthropocene)」と呼び始めました。 私は女性学研究者がこの分野の研究を本格的に始めるべきだと思います。
フェミニスト作家のマーガレット・アトウッドは「人間の絶滅は破滅ではない、終末を迎えたのは人間ではないか」と語ります。人間であることが恥ずかしくなる時代になりました。ですから、創立から40年を経たこの場で、私たちは「人間化」ではなく「脱人間化」を話します。植物、動物、鉱物、機械を含め、地球上に存在する多種多様な存在と関わりを持ち始めます。ダナ・ハラウェイ(Donna Haraway)は「糸編み遊び(string figure)」を勧めます。 不安や戦闘の代わりに、関係性の形成のための比喩、共鳴するための知識を生産しようというのです。自己の能力と限界を認識し、地球上の一つの生命体として生きるための局所的な知識を生み出す「謙虚な目撃者」として。フェミニズム理論家、哲学者のロージー・ブライドッティ(Rosi Braidotti)も、男性のように闘わないよう、呼びかけています。「フェミニズム文化戦争はアメリカに置いてきなさい」と言いながら、飛び立つことを勧めています。「巻き込まれず(disengaging)、距離を置き(distancing)、デトックス(detoxing)」しましょうと話しています。
イーロン・マスクは地球を離れるでしょうが、私たちは地球を離れません。その代わり、人新世、気候危機、ケアについて勉強しています。拡散の欲望ではなく、回復力について話します。私たちがアナ・チン(Anna Lowenhaupt Tsing)の本を読むのは、原爆で破壊された廃墟の中で育った松茸に対する話を知るためです。固定された主体などありません。相互作用の中で結ばれている関係があるだけであり、世代から世代へと続く生成消滅の生命が互いにつながり、支え合いながら生きています。地球生活者の共同体が増え、荒廃した土地が緑化しています。「女性環境連帯」(エコフェミニズムの団体)の研究所「月と木」から、『私たちは地球を離れない』という本が出版されました。この本が多くの女性の心を動かすことを願っています。1970年代の第2次大衆フェミニズム運動は、書店を中心に燃え上がっていたことを覚えています。同じようなことが再び起こることを願っています。だから、次の世代が地球の一員として、それぞれの生命の花を咲かせられることを願っています。

恥ずかしさを知らない人間であることを恥ずかしがっていた朴婉緒(パク・ワンソ)先生のことを思い浮かべながら、多くのフェミニストの先輩と後輩を思い浮かべます。そして、新しい世代のフェミニストを迎えながら、女性学会40周年を心から祝福します。
2024年6月10日 趙韓 恵浄(チョハン・へジョン)
韓国女性学会40周年記念大会 2024年6月15日開催
****************************************************************************************
趙韓 恵浄(チョハン・へジョン)
文化人類学者、フェミニスト。ソウルの延世大学名誉教授。初期の研究は韓国近代史におけるジェンダー研究に焦点を当てたものであり、現在の関心と研究は、現代韓国のグローバル/ローカル、ポストコロニアル文脈における若者文化とモダニティの分野である。
著書に『韓国の女と男』(1988年)、『ポストコロニアル時代のテクストを読む、生活を読む』全3巻(1992年、1994年)、『学校を拒む子ども、子どもを拒む社会』(1996年)、『反省的近代とフェミニズム』(1998年)、『学校を探す子ども、子どもを探す社会』(2000年)、『また、町-危険社会で生き残る』(2007年)、『教室が戻った』(2009年)、『自助共助公助-友情と歓待の町』(2014年)、『努力の裏切り』(2016年)。『羨望国の時間』(2018年) など。いずれも韓国語。
日本語訳書に『韓国社会とジェンダー』(2002年、法政大学出版局)、『ことばは届くか―韓日フェミニスト往復書簡』(2004年、岩波書店、上野千鶴子との共著)。
担当授業はジェンダーと社会、文化人類学、ジェンダーと社会、「グローバル化する世界の文化人類学」、「カルチュラル・スタディーズの課題」、「ネットワーク社会の文化とエコロジー・プロジェクト」、「ポスト資本主義政治における公共空間の創造」など。10代の若者のためのオルタナティブ教育・文化スタジオ「ハジャ・センター(SYFAC,Seoul Youth Factory for Alternative Culture) 」の創設ディレクター。
****************************************************************************************
韓国語オリジナル原稿:https://wan.or.jp/article/show/11317
日本語訳:チョウ スンミ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)