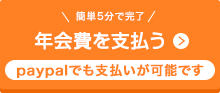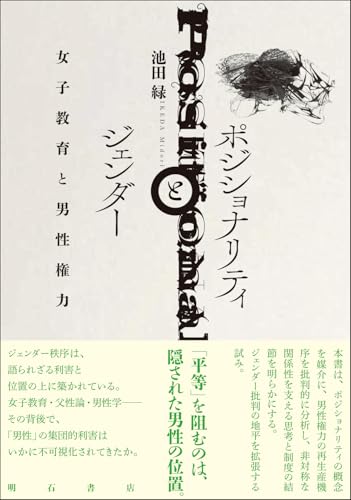WANAC第二期 受講レポート オリエンテーション回
新年度の忙しさがひと段落したかなというとき、WANフェミニズム塾アドバンスコースが始まりました。たまたま上野千鶴子さんの講演を調べるためにWANのWEBサイトにアクセスしていたのが3月の上旬。締め切りまでわずか一週間という期間の制限で焦りがあるなか、なんとか志望動機書と研究計画書を書き、応募にこぎ着けました。ここまで短期間での研究計画書を書いたことはなかったものの、この一年の間に温めていた考えが、キーボードを打つ音とともに、言葉としてスクリーン上にすらすらと映し出されました。
私自身、大学院に所属しているものの、フェミニズムやジェンダーについての専攻ではありません。しかし、学部時代にその分野の当事者卒業研究を行なっていたので、その問題を「誰かに伝えたい」ということは胸に秘めていました。ジェンダー・セクシュアリティ分野の研究を行いたくとも、大学院の専攻の枠の中では、得た知識発展させて外に出す・伝えるという機会がなかったのです。つまりは、このような専門知識を学ぶ=インプットすることができ、さらには飲み込んだ知識を外に伝える=アウトプットする、このような機会を心から待ち望んでいたのです。
審査通過することは難しいと悲観的に考えていたなか、送られてきたメールには「あなたを採用いたします」という言葉が。それを見たときは安堵感を通り越し、目元が潤んだことを覚えています。
メールを受け取った数日後にはオンラインでのオリエンテーションが開催され、そこで上野先生をはじめとする運営にかかわるWANの方々と、今年度一年を通して共に学ぶメンバーとの初顔合わせの場となりました。流れとしては上野先生から最初に年間を通してのゼミの説明があり、運営サポート役の「いきもの係」の方々からオンライン・ゼミについての補足や具体的な運営方法への説明がありました。上野先生から「うえのゼミでは」という言葉が発せられたとき、私もその一員になったのだと、嬉しさが込み上げてきました。
その後はゼミメンバー各自の自己紹介タイム。大学院のゼミや授業では、おのおのの研究テーマについて言うことが定石ですが、このゼミでは「呼ばれたい名前」と、このゼミを志望したきっかけを1分という限られた時間で発言することとなりました。きっかけ・志望動機はひとそれぞれさまざま。今回のアドバンスコースの副題でもある上野先生の書籍『情報生産者になる』を読み、論文のエッセンスとしたことがきっかけになったと言う人は複数いました。私は学部時代には社会学のゼミに所属しており、質的研究方法の教科書として同書が使われ、熟読したことを思い出しました。別々の場所に居ながら同じようにこの書籍を読み、論文を書くというクリエイティブな行為を行なった人たちが、時間を経てここに集まるなんて。とても面白いことではないでしょうか。
また、「自分が呼ばれたい名前」を自ら指定できる制度があります。姓か名のどちらかで指定する人もいれば、ニックネームを指定する人、また、苗字が変わったことによる姓へのアイデンティティの無さに言及する人、逆に普遍的な名であるために姓で呼んでほしいという人も。私自身は幼い頃に父母が離婚し、自らの意思ではなく強制的に姓を変更させられた経験があります。生まれたときには父方の若本という姓に帰属していたにもかかわらず、その後の両親の離婚により母方姓に変更を強いられました。幼心にも、当時は姓が変わることに強い違和感を持っていたことを覚えており、今でも自分の姓にアイデンティティを見出すことはできません。なので、私は下の名前で呼ばれることを希望しました。社会を生きる中で今の姓を名乗ることが「当たり前」になっていて気づかなくなってしまった自分がいましたが、日常で強制的に苗字で呼ばれるという慣習に対し、少し問題意識を向けることができる良いシステムかもしれませんね。
さて、参加者以外でこの文を読んでいる方は、参加メンバーの属性が気になっている方が多いのではないでしょうか。ジェンダー比や年齢で多少の「傾向」はあるものの、かなり多様なバックグラウンドを持つメンバー構成だと感じました。大学の学部で勉学に勤しんでいる人もいれば、バリバリに会社で働いている人も、WANのフェミニズム入門講座を受けた人も、博士課程の人も、海外のルーツを持つも。ほんとうに多様な集まりです。同じような属性ばかりを選り好みして集められた集団では、考えが凝り固まってしまいますからね。
また、多くの方が仕事と学業を同時進行で行なっており、学び直しを実践している人たちがこんなにもいるのかと、小さく感動しました。私自身は高校中退組で、仕事を経験した後に大学の学部に入り、そのまま大学院に進学したという、少し「普通」のルートからは外れた経験をしています。こんなに学問が楽しいことだとは、ティーンエイジャーである現役の学生のときは考えられなかったでしょう。今は学びの面白さの虜になってしまっています。ルートがそれぞれ違えども、ここに集まっているということは学びたいという姿勢を共有できる有志であることは、間違いありません。
まだゼミは本格的には始まっていませんが、このゼミからドロップアウトしてしまうのではないかと、不安を抱くメンバーも多数見られました。確かに、仕事や学業をこなしながら、このWANフェミニズム塾アドバンスコースを受講することはなかなか大変だと思います。加えて知識の差があり、ゼミ全体のレベルについていけるか不安と感じる人もいるでしょう。しかし、これだけ多種多様なメンバーが揃ったのです。お互いがお互いを補い合うピアの関係を活用し、「共助」の関係ができるようになると感じました。いまこの文章を書いているときにも、ゼミの運営方法をどうしようかという話が共有ツール上で話されています。私もゼミの一員として、お互いを助け合う役割を積極的に担っていきたいと、考えを抱いています。
次回はおのおのが研究計画を発表する回です。どのような回になるのでしょうか。ゼミメンバーみんなの研究計画を聞くことが、すでにもう楽しみでなりません。
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)