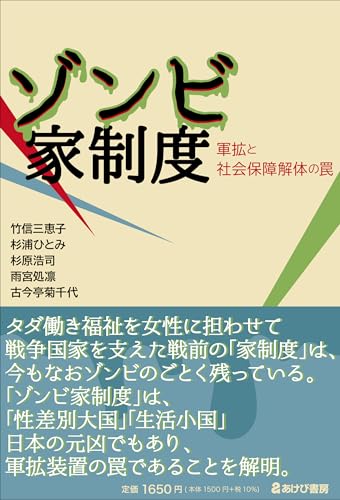views
1476
女が女に憧れる話 田丸 理砂
2009.05.26 Tue
「女が女に憧れる話」にめっぽう弱い。とはいえ、わたしがこれまで歩んできた文学研究者の道(?)の途上で、「女が女に憧れる話」に出逢うことはほとんどなかった。だからこそ、そういったものを読むと(たとえばドイツ語だけどラーエル・ファルンハーゲンとパウリーネ・ヴィーゼルの往復書簡が好き)、ああこういうのをわたしは待っていたという快感を覚える。
一方、文学は「男が男に憧れる話」で溢れている。教科書に載っていた夏目漱石の『こころ』だって、太宰治の『走れメロス』だって、身近なところでいえば(ドイツ文学に携わっているので)日本でも有名な『トニオ・クレーガー』だって、『デミアン』だってそうである。
今から思うと、わたしには昔から読書に女の快楽みたいなものを求める傾向があったのだと思う。2006年末、エレナー・エスティスの『百まいのドレス』(石井桃子訳、岩波書店)が50年ぶりに改訳されたと聞いて、わたしはとてもうれしかった。それを子ども時代に読んで忘れられずにいた。1944年に合州国で出版されたこの児童文学について、訳者石井桃子は、作者は「どこにでも、だれにでも起こりうる、人々のあいだの差別や、心の葛藤を」描いていると「あとがき」で述べている。けれどわたしにとっては『百まいのドレス』は「女の子が女の子に憧れる話」であったし、今回再読してみてもそうなのである。また表題にある「百まいのドレス」とは王子さまにお姫さまとして見出されるための小道具ではなく、女の子が女の子への憧れを示唆するものである点も秀逸である。
ところで『百まいのドレス』によって呼び起された感情は、けっして幼年時代を懐かしむという類いのものではない。最初に読んだときから、ゆうに30年以上経っているとはいえ、それは現在のわたしからも感覚的に少しも隔たってはいない。
同じような印象を角田光代の『対岸の彼女』にも覚えた。女同士の友情をこんなふうに描いたおとな向けの物語を読んだことがなかった、こんな小説が読みたかった。おとなになって、恋愛をして、結婚をして、子どもを持つと、少女時代の女友だちとのつながりを忘れるのだろうか。あるいはそのとき抱いたせつない思いを、若さゆえの遠い過去の出来事のように懐かしむのだろうか。いやそんなことはない。高校生の葵が、急に姿を消したナナコのことを思って泣くとき、大人になった葵と彼女の会社で働くようになる主婦の小夜子が互いにつながりを求め傷つくとき、彼女たちの感情はわたし(たち)にリアルに迫ってくる。
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)