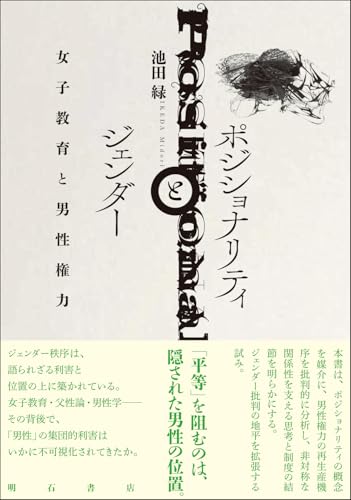2012.12.28 Fri
日本に未来があるのなら、被選挙権は先の長い人ダケ!にしてほしい・・と思うきょうこのごろ。 アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください. 『太陽の季節』を読んでみた。これぞ、そもそものマチガイのはじまりなわけで。 ところがどっこい。どうにもこうにも、じぶんの父親を思い出してしまったのだ。 石原慎太郎、昭和7年生まれ。『太陽の季節』は、当時一橋大に在籍していた彼が、慶応にいた弟(デビュー前)たち不良グループをモデルに書いたものといわれている。私の父親、昭和6年生まれ。一橋大に落ちて慶応大に上京した田舎の学生だった。 父によると、当時、大学といえば「国立大」をさし、早慶などの「私学」はだいぶ見劣りする学校だった。この小説は「国立大学」の高みにいる兄が、弟属する「私学」の文字通り下位の文化を綴ったものといえよう。 小説の〈K学園のハイスクール〉では高校生に賭麻雀が流行っている。父はよく、“ぼくらが慶応に入った数年で日吉の校舎のまわりの本屋がみなつぶれて雀荘に変わったんだ”、と自慢していたのを思い出した。 父は、戦争のただなかに育った。カッコいいのは海軍で、海軍にゆきたいと素直にあこがれながら、戦場そのものの 恐怖とは縁がないまま中学末年に終戦を迎えた。小説の主人公竜哉は、拳闘つまり殴り合いのスリルに熱中するのだが、ひたすら不敵にみられたがる気分に、父たち世代、兵隊になりそこねた軍国少年の鬱憤を感ずる。考えてみればしかし、いずれは徴兵されて弾があたるか逸れるか、確率的な将来をのみ与えられて少年時代を過ごした世代なのだ。それとギャンブルへの熱中は無関係でもあるまい。 しかし何よりこの小説に父を想起させたのは、少年たちの女性観・恋愛感だった。 〈大体彼等の内で恋などと言う言葉は、常に戯画的な意味合いでしか使われたことがない〉〈女は彼らにとって欠くことの出来ぬ装身具であった〉〈身を飾ろうと眼移りさすように、竜哉も新しい女を追っていたのだ〉 父はちなみに、東京の優良企業で順調に出世し、70年代、ウーマンリブにあおられた「自由な女たち」の部下に手当たり次第交渉をもちかけ、浮気を繰り返し、企業社会から脱落して失意の人生を送ることになる。 〈結局竜哉が女を追うのは、女を屠ること自体のためなのだ〉、このいいまわし。父の語るおんなの自慢話にそっくりで、ぞぉっとした。 この色事にまつわる異様に肩肘をはった「男の美学」も、つまりは明日をもしれぬ戦時において恋だの愛だのは論外である、といった兵隊の心境のパロディーなのかもしれない。 この美意識に突き動かされて父がセックスを求め、かつそれに応じた女性たちがいたというのは、おんな側にも「反抗」「性の解放」といった文脈があったからだ。小説の竜哉と英子にも、これと相似の同床異夢があるように思う。 とはいえこの小説が面白いのは、女性の処女性、純情さへの期待が全く描かれていないことだ。竜哉は英子の男性経験豊富さに圧倒され、それを恥じるがゆえ、彼女を尊敬してつきあい始める。逆に、英子が結婚を意識して純情初心なそぶりをみせだすや、言葉や態度で彼女をなぶりはじめる。そして、再び英子が世故たけた狡知をのぞかせると、愛情を戻していく。 竜哉に純情一途、彼しか目の中に入らない状態の英子を、〈女になった〉(※「女」にルビ)と侮蔑的に表現する。〈女になった〉英子は、やがて中絶に失敗し、御都合主義的に死んで物語が終わる。 しかしこれは、所謂女性憎悪、奔放な悪女に天罰を下して物語をとじようという、頑迷な秩序感覚なのだろうか。 竜哉は英子の、貞淑な妻にふさわしい女にみせたがる“カマトトぶり”をこそ軽蔑し、手に負えぬほど奔放なときの英子にこそ惚れていた。世間によくある恭順な〈女〉(※ルビ)らしいみぶりは憎悪しても、そこから漏れでる英子をこそ愛していた。 男と女は末永く睦まじく結び子を育てよ--。国やぶれて急にたちあらわれた「平和」、「家族愛」といった、それこそご都合主義な秩序感覚に欺瞞を感じ、その象徴として、英子と胎児はこの作家に「殺された」ようにも思う。 杵渕里果
カテゴリー:投稿エッセイ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)