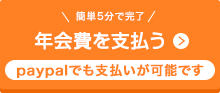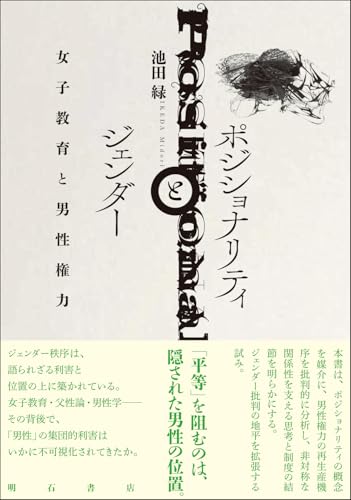【署名はこちらからお願いいたします!】
https://chng.it/F9sNGCntrw
セクシュアルハラスメントにより、精神障害を負った被害者の多くは、心身に不調を抱え、就業が困難になることに加え、通院による経済的負担が発生します。
国の補償制度である労災保険の認定基準は、セクハラ被害の実情に見合っておらず、補償を受けるハードルが未だ高い状況です。
◆精神障害の労災認定要件
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること ※セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷を評価します。
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと
セクシュアルハラスメントにおける被害者は、被害に遭った際の強いショック、職場での関係悪化を恐れることや自身の落ち度を責めてしまうことから、相談できずにやり過ごしてしまうことが多く、その対処として逃げる・抵抗することを選ぶよりも、良い関係を築こうと迎合することが多くあります。
厚生労働省のHP上でも、留意事項として以下の点が記載されています。
ア セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という。)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実はセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。
イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。
ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。
エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。
労働基準局 補償課.厚生労働省.”心理的負荷による精神障害の認定基準について”.令和5年9月1日 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html ,令和6年5月26日参照
被害当時に心身の不調があっても、自身の置かれた状況に対する混乱等から病院の受診に至っていない場合もあります。
被害が終わったかのように思えても、加害者からの接触や、被害時と同じような状況になる等のきっかけにより、強い心理的負荷を受け、精神障害を発病することがあります。
よって、厚生労働省で定められた労働災害認定基準については、遅発性の発病にも対応できるよう、6か月間の出来事における心理的負荷の強度を判定することが適正なのかを見直していただき、公平で現実的な対応策となることを求めます。
職場の人間関係において発生する不同意性交、不同意わいせつ等の性被害は、被害者の尊厳を傷つけるだけでなく、事を荒だてたくない、公にされたくない、報復が怖い、自分の落ち度を責められるのではないかといった二次的な影響も懸念され、被害者は問題を抱え込んだまま苦しむことになります。すぐに被害を自覚し、会社に相談して対策を依頼する、加害者への損害賠償を検討する等、被害者が抱えることになる負担は大きく、立ち向かうことができない人がほとんどです。
相談できるようになった被害者の心理的負担に寄り添い、その後の回復に向けた制度が平等に行き渡るよう、皆様のご支持を宜しくお願いいたします。
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)