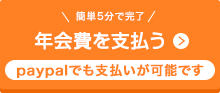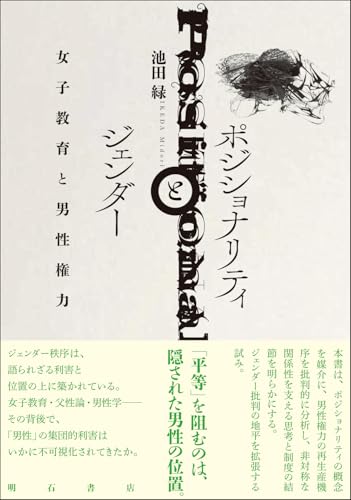6月1日、久しぶりに大阪のドーンセンターへゆく。
山家悠平著『遊廓のストライキ 女性たちの二十世紀・序説』(共和国、2015年)、『生き延びるための女性史 遊廓に響く<声>をたどって』(青土社、2023年)、青波杏(著者のペンネーム)の小説『楊花の歌』(集英社、2023年)を読んで以来、すっかりファンになってしまった山家悠平さんの著書の合評会に参加したくて、「日本女性学研究会」2024年6月例会に出かけた。
以前、山家悠平さんの二冊の本の書評をエッセイに書いたことがある。
「#わきまえない女」たちの反乱(旅は道草・133)
響きあう<声>をたどって(旅は道草・167)
午後からの会の前に天満橋界隈をぶらぶらと歩く。このあたりは小学校3年生から大学時代まで過ごした懐かしいところだ。1952年、大阪南部の農場で野山を駆け回っていた私。大阪府庁農林部に移った父といっしょに田舎から大都会へ引っ越してきた。

大川

大阪城
片町の官舎の裏を大川が流れている。川面をポンポン船が行き交っていた。宮本輝の『泥の川』に出てくるような水上生活をする一家が船上で洗濯物を干していた。川の向こうに大阪城がよく見えた。
京阪天満橋駅構内では靴磨きの少年がせっせと働き、橋の下の掘建小屋に住む男の子は近くの公衆便所へバケツで水を汲みにきていた。1950年代はじめは、戦後の混乱が、まだまだ続く時代だった。
時は流れても、川の流れは変わらない。川は時の流れを、ただじっと見つめていたのだろうか。何ごともなかったかのように、川は今も、ゆったりと流れていた。
ドーンセンターと同じ場所に昔、大手前会館があった。広い石段を上った先の会場に文人たちが講演にやってくる。文学好きの母は小学生の私を連れて聴きに行く。まだ20代だった瀬戸内晴美と少し年配の円地文子のお話。「お着物が、きれいだなあ」と、わけもわからず聴いていた。今東光や高橋圭三のお話も聴いた。
隣の大手前児童館には児童書が並んで、よく出かけては読んでいた。馬場町にあるNHK(BK)アナウンサーの泉田行夫が時々、やってきて、子どもたちにお話をしてくれた。泉田は後に児童劇団を立ち上げ、中山千夏や、いしだあゆみを育てたという。

大手前高校
大阪城の向かいの上町筋に、今はない大阪毎日会館があった。杉村春子率いる文学座の上演ホールだった。千秋楽の日、小学生の私に劇団の人から「鄭成功」で主役を演じた北村和夫に「花束をあげて」と頼まれて舞台に上がった。お花を手渡すと北村和夫が優しく頭を撫でてくれた。今、NHK朝ドラの再放送「ちゅらさん」(2001年)に北村和夫と丹阿弥谷津子が出演している。
毎日会館のすぐ南隣に大手前高校がある。西外堀のお堀端を歩いて通学していた。京阪天満橋駅近くの「ぼん繁」に同級生の男の子といっしょに、よく「お好み焼き」を食べに行ったこともあったっけ。今もまだ、お店はあるみたい。
1960年、安保闘争の時は大阪城広場に高校生も数名、集まってデモに出発。御堂筋をフランスデモで手をつなぎ、難波まで歩いたことを思い出す。そして6月15日、樺美智子さんの死を知った。
のんびり、ゆっくりと散策していたら、もうお昼だ。ドーンセンターでランチを、と思ったら1階のカフェが閉鎖になっていた。「おなかがすいたなあ」と思ったけど、合評会が、もうすぐ始まるので間に合わない。仕方ない。飲まず食わずで、持参の水筒のルイボスティのお茶を飲んで会場へ向かう。
書評会 <声>がひらく叙述の地平をみわたすために
なんだか久しぶりの大学の講義みたいな雰囲気だ。
企画担当の牧野良成さんが趣旨説明をする。
著者・山家悠平さんの「かの女/かれらの生はそこで途切れるが、その死は生き残ったひとによって伝えられる。そこでは、歴史とは、その土地に響いている<声>のようなものかもしれない」の文章を引いて、「その<声>は、『遊廓のストライキ』から『生き延びるための女性史』に至る10年間の時代の変化、たとえば、#MeTooや新型コロナウイルスのパンデミック、日韓の「慰安婦」問題をめぐる動きなどと響きあうところもあるはず。しかし、山家さんはこれらの状況にはあえて踏み込まず、あくまでも自らの経験を踏み越えぬよう、慎重に言葉を選んでいるように思う。その狙いはどういったもので、著者はこの響きあいをどのように描けると考えるのか?」と問いかける。
続いて著者の山家悠平さんから『生き延びるための女性史』が、できるまで/その後のことが語られる。
『生き延びるための女性史』は、「客観的な研究」を志すというよりも、書き手が聴きとった<声>を書き留める書法だとし、その手がかりとして、アーシュラ・K・ル=グウィンの「耳を傾けることは、反応ではなく、結びつくこと」であり、「<声>は語り手と、それに耳を傾ける人をつなぐものだ」という言葉に触発されながら、自ら言葉を紡ぎだしていったのだという。そして聴こえてくる<声>を、一般的で通りいっぺんの捉え方へと、まとめて書くことを極力抑え、当事者と書き手の相互作用の中で自らも変化していくことを含めて、響きあう<声>を丁寧に書き留めていきたいと語った。
次に松永健聖さんからのコメント。松永さんの研究テーマは、戦後の占領下、米兵たちを相手にセックスワークを行っていた「パンパン」と呼ばれた女性たちのこと。「パンパン」たちが行っていたセックスワークの内実は「性行為」のみではなく、ある種の「コミュニケーション」あるいは「ケアワーク」でもあったのではないか。それを「遊廓の女」たちに重ねてみたいと、山家さんの眼差しと記述への共感を示しながら語る。
山家さんに聞きたいこととして、「私娼」についての言及、そして娼妓たちの「移動」について。さらには「誰に、この<声>をつなぎたいと思うのか?」と直截に著者に問いかける。
森川麗華さんのコメントが続く。曾祖母が1940年代、国策で旧「満洲国」へ渡り、敗戦時、「残留」を余儀なくされて中国人と結婚。「中国残留婦人」としてのスティグマ(中国人との結婚を「満妻」として蔑まれたこと)や、敗戦時、13歳以下の子どもは「中国残留孤児」と呼ばれ、それなりの援護政策があったのに対して、13歳以上の女性たちには多くのハンディがあった。しかも日本政府の帰国援護政策においては男女で異なる対応の差があったことを、森川さんの報告を聴いて、歴史の理不尽な事実に気づかされた。
「中国残留婦人」4世として、森川さんは自分自身と「遊廓の女性」たちとの接点を探り、その問題意識を、どこまで「想像(あるいは創造)」することができるのかと、自らにも山家さんにも問いかけてみたいという。
その後、著者とコーディネーター、コメンテーター、会場の参加者との間で質疑応答が繰り返されていった。
うーん、重たい問題提起だなあ。言葉にするのが、ほんとに難しい問いや答えを、どのように言葉を紡いでいけばいいのか。問う側にも答える者にも、ひしひしと迫ってくる難問が続く。
山家さんの著書は、歴史研究でもあり、文学研究でもあることから、「歴史研究と文学研究との狭間から叙述の地平をみわたすには?」「ナラティブとは何か?」「インターセクショナリティの視点とは?」そして「誰に、どのように、この<声>をつないでいくのか?」などなど。
書いたものが、時には予想もしない方向に届くこともある。だから当事者の<声>への共感はどこまでも丁寧に。そのために、わからないことは、きちんと調べなければいけない。だが、どうしてもわからないことだって、ありうる。ならば「すべてを見る必要があるのか? 歴史の中の他者の沈黙を「空白」として描くこと。その「空白」は読み手の想像力をさらに働かせる契機になるのではないか」と、山家さんが現在、女性史研究者として、あるいは小説家として、「叙述の狭間」を生きる中から生み出されてきたと思われる「予見的」な発想が、最後に山家さん自身から語られた。
著者とコーディネーターとコメンテーター、そして参加者とのやりとりは、とても深くて誠実で、文学や歴史研究、学問に向き合う真摯な姿勢が、ひたひたと肌に伝わってくる。
「読む」こと、「聴く」ことに真っ直ぐに向き合い、書き手が、一方的に「伝える」のではなく、受け取る側が「どうとらえるか」を想像し、相手に、どう「伝わるか」を考え抜いて書いてゆく。「伝える」から「伝わる」へ。その先に何があるかは、どこまでも読み手の自由だ。
そんな「読む、聴く、書く、伝わる」を大切にしたいという思いが、会場に集う人々みんなに満ちあふれていて、「ああ、いい会だったな。参加してよかった」と心から、そう思った。
例会が終わり、おなかがすいていたこともすっかり忘れて、企画してくださったみなさんに「ありがとう」とお礼を込めて会場を後にして、久しぶりにゆっくり歩いた大阪・天満橋から、夕刻、帰途についた。
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)