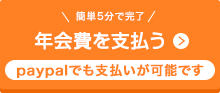「地方公共団体のための『性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増進に関する法律』を活用するための手引き」について
―多様な性的指向・ジェンダーアイデンティティの人が一緒に生きる社会の実現のために自治体は何ができるか ―
「性的指向及ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増進に関する法律」が成立・施行されて1年がたった。当会をはじめとした当事者たちが求めてきたものとはかなり違う内容で、しかも、議論の過程でばらかまかれた当事者への偏見や意図的な誤解ともいうべき負の副産物を残しながら辛くも成立した法律は、即日施行されたものの、法律に規定された「基本計画」や「指針」は、いまだ策定されていない。
賛否両論のなかで誕生した法律だが、性的指向・ジェンダーアイデンティティ(SOGI)の多様性を掲げた初めての法律であり、基本理念(法第3条)は「・・国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである・・」ことを明確にした。
法律の制定に至る過程で多くの当事者が傷つき苦しんだことを無駄にしないよう、法律の前進に活かし得る部分を使い尽くしてほしい。そんな願いから、LGBT法連合会は、2024年3月に、『「地方公共団体のための性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増進に関する法律」を活用するための手引き』を刊行した。
法の制定や改正が行われた際、関わった民間団体や有識者が解説本や資料を出すことは他の分野でも広く見られるが、本手引きも、「はじめに」に記載のように、理解増進法の制定過程に深く関わった経験を踏まえ、当事者・支援団体の立場から法の効果的な活用を提案するものである。
この手引きをつくるにあたっては、三浦まり上智大学教授や、中野麻美弁護士、内藤忍労働政策研究・研修機構副主任研究員をはじめとする有識者にもご参画いただいた。有識者とともに行った自治体などからのヒアリングで得た実践的な知見が本手引きの核となっている。
私たちは今回の策定過程を通じて、自治体の実践の拡がりと豊かさを実感した。この素晴らしい事例の数々を、少しでも多くの自治体に知ってもらいたいとの想いから、項目ごとに自治体の事例を示した。この多様性、豊富さを眺めるだけでも社会の着実な変化を感じられ、どのような施策を採るべきかということが自ずと見えてくるのではないだろうか。
一方、自治体に寄せられる住民意見や議会質問への対応の参考となるようQ&A形式で基礎的事項の解説を掲載した。本法は「LGBT理解増進法」と略されることがあるが、法の趣旨は、「LGBT」ではなく「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」を理解することである。この趣旨を踏まえず、「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」についての本法における定義規定や、その背景となる科学的な知見を無視するような俗論や暴論が蔓延し、それに依拠した住民や議会からの批判が自治体を萎縮させているという声が当会にも多く届いている。このQ&Aが、地に足のついた議論の糸口になれば幸いである。
このような住民の意見や議会での質問は、20年前に巻き起こったジェンダーバックラッシュに近似する動きではないかとの指摘も、ヒアリングや議論の中で得られた。各論点について、しっかりと根拠のある反論を示すことが、バックラッシュを防ぐことにつながるのではとの意見が出ていたことも付記したい。
基礎事項などに関する疑問については、2023年12月に内閣府からQ&Aが出されている。加えて、2024年3月の参議院予算委員会において、立憲民主党の石川大我参議院議員の質問に対し、岸田総理からいくつか重要な答弁がなされた。「いわゆるトランスジェンダーの方に対する誤解に基づく誹謗中傷など、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別や偏見は許されないものであり、もとより自己のジェンダーアイデンティティを否定されるようなこともあってはならない。このように認識をいたします」などについては、広く自治体をはじめとして周知されるべきであると考えており、これらも手引きに収録している。
その他、省庁のさまざまな資料や、重要裁判例、国連機関などからの勧告についてもまとめて収録した。ぜひ、自治体をはじめ、この課題に関わる多くの人に活用いただきたい。
なお、本手引は、できるだけ多くの自治体に活用していただけるよう、自治体向けのデータ版は無料とした。データ版(自治体以外用)や、紙版(カラー、100ページ)は有料(それぞれ、500円(税別)、1500円(税別・送料別))で頒布しているが、作成・印刷経費等は当会で負担しているため、有志のカンパなどがあればありがたく思うことを末尾に記したい。
お求めはこちらからどうぞ。
2024.06.24 Mon
タグ:LGBT
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)