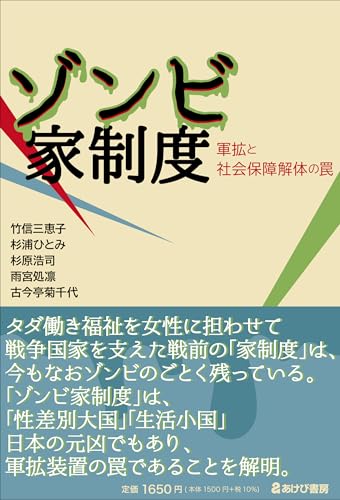views
3188
欠損を抱えて生きる 林葉子
2010.11.12 Fri
アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.
さまざまな成長物語を紹介する荒木さんのエッセイの、「自立」とは「どうやって人と関係していくかを考え続けられるようになること」という問題提起を受けて、引き続き「自立」という問題について考え、私なりに感じたことを綴ってみたい。
「自立」を他者との関係性の問題として考える場合、少なくとも私自身は、「自立」が可能だから誰かとの関係が上手く作れるのではなくて、むしろ「自立」したくてもできないという点でこそ、人とつながり、深く濃い人間関係が生じてきた、という感覚がある。
忘れがたい出会いについて思い出すとき、その思い出の中に登場する自分は、たいてい情けなく、惨めだ。本当は、誰かに弱いところなど見せたくはない。本当は、誰かにわざわざ会いに行くのは面倒くさい‥‥そんな見栄っ張りで無精者の自分が、それでも誰かに会いにいくのは、淋しいからだ。自分で埋められない心の欠損を、誰かに埋めてほしくて会いにいく。そんな時の自分は「自立」という言葉からは最も遠いように思える。
そうやって「自立」できない自分を、責めながら生きてきた。心の問題だけでなく、経済的な「自立」についても、私はずっと失敗続きだ。その「自立」できない私が、二十代の半ばで、赤ん坊という全く「自立」できない存在を産み、世話するようになると、いっそう就職への道は遠のき、夫への依存度が増して、私は結局、これまでに一度だって経済的に「自立」できたことがない。子どもの頃、専業主婦の母の愚痴を聞きながら「経済的自立なくして自由なし」と心の中で唱え続けてきた私であったのにもかかわらず。
「自立」をめざす人にとって、赤ん坊は鬼門だ。そもそも子どもは、自分一人でつくることはできない。妊娠から出産までのプロセスも、その後の子育ても、多くの人の手を借りなければ乗り越えられない。子育てには莫大な時間と費用がかかり、そうした負担を抱えることは、熾烈な競争社会で生き抜くのには、きわめて不利な条件となる。「自立」をめざす人が赤ん坊を産みたがらないのは、考えてみれば当然だ。子育てをとりまく世界は「自立」という概念とは真逆の「依存」に満ちた世界である。
しかし私は、ある時、ふと気がついた。私自身の経験に限って言うならば、これまでに私が生み出したもののうち、二人の子どもたちは、最も尊い。できることなら忌避したかった「依存」にまみれた関係性の中で産み育てられてゆく彼らは、私が自分の「自立」的な仕事として誇りをもって取り組んでいる研究論文と比較しても、圧倒的な尊さだと、私には感じられるのである。だからといって、ずるずると「依存」的になってゆく自分の日常の在り方を、簡単に許せるというものでもない。できることなら「自立」したいと、常に思っている。けれど、それができない自分の一面から生み出された結果が最も尊いという逆説に向き合うとき、その不思議さに私は打たれる。
それにしてもなぜ、人と人とは、力ではなく欠損を介して出会うのだろう? なぜ、命あるものは、そのような惨めさの中から生まれるのだろう? そして、そもそも私がその寄りかかり合いの関係性を「惨めさ」として受けとめるのは、なぜなのだろう?
そんなことを考えている時に、一冊の本と出会った。最近翻訳された『愛の労働 あるいは依存とケアの正義論』(エヴァ・フェダー・キテイ著、岡野八代・牟田和恵監訳、白澤社、2010年)は、私の出口のない自問自答に、さまざまなヒントを与えてくれた。キテイは「依存」の意味について考察を深めていく。一般的には「自立とは何か?」という問いから出発しがちであるけれども(私自身も、ずっとそうだった)、その発想を逆転させて、「依存」を起点として論理を組み立てている点が斬新だ。ここでの考察は、主に子育てや介護をめぐる問題を軸に展開されているけれども、より広い文脈から「依存」について考えるときにも役立つ本だと思う。人が皆「自律的な個人」であると前提する従来の政治思想は「依存者の問題を他者に押し付けることのできる特権を持った」人々だけに焦点を当てているのにすぎず、そんな人間像に基づく社会観は「架空の創造物」にすぎない、とキテイは喝破する(56頁)。無力な赤ん坊として生まれ、やがては老いて介護を必要とする人間にとっては、むしろ「依存状態」こそ基本であり、「依存」は「深い愛着が湧き出す源泉、人間の社会組織をつなぐ核としてむしろ大事にし」なければならない、と彼女は述べるのである(4頁)。キテイはその自らの政治思想を「みな誰かお母さんの子どもである」という言葉を軸に表現してゆく。
どうやら私は、「依存」を「惨め」と感じる自らの心性そのものについて、再考を迫られているようだ。どうしたって私は、この先も、さまざまな欠損を抱え、誰かに助けられながら生きてゆく。「依存」を厭うて目を背けるのではなく、「依存」の現実から出発し、人が人に上手く「依存」できるような社会のありかたを、むしろ積極的に考えていかねばならないのではないか。いつか個々人の欠損を、それぞれに大切な誰かとつながるための扉なのだと思えるようになったなら、その時は皆が、自分と周りの人たちを、今よりももっと好きになれるにちがいない。
次回「弱くてもかまわない」へバトンタッチ・・・・つぎの記事はこちらから
カテゴリー:リレー・エッセイ
タグ:家族、ケア、フェミニズム
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)