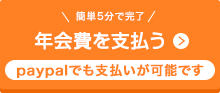「河野貴代美のボストン便り」は河野がもうボストンに居ないので、④回で終わりにします。
あとは、ボストンにいてそれぞれに活躍しながら、そのことがよく知られていない日本女性がいらっしゃるので、今後のボストン便りは、彼女たちへリレーバトンをお渡ししたいと思います。ぜひお楽しみに。
先ずはこの方です。(河野貴代美)
内田舞
小児精神科医、ハーバード大学医学部助教授、マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長、3児の母。2007年北海道大学医学部卒、2011年Yale大学精神科研修修了、2013年ハーバード大学・マサチューセッツ総合病院小児精神科研修修了。日本の医学部在学中に、米国医師国家試験に合格・研修医として採用され、日本の医学部卒業者として史上最年少の米国臨床医となった。趣味は絵画、裁縫、料理、フィギュアスケート。子供の心や脳の科学、また一般の科学リテラシー向上に向けて、三男を妊娠中に新型コロナワクチンを接種した体験などを発信している。
記事「コロナワクチンの情報発信で気づく日本の女性の生きづらさ」が注目された。
https://www.buzzfeed.com/jp/maiuchida/japanese-misogyny
Twitter: @mai_uchida
Instagram: @maimaiuchida

◆同意とは?
「同意」と聴いて皆さんはどのようなものを思い浮かべるでしょうか?
医師である私は医療行為のインフォームドコンセントが思い浮かびます。患者さんにとって必要な医療行為に関してリスクとベネフィット、医師として何を薦めるかを説明し、患者さんの希望を聞きながら一緒に次のステップを決定していきます。その際、患者さんが説明を受けた上で、「この医療行為をすることに同意します」とサインするのがインフォームドコンセントです。
近年、「同意」と聞くと、性的同意に関して思い浮かぶ方も多いでしょう。ヨーロッパでは性教育が義務化されており、フランスでは6歳から、フィンランドでは7歳から、ドイツでは9歳から、公立学校での性教育が始まり、人間関係の中での「同意」というコンセプトに関しても低年齢から紹介されます。性教育に関しては、日本では各学校の自由裁量だそうです。アメリカでは30の州で性教育が義務化されていますが、義務化されていない州もあります。分断の国なので教育も価値観も、同じ州の中でも地域や学校区ごとに全く違うこともあります。
◆息子達の学校から学ぶ幼児の同意教育
私の息子達が通うアメリカ・ボストンのプレスクールでは、2歳児のクラスから「同意」について教えられていました。もちろんこの年齢では、性的な同意でも、医療的な同意でもありません。人間関係の中で、自分の意思を表明すること、そして相手の意思を尊重することの重要性を学ぶための教えでした。
例えば、2歳児の教室のアクティビティにお茶を入れるというものがありました。ポットを使って紅茶を入れ、友達に「一緒にお茶飲まない?」と誘うアクティビティでしたが、そこで友達が、YESと言っても、NOと言っても、どちらの答えもリスペクトすること、と教えられました。友達と経験を共有することだけでなく、NOと言われた場合は「仕方ない」とムーブオンすることが日常の学校生活の中で教えられていることに、親の私はびっくりしました。
また、悲しそうな友人を見て、ハグしてあげたい、と思ったときに、”Can I give you a hug?”と聞くことなどを先生が説明していました。「一緒に遊ぼう」と声をかけられて嬉しいときもあるし、遊びたくないときもあるので、声をかけられた子に「一緒に遊びなさい」と言うこともありませんでした。
「これ、貸して」と自分が使っているものを友達が使いたいと言った場合も、「もう使い終わったから貸してもいい」と思うときもあれば、「まだ使ってる」というときもあり、どちらの答えでもいいと教えられていました。その教えのことを先生に尋ねると、友達とおもちゃなどをシェアするためには何よりも「自分が使っているものを使い終わるまで使ってもいい」「誰かに貸しても自分が必要なときには返してもらえる」と思える安心感が必要で、逆にもし「自分が使っているものが誰かに取られてしまうかもしれない」という不安が先行してしまうと、友達とのシェアが難しくなる、と説明され、なるほど!と思わされました。
私の子どもとその友達たちの交流を見ていると、「同意」は契約でもなく、同意がなければ何かが禁止されるというルールでもなく、「自分の身体や意思は自分のもの」という、自分を尊重する力を与えてくれるものだと感じます。私は子ども達に、自分を尊重する発言をしてもいいと学んでほしいと願っています。また、自分を尊重する判断を他者がした場合には、それが自分の希望と違っても、仕方がないとムーブオンできる考え方ができるようになってくれたらいいなと思っています。
◆言語化の重要性
息子達の友人で、新型コロナワクチンの子どもの治験に参加した子は数人いますが、治験においても、一個一個の手技に関して、親と子どもの両方への説明と両方からの同意が必要です。息子の友人の6歳の女の子で、親は治験に同意したものの、”This is my body and I don’t give permission.”と治験の中での注射を拒否したケースもありました。その場合、治験スタッフも「わかりました。では、また考えが変わったらいらしてください。」と6歳の子どもの同意を得られなかったことに関しても尊重した対応をしたそうです。その後、親子で話し合って、翌週治験に戻り、ワクチン(かプラセボ)を接種したそうです。
アメリカでは#MeToo を通して、大人間でも「同意」とは何かという議論が盛んに行われました。例えば、女性が仕事を失ってしまうから上司の性的なアプローチにNOと言えなかったシチュエーションは「同意」ではないこと、またNOと言わなかった=YESではないということなどを耳にする機会が増えました。今までムズムズと感じていた違和感を#MeTooムーブメントをきっかけに言語化できたと話す人も多く、私も「言語化」の重要性に関して考えさせられています。
また、人間関係における「同意」というのは、契約のような同意ではなく、二人の人間の間の同意なので、後から「やっぱり嫌だ」と気が変わってもそれを尊重し合う必要があります。言葉での意思表示が日本語だと難しいかもしれませんが、その分基盤にあるお互いへのリスペクトが重要なのではないかと思います。
◆違和感を信じて意思表明
私は、日本で育ったことも影響してか、なかなか自分の意思を表明できないこともあります。日常的に耳にする言葉やメディアで目にするイメージ、また育ったカルチャーの中で感じる雰囲気が我々に与える影響は予想以上に大きく、その中で違和感を感じても、「自分が気にしすぎかもしれない」「私の捉え方が間違っているのかもしれない」と考えてしまい、なかなか意思を表明できないのは私だけではないのではないでしょうか。もしかしたら怒りや悲しみを感じないようにと、「嫌なこともそんなに嫌がる必要がない」と自分を説得している無意識下の自己防衛の心理かもしれません。
しかし、違和感には必ず理由があるので、できるだけ自分の感覚を信じて、もっと楽にYES・NOの発言ができるようになりたいと思っています。また、YESでもNOでも自分の意思が受け入れられるだろうと安心して信じられる環境が広がってほしいと願っています。
問題点を認識すること、言語化すること、意見を表明すること、また互いの意思をリスペクトすること。子ども達が受ける教育から学ばせてもらっています。
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)