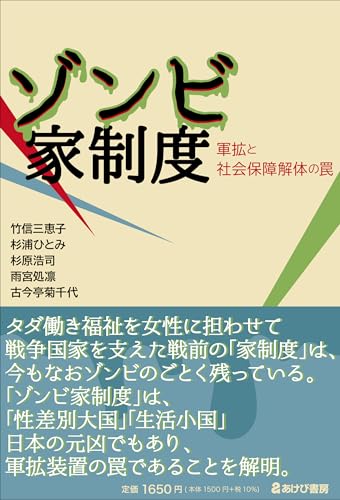2010.01.16 Sat
 ジェンダー論、フェミニズム、女性学、男女共同参画など、性をめぐる様々な事柄に関する言葉は多々ありますが、『女性学年報』は日本女性学研究会により創刊された「女性学」の雑誌です。1979年の創刊以来、刊を重ね、おかげさまで30号を迎えることとなりました。
ジェンダー論、フェミニズム、女性学、男女共同参画など、性をめぐる様々な事柄に関する言葉は多々ありますが、『女性学年報』は日本女性学研究会により創刊された「女性学」の雑誌です。1979年の創刊以来、刊を重ね、おかげさまで30号を迎えることとなりました。
今号では「書いてつないで30年」をテーマに、特集「30周年記念特集『女性学年報』30号によせて」では、歴代の編集委員長に当時をふり返っていただき、また読者、執筆者の方々にも『年報』への思いに関するエッセイをいただいています。そこで、今回の特集では、『女性学年報』30周年を記念して、編集委員会の小山有子さんと森松佳代さんにお話を伺いたいと思います(聞き手のB-WAN荒木も『女性学年報』の編集委員でもあります)。
フェミニズム、女性学が勢いを失い、さらにはそれらへの反発も高まりつつあると言われる昨今ですが、その中で『女性学年報』は、どのように執筆者、読者の思いをつないできたのか。「学」とつく「女性学」はやはり権威主義から逃れられないのか。「女性学」の文章は他の論文やエッセイとはどう違うのか。そのような「女性学」への思い、未来につながる悩みや迷いをお伝えできたらと思います。
※『女性学年報』は、日本女性学研究会サイトhttp://www.jca.apc.org/wssj/
もしくはオフィス・オルタナティブ06-6945-5160 begin_of_the_skype_highlighting 06-6945-5160 end_of_the_skype_highlightingよりご購入いただけます。
【「女性学」の模索】
荒木:
今号は『女性学年報』(以下『年報』)の30周年記念号となるわけですが、今号掲載の上野千鶴子さんの文章にもありますように、『年報』は当初、女性たちが「書きたいことはあふれていて、聞き手はどこにもいなくて、そして既存の雑誌は、とても載せてくれそうにない時代」に創刊された「女性学」の雑誌であったということです。そういった状況はたしかに変化しつつある30年後の今というのは、もはやこのような雑誌は必要ないのか、という、いきなりヘビーな問い(笑)が突きつけられざるを得ない状況でもあります。
しかし同時に、この『年報』は、「既成の『学問』」が「女の視点欠いた」「ゆがみをもった」であった、そういったことへの告発としての「女性学」をどのように表現するかについて、ずっと模索を行ってきて、女性を取り巻く状況が様々に変化する今は、まさにその模索の通過点にあるということもできます。
小山:
その模索の中で大きなものに、投稿論文にたいするコメント制度というものがあります。このコメント制度は、「いろんな意味で『支援』し、『一緒につくりあげていく』プロセス」、「覆面レフリー」ではなく「顔を出して、書き手と双方向で、お互いに納得のいくやりとりをして論文を書き直すプロセス」(『女性学年報』30号より)として続けられてきました。 いわゆる「査読」とは全く異なったものであったわけですね。
荒木:
小山さんが実際コメントをされてきたり、他の方のコメントをご覧になる中で、感じたことなどありますか?
小山:
『年報』で扱う論文やエッセイは、「個人的なこと」から出発し問題を考え、伝えるというものであることが特徴的です。最初に投稿を受け取るときは、強い思いが込められている文章であることもしばしばあるのですが、そのような、いわば「思い」が吐き出されたような論文が、編集委員やコメンテーターとのやりとりを通じ、次第に思いのエッセンスが整理され、伝えられる可能性のある読者の方によりパワフルに伝わるものとなっていくことは、コメント作業の醍醐味だと感じます。
荒木:
しかし、たしかにコメントする上で、当初の投稿者の意図を軽んじて型に押し込めてしまわないか、という懸念は常につきまといますね。
小山:
そこが難しいところですね。ただ、コメンテーターもまた、投稿者から得ているものも大きく、決して一方通行ではないやりとりではないというところが面白いですね。
荒木:
通常、一つの投稿論文やエッセイへのコメント作業のチームは、投稿論文の専門性に明るい人と、そうでない人両方が入っています。なので、必ずしも自分の関心と直結するわけではない文章と向き合うことになります。そういう時、自分が日常的に気にはなっていたけれど言語化できないことが、投稿者の論文の中で言葉にされているのを見て胸がすくような思いをすることもあります。
小山:
社会的な物事を扱う文章の場合、自分と全く関係しない論文はないと思います。特に「女性学」の論文の場合、「個人的なことは政治的なこと」と言いますが、どうしても自分の問題として考えながら読んだりコメントしたりしてしまうこともあります。そういう意味では、コメント作業はコメンテーターにとっても、執筆者にとっても、しんどいことでもあります。物理とか化学の論文と向き合うのとはその辺りが異なるのかもしれません。 昔、理系から文系の女性学に研究分野を変更した知り合いが、「こっち(女性学)のほうがしんどい」と言っていたのですが、そういうことが関係しているのかなと思います。
【立場の違う者同士の対立】
荒木:
理系のほうがしんどいように思いますけど(笑)、たぶん、違う種類のしんどさなんでしょうね。より「日常」に直結しがちな問題であると、どうしてもそれぞれのコメンテーターや編集委員で立場や意見が違い投稿論文をめぐって対立する、ということが多く起こりがちであり、皆さんもそういったことを経験されてきていると思うのですが、そのあたりいかがですか?
 ←小山&荒木の「デコ年」(今年はまだ地味目)
←小山&荒木の「デコ年」(今年はまだ地味目)
小山:
『年報』では、投稿いただいた論文の中から、最初に、コメント作業に入る論文を選ぶのですが、コメント作業に入っても取り下げがなされるケースもありますね。多かれ少なかれ、『年報』に投稿していただく論文は、その執筆者の方が思いを吐き出す文章であるわけですので、掲載に到った論文でも、コメント作業の中で執筆者、編集委員、コメンテーターの「格闘」を経ています。もちろん最初からそんなに新たな提案が必要ない状態の方もいますが…。
森松:
今号の特集で、コメント制度について書いてられるのを読んで感じたことは、だんだん、コメントする側が気を遣いだしたかな、ということです。昔はもっと、コメンテーターと執筆者がバンバンぶつかりあっていて、今から考えるととても失礼なコメントもしていたと思います。
でも、最近は、こんなコメントをしたらハラスメントになるかな、と思って躊躇してしまったり、たかがコメントぐらいで人間関係壊すなんてもったいない、みたいな姿勢があるように思えます。それは、やっぱり、同じ女性、というよりはいろんな立場の人が物を言い出したからかと…。
荒木:
私は最近のことしか知らないのですが、今もコメント作業は「格闘」だなあと常々思うのですが、昔はもっと激しかったんですね。それは、昔はいろんな立場の人がいなかったということなのでしょうか?
森松:
そこまで、それぞれの立場の違いが見えていなかったのかもしれません。というよりは、コメント作業とは、失礼なことを言ったり傷ついたり、また自分も傷ついたり、とか、そんなもんだとみんなが割り切っていたような感じがします。
小山:
コメントは厳しい査読、ではなく一緒に論文を作り上げていく作業とはいえ、実際に起こっていることはかなり厳しかったのですね。
森松:
今から考えると厳しいぶつかり合いだったかもしれませんが、当時は会ってコメントしてたことが大きいのではと思います。以前、執筆者、コメンテーターの間で、お互い一歩も引かないようなとても激しい「ぶつかり合い」があったんですが、その状況に嫌気が差し去っていくのではなく、なんと今度は編集委員として参加されました。意見の相違や論争があっても、その当事者がずっと『年報』に関わってくれているということは嬉しいことです。もちろん、お互い分かりえないまま決別することもありますが…。
荒木:
激しい衝突を経験された執筆者の方々が、逆により関心を持っていただいたのはなぜでしょう?
森松:
やっぱり、意見が違うからといって排除しない、内輪だけで篭ってなあなあにならずぶつかり合う、という雰囲気があったからかなと思います。閉鎖的になると、どうしても自分と違う立場について堂々と批判を言わない、という状況になってしまいますし。
荒木:
そのような場合は、合わない個性同士でも、批判し合えることが上手く作用したのかもしれませんね。ただ、自分と異なる意見に疑義を挟み批判し、衝突が起きるということを、どう解決に向けていくかということは、やはり、難しい問題だと思います。
森松:
納得がいかない点やぶつかり合うことが多くても、それよりも論稿の内容の中で政治的に「これはこの時期言っておかないといけない」という気持ちのほうが強く執筆者、コメンテーターで共有できて、結果としてスムーズにコメント作業が進むこともあります。
荒木:
上手く、対立を超えて関係性を作っていけたらいいのですが、「こういうことが正しい」と思ってコメントすると、実はその「正しさ」から抜け落ちてしまっている、自分と異なる立場の誰かを傷つけてしまうという危険性もありますしね。結局、どうしても様々な視点や立場の人がいるわけで…。
小山:
執筆者も、編集委員も、コメンテーターも、いろんな声を出すことができて、その中で、「今の時点」で考えうる可能性をかんがえることが大事なのではないかと。例えば、バックナンバーを読んでいて思うことなのですが、5年前10年前に行われていた議論が今でもまだ同じようなことが行われていることがあります。
荒木:
それは、議論しても結局社会は変わらない、ということ…?
小山:
そうではなくて、その時々の人たちが、その問題について考えていた証拠として見ればいいんじゃないかと思うんです。社会がそれだけ変えにくいものなんだ、という自覚にもつながりますし、でも昔のみんなも、私たちと同じように一生懸命その問題を考えていた、という。
荒木:
なるほど、自分ひとりじゃない、という心強い感覚ですね。そういうわけですのでぜひ皆様『年報』バックナンバーもお手にとって見て下さいませ(そして気に入ったらご購入のほうも(笑))。
小山:
今の時代は情報に溢れていて、自分が何かしたいと思ったらすぐできる、何か欲しいと思ったらすぐ手に入る状態にあるとは思うんです。でも、自分ではない他者は、自分と同じとは限らない。政治や経済でも、成果をすぐに求めすぎる傾向にあると思います。昨年、政権交代がありましが、三ヶ月立っても変わらないって、最近批判の声をよく耳にしますが、三ヶ月じゃあそりゃそうだろうと(笑)。何か言ったら人がすぐ変わる、社会がすぐ変わるという錯覚は危険なのでは。
荒木:
ゆっくり変わっていくことも大切ですね。結果ばかり大事にされる世の中では、プロセスや関係性の大事さに目を向けることも必要だと思います。『年報』のコメントや編集作業も、こういったことを忘れてはならないなと思います。
次回、「『女性学年報』30年をふり返る【後編】」では、なぜ今の時代に「女性学」なのか? また、今号のバラエティに富んだ投稿論文のご紹介をさせていただきたいと思います。
創刊号の編集長であり、現在に至るまで継承され続ける『女性学年報』のあり方を形作ってこられた上野千鶴子さんよりメッセージをいただきました。【前編】ラストを飾らせていただきたいと思います。
———————————————————
『女性学年報』30号が刊行されました。
創刊号から30年、この号は30周年記念号になります。
上野は創刊号の編集長でした。30年分の回顧と証言が掲載された歴史的な号です。
巻頭論文は、桂容子さんの「フェミニズムと男女共同参画の間には、深くて暗い河がある」。
桂さんは民間人から公設女性センターの館長職を経験した人。
インサイダーでなければ書けない、内部情報や行政の問題点が具体的にえぐられています。
外から見ていて、うすうすそうではないかと感じていたことが、やっぱり、と納得できる報告でした。女性センターが「事業仕分け」されかねしない今日、必読文献だと思います。
女性学・ジェンダー研究の学術誌は増えましたが、こういう現場レポートは他誌には載りそうもない
『女性学年報』ならではの、貴重な情報発信でしょう。
民間人から女性センターの職員や管理職を経験した人たちは他にも多いはず。具体性のある報告や分析、課題や提言がもっと出てきてほしい、と思います。
他にも
石河敦子さん「総合職経験を持つ大卒専業主婦にみる性別役割意識の変容」
木下尚子さん「DV被害者支援をおこなう民間シェルターの課題」
石井香里さん「レズビアンのパッシング実践の可能性について」
木村尚子さん「『産ませること』から『選択的に産ませること』へ」
山家悠平さん「遊廓の女性たちがみた『近代』」
など、興味深い研究論文が満載です。
————————————————-
『女性学年報』のお買い上げは、日本女性学研究会サイトhttp://www.jca.apc.org/wssj/
もしくはオフィス・オルタナティブ06-6945-5160よりどうぞ!
カテゴリー:シリーズ
 慰安婦
慰安婦 貧困・福祉
貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント
DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚
非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ
セクシュアリティ くらし・生活
くらし・生活 身体・健康
身体・健康 リプロ・ヘルス
リプロ・ヘルス 脱原発
脱原発 女性政策
女性政策 憲法・平和
憲法・平和 高齢社会
高齢社会 子育て・教育
子育て・教育 性表現
性表現 LGBT
LGBT 最終講義
最終講義 博士論文
博士論文 研究助成・公募
研究助成・公募 アート情報
アート情報 女性運動・グループ
女性運動・グループ フェミニストカウンセリング
フェミニストカウンセリング 弁護士
弁護士 女性センター
女性センター セレクトニュース
セレクトニュース マスコミが騒がないニュース
マスコミが騒がないニュース 女の本屋
女の本屋 ブックトーク
ブックトーク シネマラウンジ
シネマラウンジ ミニコミ図書館
ミニコミ図書館 エッセイ
エッセイ WAN基金
WAN基金 お助け情報
お助け情報 WANマーケット
WANマーケット 女と政治をつなぐ
女と政治をつなぐ Worldwide WAN
Worldwide WAN わいわいWAN
わいわいWAN 女性学講座
女性学講座 上野研究室
上野研究室 原発ゼロの道
原発ゼロの道 動画
動画


![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)