
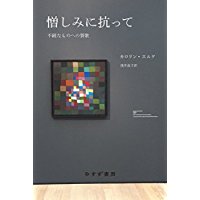
憎しみを公然と言い、それが政治的に正しい態度のようになっている、これはもはや世界中でみられる現象です。そうした憎しみのメカニズムを見つめ、「基準とは異なる人を攻撃してもかまわない」という流れに抗う生き方を模索します。
「本書で取り上げる憎しみは、個人的なものでも偶然の産物でもない。ついうっかり、または本人たちに言わせればやむにやまれぬ必要性にかられて口にされる、あいまいな感情ではない。ここでの憎しみとは集合的なものであり、イデオロギーという器に入っているものだ」(本書より)。
あらゆる場所で同じような現象が起こっていますが、それはポピュリズムの台頭のせいで起こった最近のことではないと、著者エムケはいいます。そこには長い憎しみの蓄積とその正当化があります。
エムケは、2015年の難民排斥事件や、白人警官による黒人男性への暴力事件をとりあげ、そこで何が起きていたかを描写します。そこにいるのにあたかも見えないかのように人を扱うこと。「我々は民衆だ」という言葉が難民排斥のスローガンに転用されたこと。侮辱を「おおらかに受け流せ」という暗黙の要請。そして、暴力を受けたエリック・ガーナーの「もううんざりだ。今日で終わりにしよう」という言葉。
注目したいのは、「不純なものへの賛歌」という言葉で、人びとや社会の多様性を描き出しているところです。多様な社会と言いつつも背後に見えてしまう均質な人間像とはちがう、自分の中の他者性、他人の他者性を前提とした、葛藤含みのヴィジョンを言わんとしているように思えます。
自分とは「違う」存在をつくりだし攻撃するという、世界的に蔓延する感情にまっすぐに向き合った本書は、ドイツでベストセラーになりました。今の世界を読むために、おすすめします。 (鈴木英果:みすず書房編集部)






![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)











