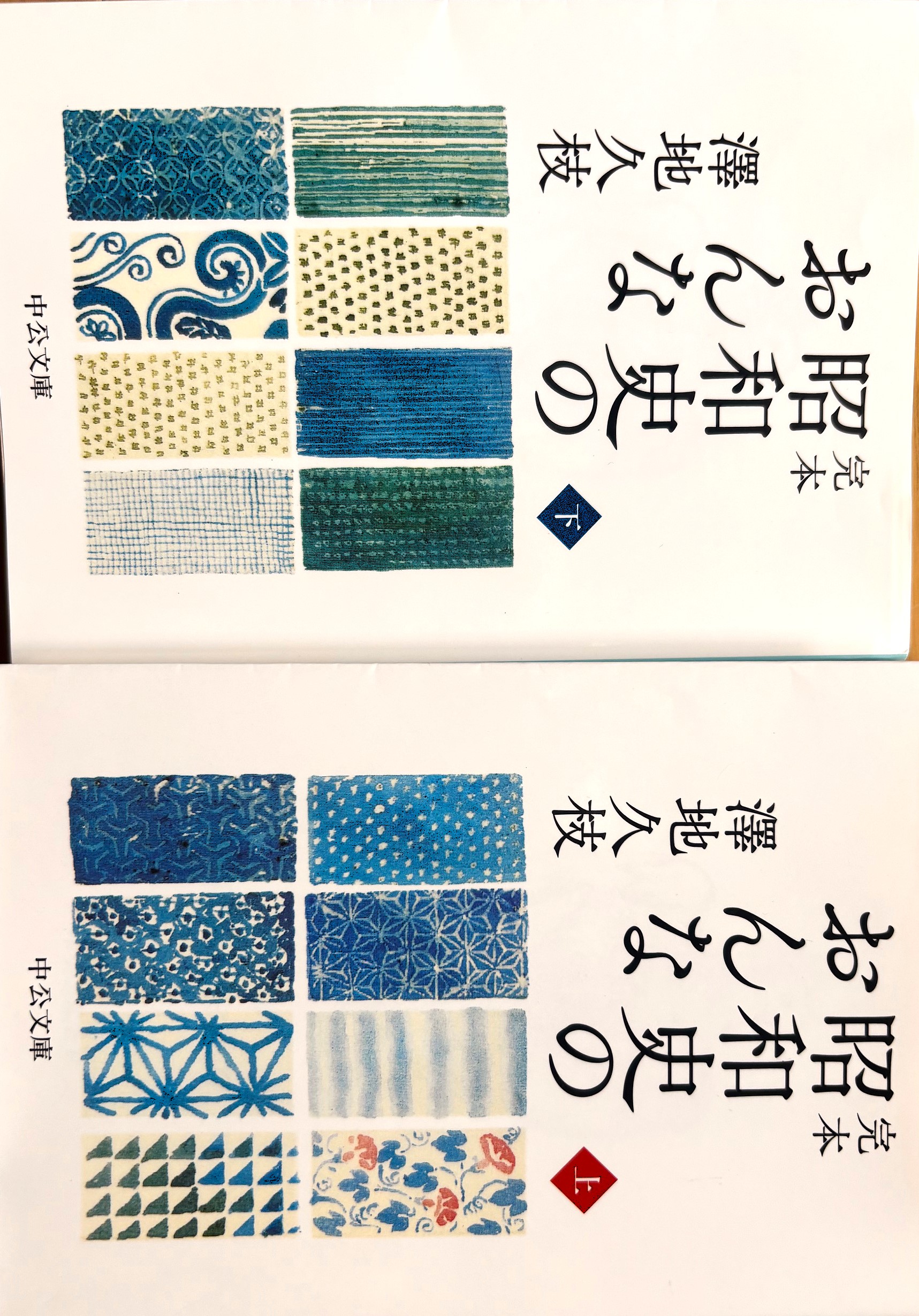
NHKラジオ深夜便「本のほんもの」を夜11時~夜中の1時まで聴いて、あんまり面白いので眠れなくなった。元・文春編集長で社長だった平尾隆弘さんとアンカーの服部祐規子さんの話に引き込まれてしまって。平尾さんが文藝春秋で編集を担当した作家の立花隆や山崎豊子、野坂昭如などのこぼれ話が楽しい。それに平尾さんのおススメで生まれた澤地久枝著・完本『昭和史のおんな』(上)(下)(中公文庫・2024年10月)の出版経緯も語られ、「この本、ぜひ読まなくちゃ」と思って、すぐに本屋へ走る。
澤地久枝さんは「あとがき」で、『昭和史のおんな』は昭和五十四年(1979)五月号から月刊『文藝春秋』で連載が始まったこと。それ以前に約二年間の準備期間があったと書いている。当時の編集長・半藤一利のもと、綿密な資料調べに基づく、まるで小説のような、ドラマのような史実に圧倒される思いで読む。
澤地久枝さんは五味川純平の長編『戦争と人間』の助手として十年近く、戦争の「昭和」を調べ、巻末注を書く時、当時の新聞の縮刷版を丹念に調べて、政治、経済はじめ三面の社会記事だけでなく、写真や広告も見落とさず、それぞれの時代相を反映するものを手書きでうつしとったという。すごいなあ。
その後、『妻たちの二・二六事件』を書いて、澤地さんは作家として一人立ちする。「歴史の網の目からこぼれ落ちて知られず、忘れられた有名無名の女たち。その「おんな」たちの人生をはめこんでゆかなければジグソーパズルは完成しない」との思いで、「思想弾圧への命をかけたたたかい」「国際結婚」「戦争後遺症」「堕胎(妊娠中絶)」「認められぬ恋」「情死」「保険金殺人」「欺いた男への報復」などを上巻(十章)下巻(六章)にまとめている。その「おんな」たちの子や孫を各地に訪ねてたどった史実は次の時代の私たちにもつながってゆく。「おんな」を書くとは、また「おとこ」を書くことでもあったという。
ああ、それにしても私、こんなに昭和史を知らなかったとは。歴史の中に埋もれてしまった「おんな」たちを、1970年代~1980年代にかけて「澤地さん、よくぞ調べてくださった」との深い感謝の思いしかない。
上巻の「妻たちと東郷青児」の章。「昭和四年三月、朝刊社会面トップに「洋画の鬼才東郷青児氏/愛人と情死を企つ」とのスクープが載った。この時東郷には二人の妻がいた」。さて次々回のNHK朝ドラ「ブラッサム」の主人公・宇野千代と東郷青児の関係は、どう描かれるのだろうか?
「井上中尉夫人の自決」の章では「満洲事変(昭和六年・1931)勃発後、軍人の夫の出陣前夜に二十一歳の新妻(千代子)は謎の自決を遂げた。やがて事件は、軍国妻の美談へと仕立てあげられていった」とある。戦地に赴く夫に後顧の憂いを絶たせるために、ということなのか? 千代子の自刃から「大日本国防婦人会」が生まれたことは、彼女自身も与り知らぬことだったかもしれないが。
今、放映中のNHK朝ドラ「あんぱん」にも登場する「大日本国防婦人会」は、1932年~1942年の10年間に全国会員が一千万人にものぼった。明治三十四年創設の「愛国婦人会」は40年の歴史をもち、共に会員の奪い合いなど拮抗していたが、太平洋戦争下、「大政翼賛会」の下部組織として合併、「大日本婦人会」となったという。「おんな」たちも、あの戦争を、しっかりと担ったのだ。
「杉山智恵子の心の国境」の章では、「昭和十三年初頭、杉本良吉は女優岡田嘉子と共にロシアへと越境した。残された杉本の妻、杉山智恵子は病いの床で孤独なたたかいを続けた」とある。杉本良吉は越境後すぐにスパイ容疑で検挙、銃殺されたが、岡田嘉子はその後も生きて九十歳の天寿を全うした。
下巻。「日中の懸橋 郭をとみと陶みさを」の章。「郭沫若、陶晶孫の妻として日中戦争の“時代”を生きた佐藤をとみ・みさを姉妹。今は中国に住む姉と日本に住む妹の辿ったそれぞれの人生」。澤地さんは当時、八十六歳の佐藤をとみ(中国名・郭安娜)の取材のために上海と大連へ飛ぶ。
下巻の最終章に加えられた「雪の日のテロルの残映」では、「二・二六事件(昭和十一年・1936)で惨殺の渡辺錠太郎大将の次女は九歳で事件を目撃。戦後修道院へ」とある。父・渡辺錠太郎の最後の姿を、わずか九歳で目撃した渡辺和子は後に修道女となり、ノートルダム清心学園(岡山市)の理事長となる。著名なカトリックのシスター・渡辺和子が、あの二・二六事件で惨殺された父親の最初の目撃者であったことを改めて知る。
また1970年11月、「憲法改正」を求めて自衛隊に決起を呼びかけた三島由紀夫が、『英霊の声』で、「などてすめらぎは人間となりたまひし」と書き、天皇の「人間宣言」を批判し、霊媒を通してあらわれる二組の神霊たち「兄神である二・二六事件の決起将校たちの霊と弟神である特攻隊の若者たちの霊」の「怨みと憤り」の声を記していたことを、現代に引き寄せて再び思い返した。
澤地久枝さんは1930年生まれで現在、九十五歳。今もお元気に「九条の会」の呼びかけ人として先頭に立つ。確か数年前、腰を骨折されて身動きがとれなくなったと、『婦人公論』の上野千鶴子さんとの対談で読んだことがある。その時、あの澤地さんが介護保険のあることを全く知らなかったと知って、もう、びっくり。後に「介護保険を使えると教えてもらい、ほんとにありがたかった」と言われて、その後、病院にも行かず、自力で回復。しばらくして沖縄の集会へ颯爽と出かけられたとか。さすが澤地久枝さんだ。
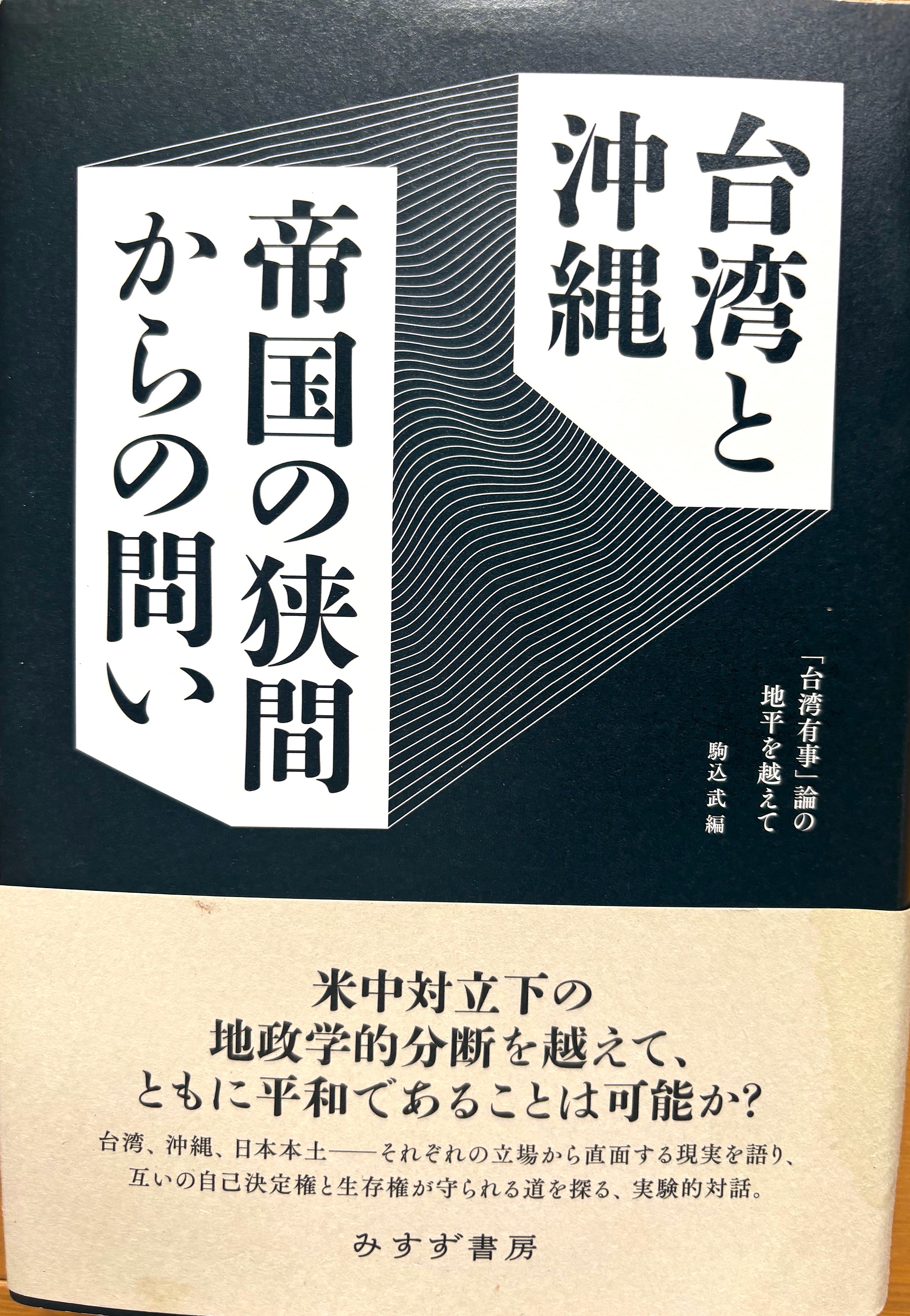
そしてもう一つ、知らない歴史を知ることになった集会に参加する。5月31日、SNSで知った駒込武さんの講演「台湾と沖縄 帝国の狭間からの問い」(主催・京都教区カトリック正義と平和協議会)へ出かける。駒込武編『台湾と沖縄 帝国の狭間からの問い 「台湾有事」論の地平を越えて』(みすず書房・2024年10月)にもサインをいただいた。
安部晋三元首相が2021年12月、「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある」と言った。もちろん「台湾有事」は起こしてはならない。だが、駒込さんは「台湾有事の地平を越え、台湾や沖縄の「歴史」と「現在」から発する問いかけに、もっと耳を傾けなければならない」と主張する。過去から現在まで台湾・沖縄が置かれてきた「狭間」の歴史を、台湾や沖縄に何度か訪れながらも私は一体、何を、どれだけ知っていたのかと、講演を聴き、本を読んで恥ずかしくなった。ならば知らなかったことを、きちんと知らなければいけない。
1895年、日清戦争後の下関条約で台湾は清国から日本に割譲され、1945年の日本敗戦まで50年間、日本の植民地・統治下にあった。後藤新平をはじめ民政長官による「内地延長主義」の統治政策により、日本語学習や鉄道敷設、水利事業など「同化政策」を推進していく。1937年、日中戦争勃発後は「皇民化政策」のもと、台湾語、客家語、原住民語の使用を抑圧・禁止、日本式生活習慣をもつ家庭を「国民の家」と認定、進学、就職、商売の認可などの優遇施策を講じた。
1943年の「カイロ宣言」でルーズヴェルト米大統領、チャーチル英首相、蒋介石中華民国総裁の間で台湾の中華民国「返還」を定める。その後の「白色テロ」の時代、台湾では1947年~1987年まで戒厳令が続く。そして1971年、ニクソン米大統領の中華人民共和国訪問後の1972年2月、米中・日中共同声明。同9月、日中共同声明により「中華人民共和国政府は、台湾は中国の一部分であると主張していることを認識する」とされた。
しかし台湾は戒厳令解除後、2014年の「ひまわり学生運動」に始まる民主化の道を進めてゆく。IT相に就任したオードリー・タンを中心に運動はITを駆使して、どんどん多様化していく。「台湾の持つ価値は、自由、民主、多様性、寛容」と第七代蔡英文中華民国総統は言い、2020年の総統選の投票率は75%にのぼった。2019年5月には台湾でアジア初の「同性婚特別法」が成立する。
沖縄もまた同じ。15世紀、琉球王国は明・清と冊封関係を結ぶ一方、薩摩・島津藩の琉球侵攻(1609年)以来、徳川日本にも従属。明治十二年(1879年)、明治政府は「沖縄県」を設置し、第一次「琉球処分」がなされる。日清戦争後、琉球諸島は日本領土となり、さらに第二の「琉球処分」とされるサンフランシスコ講和条約(1952年)では、日本が独立国となるのと引き換えに沖縄に軍事占領の継続を認めることになる。
第三の「沖縄処分」ともいえる1972年の「沖縄返還」をめぐる米国との交渉にあたり、密約があったことは知られているが、最近の時事通信、共同通信の記事(2025年5月26日付)には、「沖縄返還を目指す佐藤栄作首相(当時)の密使を務め、核兵器持ち込みに関する「密約」にかかわった国際政治学者若泉敬氏の遺書を預かっていた知人が、沖縄戦の組織的戦闘が終わった「慰霊の日」(6月23日)に沖縄へ寄贈することになった」とある。若泉氏は1994年出版の著書で、沖縄返還にあたり、有事の際に沖縄への核兵器持ち込みの密約の存在を明らかにし、「歴史に対して負っている私の重い『結果責任』を採り、自裁します」と記して、その2年後に自殺したという。
しかし沖縄の若い人たちは決して負けない。「軍事化に抗う石垣島の民主主義」の章で、宮良麻奈美さんは自衛隊基地建設に抗する闘いをしっかりと記す。また本書に採録されたシンポジウム「台湾と沖縄 黒潮により連結される島々の自己決定権」(2023年7月8日、京都大学で開催)でも、若い人たちの発言が次々と語られてゆく。
台湾と沖縄は海続きの世界だ。『新沖縄文学』編集責任者だった川満信一さんは、フィリピンから台湾を経て沖縄、韓国済州島に至る「黒潮ロード」を非武装地帯とする構想を提唱した。日本「本土」中心の「一国平和主義」を超えた東アジアの「平和」は、そこにあるのではないかと。
帝国の「狭間」にある台湾と沖縄から「東アジアの非武装地帯を」と呼びかけた川満信一さんが、本書の出版直前に亡くなられたことを、最後に駒込さんは言葉を詰まらせながら語り、講演を結ばれた。
まだまだ知らないことばっかり。でも大事なことは知らないといけない。そしてそのことを次の世代につないでいかなければ。さあ、歳になんか負けてはいられないぞ。「もっと本を読み、話を聴いて、しっかり自分で考えて」と思う、今日この頃。
ご参考に。これまでの私のエッセイから
澤地久枝さんのこと
戸籍なんて、いらない!(旅は道草・138)
沖縄の今
沖縄に原発はない(「旅は道草」・18)
オキナワからヤマトが見える(旅は道草・32)
女の友情は変わらない(旅は道草・81)
台湾へ行く
ひとにやさしい・台湾(旅は道草・39)
オードリー・タンの、透明性と共感力(旅は道草・142)
台湾満腹「おいしい!」と「ほろ苦さ」と 『台湾漫遊鉄道のふたり』(旅は道草・166)






![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)












