 著者・編集者からの紹介
著者・編集者からの紹介
-
水無田気流著『「居場所」のない男、「時間」がない女』(ちくま文庫) 砂金 有美

2020.05.15 Fri
大人になった「私」の時間は「私」のものではなくなるのだろう。暗い予感を子供の頃から意識せざるを得なかった。「母」の時間は、「祖母」の時間は、まわりで生きる「女」たちの時間は、仕事の有無にかかわらず見事に家庭に溶けていた。なんてこった。勘弁してくれ。すると私が「息子」であれば万事ハッピーな人生だったか? わからない。そちらはそちらで、違う…
タグ:本
-
大田美和著『『世界の果てまでも』 女たちは世界の果てをめざす 大田美和
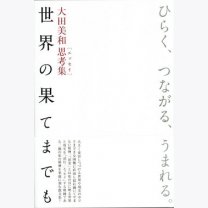
2020.05.06 Wed
短歌を作り、詩を書き、イギリス小説についての論文を書き、文学とジェンダーについて大学で教えている著者による、初めてのエッセイ集です。47のエッセイ(書評を含む)と2つの対談が収められています。文学、美術、音楽、歴史、国内外での講演、「「女の平和」国会ヒューマンチェーン」への参加、両姓併記パスポートなどトピックは多岐にわたります。 「女の…
タグ:本
-
岩淵宏子・長谷川啓監修『[新編]日本女性文学全集』全12巻、ついに完成 ◆岩淵宏子

2020.04.29 Wed
書名 『[新編]日本女性文学全集』全12巻 監修 岩淵宏子・長谷川啓 出版社 六花出版 刊行 2007年8月~2020年3月 定価 各巻5000円+税 本全集は、近代出発期から現代までの女性文学を集成した日本で初めての女性文学全集である。 従来、女性文学の評価は男性文学に比して極めて低く、例えば筑摩書房刊『現代日本文学全集 増…
タグ:本
-
川 恵実 NHK ETV特集取材班『告白――岐阜・黒川 満蒙開拓団73年の記録』 「性の接待」――史実を受けとめ、支え伝える群像 ◆三輪ほう子
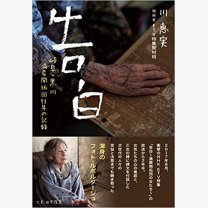
2020.04.04 Sat
「性の接待」――戦後75年を経た今、私たちはようやく、このあまりにも凄惨な史実を知ることになりました。加害/被害、敵/味方に留まらず、その心の奥底に閉ざされた「内なる加害」への声を感受できる時代・社会になりつつある、ということなのかもしれません。 2017年放送のNHK ETV特集「告白~満蒙開拓団の女たち~」は、日本の社会に大きな衝撃…
タグ:慰安婦 / DV・性暴力・ハラスメント / 憲法・平和 / 本
-

2020.04.02 Thu
書 名 川へ 著 者 斎藤よし子 刊行日 2020年2月10日 発 行 鳥影社 定 価 1400円+税 推 薦 上野千鶴子 「旅と文学は斎藤さんにとって変身のツールだ。 主婦の日常から脱して、いろんな「私」になりかわる。 そして斎藤さんの想像力は、人々の屈折や襞にそっと届く。 解はない。誰もが人生の途上だからだ。」 喜寿の記念として出版…
タグ:本
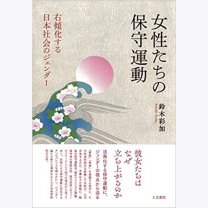
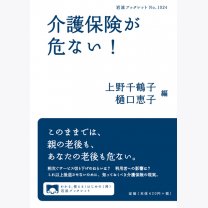
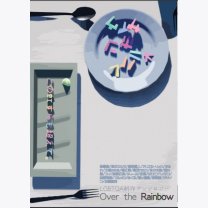
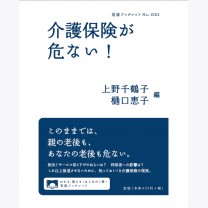
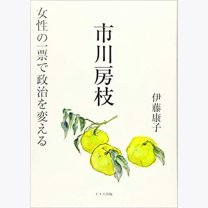






![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)











